
一木康広
塾長の考え(夏期講習)②
2024-07-26
夏期講習が始まった最初の週末。 とりあえず一週間。 感想としてはまずまずかな。 やはり「まとまった時間」が、 これだけ連続でとれる夏期講習は、 小中学生にとっては、 かなり学力...



一木康広
2024-07-26
夏期講習が始まった最初の週末。 とりあえず一週間。 感想としてはまずまずかな。 やはり「まとまった時間」が、 これだけ連続でとれる夏期講習は、 小中学生にとっては、 かなり学力...



小野寛明
2024-07-26
今日は出産祝いにご両親から娘さんにプレゼントされたベビーリングをご紹介します。 7月に無事ご出産されました。 おめでとうございます! 7月の誕生石は「ルビー」。 誕生石は守護石と言われ、お守りとしても身...



矢田美麗
2024-07-26
千葉県 市川市 船橋市のピアノ教室〜発達障害ピアノレッスン【My Piano room】の矢田美麗です(^^) 今日は以下について投稿してみたいと思います。 [囲み装飾]《過去の関連記事》 ・子育て持論「...



中野雅夫
2024-07-26
子育てを大変にしているのはお母さんの育てら方なのです 自分の子供頃特に幼児期の頃覚えていますか? 子育てはお母さんの心の動きに影響されます 勉強会していて、時々不思議に思うことがあります 勉強会をす...



吉田洋一
2024-07-26
小学生(6歳から12歳児編)における発達の症状の特徴を解説します。今回は65回目です。誤解のないように申し添えますが、ここで述べているのは、1回目で解説しているとおり、子どもの外側からみた行動の観察です。子どもが...



井川治久
2024-07-26
(高2男子)次回8月1日ですが「体調不良」なら「お電話」を! ・・・・・・次回、 ◆8月1日(木曜日)17時30分~20時30分。 ・・・・・・ただし、 ◆「体調が良くない」場合、・・・・・・お電話くださ...



一木康広
2024-07-25
今週の頭から始まった夏期講習。 この夏期講習の期間は、 肉体的にも時間的にもきつい。 初めて夏期講習を、 塾講師として、 経験したのは平成元年の7月。 あっという間に夏が...



一関港
2024-07-25
夏期講習が始まりました。 今年の夏期講習は、いつもと異なり 一斉指導を受講している生徒が一番多い学年は 中学1年生 です。 彼らの国語の一斉指導では、文章の内容を 踏まえて、私の「脱線」が多々起こります。 ...



漆間文代
2024-07-25
みなさま こんにちは ワクワクピースの漆間文代です 今日も暑かった( ̄▽ ̄;) でも… 夏休みの宿題をして 外遊びをしたいこどもたちだけ 外遊びを楽しむこどもたち… 暑いから 中に入ろうよーって言っても...



井川治久
2024-07-25
(2024年7月25日)高2男子から「欠席」の留守電。 ・・・・・・15時15分に、 ・・・・・・生徒本人の声で、 ◆「欠席」の留守電 がありました。 (その後)当方から、何度か、折り返していますが、「...



小西一航
2024-07-25
ブログを更新しました! 今回の担当は横浜オフィス所属の社会保険労務士有資格者、鈴木です。 特別支援学校高等部在学中の息子の話さんが、はじめておつかいをこなしたそうです! 記事を読む



相原尚美
2024-07-25
インターネットの記事やSNS 色々な情報が溢れています。 有益なものもあれば フェイクのものもあります。 音楽教育や指導においても然り。 だからこそ、 ...



吉田洋一
2024-07-25
小学生(6歳から12歳児編)における発達の症状の特徴を解説します。今回は64回目です。誤解のないように申し添えますが、ここで述べているのは、1回目で解説しているとおり、子どもの外側からみた行動の観察です。子どもが...



一木康広
2024-07-24
4月から全塾生を観察してきて、 7月上旬(期末テスト終了)までに、 あらためて確認できた。 小学生であっても、 中学生であっても、 高校生であっても、 「なぜ勉強をするのか?」 こ...



中野雅夫
2024-07-24
先を見た子育て 小学校高学年以降伸びる子を育てたいものです 後伸びのポイントまとめると 無条件の愛情が伝わっている事(特に3歳までに伝わっている事が大事です) 出来る出来ないにこだわらない豊富なイン...


編集部が独自の視点で時事問題をピックアップ。さまざまなジャンルの専門家による「解説」「お役立ち情報」をお届けします。

枝川陽子
2023-06-30
夢はかなう!教育費支援制度が、大学進学をバックアップ!


清野充典
2022-03-25
逆子(さかご)の改善を希望して来院される方が、毎日のようにおられます。以前は、逆子の場合でも通常分娩を行っていましたが、 近年は38週の時点で帝王切開を推奨する産院が増えています。そのため手術を避けたいと思う妊婦さんが多くなった事が来院増加の背景にあると思います。逆子は、妊婦さんの不調を知らせるサインです。逆子と言われたら、 直ちに生活を改め、鍼灸治療で解消する事を推奨します。本記事では骨盤位(逆子)の改善を目的とする鍼灸治療について詳しくご紹介いたします。


安藤和行
2021-06-07
ここ数年、「大人の発達障害」という言葉がよく聞かれるようになり、注目されるようになりました。そんな中、まだあまり認知されていない、発達障害のある人は頑張り過ぎてしまう傾向があるという点について詳しくご紹介いたします。


高澤信也
2021-03-16
文科省はコロナ禍のさなか、児童生徒の心のケアや環境の改善に向けて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる支援の促進を各都道府県の教育委員会に求めてきました。 子どもの教育や心のケアの部分でも、これまでの取り組みを強化するしかないのでしょうか。心理カウンセラーの高澤信也さんに聞きました。


安藤和行
2021-01-20
発達障害のある人の誤学習(自分にとって都合の良い風に解釈した学び)はどのように修正(学びなおし)すればよいかについて安藤和行様に詳しくご説明いただいております。


須田泰司
2020-12-07
悪意あるあだ名は問題ですが、教育現場で禁止にすることは果たして現実的な方法なのか、あだ名文化はどうなっていくのか、スクールカウンセラーの須田泰司さんに聞きました。


岸井謙児
2020-10-06
子どもから「学校に行きたくない」と言われたとき、親はどのように対応すればいいのでしょうか。心理カウンセラーの岸井謙児さんに聞きました。


小田原漂情
2020-10-01
読書はどのような力を育むのでしょうか。また、子どもを「本好き」にする方法は。国語教育に重点を置く塾講師の小田原漂情さんに聞きました。


芝原佳子
2020-09-29
「子どもロコモ」になる要因とは。体力低下を改善する方法はあるのでしょうか。幼児から中高生まで、子どもの運動指導を行うトレーナーの芝原佳子さんに聞きました。


藤村高志
2020-09-05
子どものレジリエンスには、親の接し方や声かけが大きく影響するといいます。将来、挫折を経験したとしても、しなやかに乗り越えられるように、親が心がけたいことは。心理カウンセラーの藤村高志さんに聞きました。

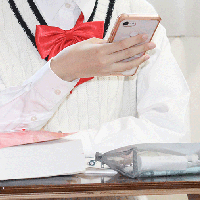
目代純平
2020-07-13
改めて親子で学びたい、スマホとの上手な付き合い方とは。小中学校でスマホの利用法などについて講演を行う、ITコンサルタントの目代純平さんに聞きました。


安藤和行
2020-07-07
本記事では、親は何故子どもに対して過干渉をし、それに対して子供はどう感じているのか。そして過干渉への対応方法について詳しく紹介いたします。


村田学
2020-05-27
社会全体の仕組みが変革の動きを見せているなか、進められるICT学習とは?「9月入学」の実現で可能になるグローバルスタンダードのメリットは?国際教育評論家の村田学さんに聞きました。


富田祥文
2020-05-15
勉強を「やらされる」のではなく「習慣」にするコツとは。親はどのように働きかけるといいのでしょうか。母と子の教育相談を行う富田祥文さんに聞きました。


茅根真由美
2020-05-01
自宅で働き続けるママにとって、子どもを保育園に預けられないことはストレスに。イライラをためずに、子どもと一緒に上手に在宅勤務を乗り切るコツは。特定社会保険労務士・産業カウンセラーの茅根真由美さんに聞きました。
