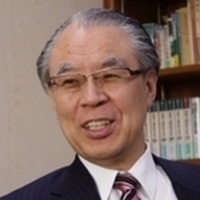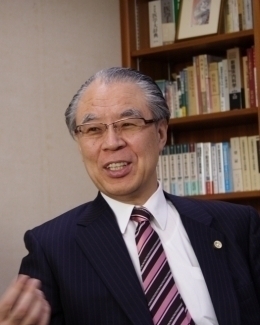地方自治 概算払と前金払の違い
1 登録免許税
土地を買受け所有権移転登記をしたとき、あるいは家屋を新築し保存登記をしたときに、登録免許税が課せられますが、この登録免許税は、登録免許税法によって、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続等が定められています(同法1条)。課税の範囲も、一定範囲の登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)に及んでいます(同法2条)。
2 納税義務の発生と納税額の確定
登録免許税の納税義務は登記等の時に成立し,納付すべき税額は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定する(国税通則法15条2項12号、3項5号)ことになっています。
3 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合
この場合は、納税義務者は、当然に還付請求権を取得します(国税通則法56条1項)。
4 還付請求権の時効期間
還付請求権の時効期間は5年間です(国税通則法74条)。
この間は、還付がされないときは,直接、国に対し、還付金請求訴訟を提起することができることになります。
5 登録免許税法で定められた簡易な方法の請求権
登録免許税法31条1項は、過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき等同項各号のいずれかに該当する事実があるときは、登記機関が職権で遅滞なく所轄税務署長に過誤納金の還付に関する通知をしなければならないことを規定しています。
これは,登録免許税の過誤納金の還付が円滑かつ簡便に行われるようにすることを目的としたものです。さらに31条2項は,登記等を受けた者が登記機関に申し出て上記の通知をすべき旨の請求をすることができることとして、登記等を受けた者が簡易迅速に過誤納金の還付を受けることができるようにしています。ただし、この通知をすべき旨の請求には1年の期間制限が定められています(31条2項)。
6 双方の権利を行使できる
登記等を受けた者が、過大に登録免許税を納付した場合、登録免許税法31条2項による登記官の所轄税務署長への通知を請求することも、国税通則法56条に基づき,直接、国に対し登録免許税の過誤納金の還付を請求することもできることになっています。
7 そうした中で、登録免許税法31条2項に基づく還付通知をすべき旨の請求をした者が、登記官から拒否通知されたとき、その取消を請求できるか?が問題になりました。
最高裁平成17.4.14判決は、それはできる、と判示しました。
すなわち、最高裁は、「登録免許税法31条2項は,登記等を受けた者に対し,簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することができる地位を保障しているものと解するのが相当である。そして,同項に基づく還付通知をすべき旨の請求に対してされた拒否通知は,登記機関が還付通知を行わず,還付手続を執らないことを明らかにするものであって,これにより,登記等を受けた者は,簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することができなくなる。そうすると,上記の拒否通知は,登記等を受けた者に対して上記の手続上の地位を否定する法的効果を有するものとして,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。」としたのです。
この判決は、改正行政事件訴訟法の施行後のものです。抗告訴訟の対象の拡大化の一例と言って良いでしょう。