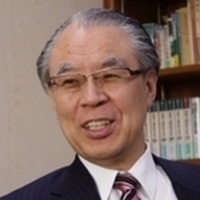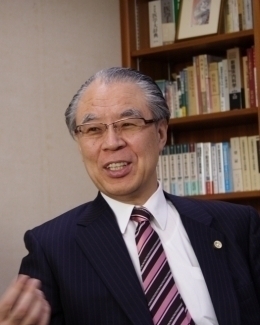労働 減給処分における減給額の制限
労働審判メモ
1 労働審判の特徴
① 迅速な手続と書面の作成など
労働審判法15条2項は、「労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において、審理を終結しなければならない。」と規定。
→ 労働者側も使用者側も、その事件の争点と証拠を第1回期日には明らかにしておかなければならない(15条1項)。そのため、争点を絞った書面の作成が重要。
②柔軟な解決
労働審判制度は、「紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ること」を目的としている(1条)ので、労働審判委員会からは、法律論でない解決案も提示されることが多い。
③拘束力が弱い
労働審判の結果(審判)に不服な場合は、2週間の不変期間内に裁判所に異議の申立てをすることができ(21条1項)、適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失う(21条3項)ことになっているので、拘束力が弱いものになる。
④しかし、解決率は高い
申立事件の7割が、労働審判委員会の調停で解決している。
⑤ 労働審判で扱える事件
これは、「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」すなわち「個別労働関係民事紛争」である(労働審判法1条)。例えば、解雇、雇止めの有効・無効に関する紛争、賃金とくに残業手当の支払義務に関する紛争、安全配慮義務に関する労災事故紛争、セクハラ、パワハラによる損害賠償請求事件等。
なお、採用内定後の紛争でも、採用の内定の法的性格が解約権留保付き就労始期付労働契約とされるとき(最判昭和54.7.20)は、労働審判になり得る。
派遣労働者と派遣先事業主との紛争でも、労働者派遣法44条から47条の2で労働基準法の適用がある事項についての紛争については、労働審判の対象になる。
⑤労働審判では扱えない事件
労働審判法24条1項は「労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。」と規定している。
例えば、就業規則の不利益変更や整理解雇の効力が争点になる事件、思想・性別等を理由とする賃金差別等が争点になる事件、不当労働行為を理由とする配転命令無効事件等は、3回以内の期日での解決は無理なので、労働審判を終了させることになると思われる。
2労働審判をする主体
これは労働審判委員会。
労働審判は、地方裁判所でするが、裁判所は、労働審判官1人及び労働審判員2人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う」ことになる(7条)。
なお、「労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する」(8条)ことになっており、労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命され(8条2項)、労働審判員2名のうち1名は労働者側から、具体的には、連合、全労連、全労協という全国労働組合組織の構成比率に応じて、労働組合の幹部、執行委員であるか、あった人が選任され、他1名は使用者側、具体的には、日本経団連が各都道府県の会議でとりまとめて最高裁に推薦した名簿の中から選任される企業の人事部長等人事経験者がなっている。
なお、労働審判員は、選出された母体にかかわらず、当事者の一方に偏らない「中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う」ことになる(8条1項)。この点は、都道府県労働委員会や中央労働委員会の委員とは違うところ。
労働審判手続は、労働審判官が指揮する(13条)が、労働審判委員会の決議は、過半数の意見によってなされる(12条)。
3 データ(少し古いが)
労働審判申立事件は、法24条で審判が終了する事件は3~4%、調停成立率70%超。残り20数%が審判になるが、審判になった事件のうち異議の申し出がなされる(この場合は訴訟に移行する)のが20%程度(申立事件数の5~6%)、したがって、80%(申立事件数の20数%)は審判が確定して解決している。
4.使用者側の弁護士が考えるところ
労働審判の申立をされたときは、労働審判委員会の提示する調停案を受け入れざるを得ない場合が多い(それが不服で調停の成立を拒否しても、労働審判がなされると、なんとなくそれに納得して異議を言わない可能性が大きくなる)という現実を意識して、取り組むことが必要になる。
また、労働審判事件は、審理期間は3回までという縛りがある(15条2項)ため、短期決戦型の事件であること、実際の運用面でも、解決までの期間は、平均して75日間程度である現状の下では、第1回の審判期日が極めて重要な意味をもってき、受任をしたその瞬間から、準備にとりかからなければならないという緊張の伴う事件になっている。
そのため、弁護士は、
⑴ 現場へ行く
労働審判の申立は、使用者からもできるが、労働者からがほとんどであるので、使用者代理人である弁護士は、申立書を見て、争点が何かを把握すれば、そこを中心に、使用者の主張をまとめ、証拠の準備をしなければならない。
その使用者の主張のまとめ方につき、問題があることが多いのは、事務所に来られる会社幹部のお偉方の言い分は、多分に、部下からの伝聞に基づく評価が多く、意外と事実関係を把握していない点があること。
そこで、弁護士は、お偉方の主張を聞く前に、現場に飛んで、申立人である労働者の同僚などから、申立人の仕事の詳細な内容、仕事ぶりや時間の使い方などを質問していき、弁護士自身が、申立人になったつもりで、申立人の体験した事実を体験してみる、ということから始める必要がある。むろん、会社にある賃金台帳等、あらかじめその存在が予測できる帳簿類の確認はむろんしなければならない。その上で、他の従業員から事情を訊いていくのであるが、労働者の同僚から、申立人に書かれた争点を中心に事情を訊いていくと、一波が万波を呼ぶように、お偉方も知らなかった新しい事実(使用者に有利な事実)が芋づる式に出てくることもある。
逆に、使用者に不利な事実しか出てこない場合もむろんある。その場合は、争いを避け、少しでも有利な調停になるような弁護活動へ舵を切るも大切だ。
労働事件は、依頼人の言い分のみを頼りに、主張や立証を組み立てるべきではない。時間と労力を厭わず、客観的事実を知る努力が必要になってくるのだ。
⑵ 争点を絞る ー 能力不足に絞った例
例えば、従業員から解雇無効を原因とする、従業員の地位にあることの確認を求める等の労働審判の申立や、訴訟の提起がなされたとする。会社代理人としては、解雇が有効であると考えるときは、それを裏付ける事実を答弁書に書くが、このとき、何を解雇の理由とするか?が1つの問題になる。
一例として、私が扱った訴訟の例を紹介する。
ア 会社が考えた解雇理由
会社は、従業員Aを解雇した理由を、①協調性の無さと②能力不足を挙げたのであるが、私の方では、Aの同僚B、C、D、EやAと一緒に仕事をした発注者会社の従業員F、Gから、Aの仕事ぶりを聴き出した結果、解雇の理由を、能力不足1本に絞ったのである。
理由は、Aには、同僚や発注者側の会社従業員の求める仕事が、能力的にできていないこと、その能力不足は顕著で、Aには将来ともそれができるレベルに達することはない、と思ったからである。会社の社長は、Aが他の従業員などと協調できないことも、解雇の理由だとして、解雇理由を能力不足1本にすることに抵抗があったのだが、私は、社長に、
ア たしかに、Aは他の従業員と協調して仕事をすることができていないが、それは、協調性の欠如が原因ではなく、能力がないため仕事ができないことが原因ではないか?
イ もし、Aに他の従業員同様の能力があれば、仕事に対する姿勢も、他の従業員との共同作業が必要な場合における連携も、今とは、大きく、違っているとは思わないか?
ウ 仕事の中味が理解できないAに、仕事の中味の理解ができていることを前提として、他の従業員との連携や連絡や、会社のいうところの協調性が期待できるのか?
と質問した後、
エ もし、解雇理由を、①能力不足と、②協調性の無さの2つすると、焦点がぼやける(そもそも協調性の無さという多分に性格的な欠点が解雇理由になるのか疑問である)上に、能力不足の立証は、実際にAのした仕事ぶりを明らかにするだけで、比較的容易にできる(仕事ができないことを具体的に立証できれば、従業員Aには、雇用契約における債務の本旨に従って履行はできないことが理解される)が、協調性の無さという性格的な欠陥(しかも、その欠陥が債務の本旨に従った履行ができないほどの欠陥)を立証することは至難の技だと思えるので、もし、会社が、Aに対する解雇理由を、能力不足と協調性の無さの2つとした場合、そのうち1つは立証できていないので、結局のところ解雇理由は立証できていない、という判断に傾きやすくなるのではないか?
と、私の疑念を言ってみたところ、社長も、なるほど、と理解してくれ、解雇理由を、Aの能力不足1本に絞ったのである。
この事件は、金銭による和解で解決したが、Aは、和解の席で、解雇は無効なので会社に復帰したいと執拗に言い続け、これに対し、裁判所は、Aに対し、断固とした姿勢で、それは無理だ、裁判所はAが職場復帰することを内容とする和解はできない、と言い、金銭による和解に至ったので。私の争点を絞った争い方は、成功したのではないかと思っている。
なお、証明の仕方にについて一言する。
能力不足の主張に、評価は不要、事実で勝負
言うまでもなく、「能力不足」という言葉は、評価概念である。これは、つまりは、Aという労働者の仕事を見て、会社が求める仕事ができないという評価を、会社がしたというにすぎない。しかし、訴訟や労働審判で重要なことは、評価は、当事者やその代理人である弁護士がすべきことではなく、裁判所や労働審判委員会に、してもらわなければならない。
であるから、当事者や弁護士がすべきことは、裁判所や労働審判委員に、Aの能力不足と評価判断してもらえるだけの、事実の主張と立証なのである。
言葉を換えて言えば、「能力不足」という評価は最後の付け足しにして、その中味を主張立証しなければならないのである。
(3)審判期日には、事実関係を説明できる者、調停を成立させる権限のある者を同行すること
労働審判事件では、冒頭から、審判官や審判委員が、当事者や参考人に、質問を発し、直接事実関係を聞きだし、また、解決案を提示するからである。