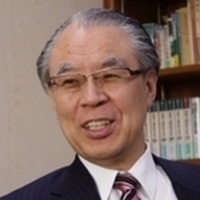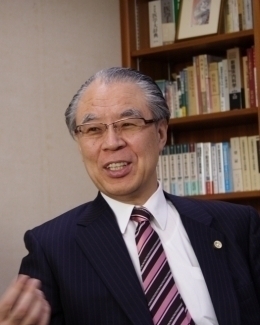景品表示法違反② 課徴金制度の導入と初適用事例
デジプラ消費者保護法の制定
令和3年(2021年)5月10日に取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(通称DPF保護法またはデジプラ消費者保護法)が成立公布されました。
以下に、その概説をいたします。
もっとも、以下の文章は、定年まで広島大学で会社法、金融法、独禁法などを研究してきた当事務所の弁護士(広島大学名誉教授)後藤紀一の文章です。。
ただし、ア、イ、ウ、それにエの見出しの部分のみは菊池がつけ加えました。
ア ネット通販全盛時代の到来
1 新立法の制定
(1)新立法の経緯
アマゾンとか楽天に代表されるように、ネットを利用した商品の販売、サービスの提供に関する通信販売等の取引が国の経済活動に大きなウエイトを占めるようになった。ことに昨今のコロナ禍の影響もあって、一般国民もネット購入が当たり前のような時代になってきた。それに伴い、このような取引に固有のリスクも明らかになった。
イ リスクの例
例えば、大手のネット販売市場(イチバ)に出品した海外の業者から購入した携帯電話のバッテリーから出火し、自宅が火災の被害を受けた個人購入者(消費者)が、海外販売事業者に損害賠償請求しようとしたが、当該ネット事業者(デジタルプラットフォーム提供者)が適切に対応できなかったことから、結局泣き寝入りになったケースとか、まがい物商品等をネット購入した消費者が返品とか損害賠償との請求をしようとしたところ、販売者の所在が特定できない等のため、これができなかった等のケースが発生した。
このような事情を背景に、今般新しい消費者保護に関する立法がなされた。
ウ デジプラ消費者保護法の制定理由
(2)取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の制定
上記の理由から、令和3年(2021年)5月10日に「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」という名称の新法が成立公布された。同法の立法趣旨の概略は、「取引デジタルプラットフォームが国民の消費生活にとって重要な基盤となっていることに鑑み、取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護することを目的とする」ということであるが(本法1条)、公布の日から1年以内に施行されるので、間もなくである。所轄官庁は、内閣総理大臣より委任された消費者庁である。
エ 略称
「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」という名称は、あまりに長いことから、消費者庁は、「DPF保護法」と略称している。
経団連は「デジプラ法」と略称している(週刊 経団連タイムスNo.3508「取引デジタルプラットフォーム消費者利益保護法と特商法等改正法のポイント」)。
本稿では、以後DPF保護法と表記するが、DPFという横文字を使うと一般国民にはピンとこない。より内容に則して言うと、個人的意見であるが、「デジプラ消費者保護法」といえば、大体理解できるのではないか。
2 本法の基本概念
本法の基本概念は以下のとおりである。
(1)取引デジタルプラットフォーム
「取引デジタルプラットフォーム(以下、DPFという)」とは、①ネットで表示された手続きに従って、消費者(個人)が販売業者等に対し、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの意思表示を行うことができる機能(インターネットモール)、②同様の手続きによって「競り」に参加できる機能(インターネットオークション)を有する「場(バ)」をいう(本法2条1項)。
(2)「取引デジタルプラットフォーム提供者」
取引デジタルプラットフォーム提供者とは(以下、DPF提供者という)、事業として、取引デジタルプラットフォームを提供する者をいう。(本法2条2項)。
(3)消費者
本法の保護対象になる消費者」とは、個人(商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。)をいう。一般の消費者保護法の概念と同様である(本法2条3項)。
(4)販売業者等
「販売業者等」とは、販売業者又は役務の提供を営む事業者をいう(本法2条4項)。一般には出店者という。
3 DPF保護法におけるDPF提供者の義務等
(1)DPF提供者の(努力)義務
本法3条1項によると、DPF提供者に対して、下記の3つの「措置」を執ることが努力義務となっている。具体的措置については、政令で指針が示されるが、なぜ強制力を伴う「法的義務」としなかったのかについては、本法の立案過程で複数の論点が検討課題となったこと、この「措置」の内容があまりにレベルの高いものになると、その要求に応えられるのは大規模取引DPF提供者のみということになり、DPF事業の参入障壁となってしまうのではないかという点にある。
しかし、努力義務といっても、DPF提供者は、講じた措置の概要及び実施の状況等を開示しなければならないので(本法3条2項)、いい加減なものだと消費者に信用されなくなることら、単なる「努力」義務というものではない。
本法は、施行状況及び経済社会情勢の変化を勘案し、施行後3年を目途に見直しが予定されているので(附則3条)、この問題については、いずれ改正される可能性がある。
(2)「措置」の内容
①販売業者と消費者との間の円滑な連絡を可能とする措置
②販売条件等の表示に関し苦情の申出を受けた場合における必要な調査等の実施
③販売業者に対し必要に応じ身元確認のための情報提供を求める。
4 危険商品等の出品の場合における利用停止要請
内閣総理大臣(消費者庁)は、いわゆる危険商品等(商品の安全性の判断に資する重要事項につき、著しい虚偽・誤認表示がある商品等)であって、所在不明等によって当該表示が是正されることを期待することができない場合には、DPF提供者に対し、当該販売事業者等のDPF利用の停止等を要請することができる(本法4条1項)。
DPF提供者がこの要請に応じて利用停止をしたことにより販売業者に損害が発生しても、DPF提供者は責任を負わないと明記したため(4条3項)、DPF提供者は安心して利用停止措置をできることになった。利用停止に関する規定は、前記のスマホバッテリー発火事件による消費者被害の回復が困難であったことも踏まえて導入された。
そして、内閣総理大臣(消費者庁)がこの利用停止要請をしたときは、その旨を公表することができるが(同条2項)、公表されると、販売事業者等は、社会的信用が失われるので、その抑止効果は大きい。
5 販売業者に係る情報の開示請求権
消費者が購入商品等の欠陥について損害賠償請求等を行う場合は、当該販売業者等の氏名又は名称、住所その他の当該債権の行使に必要な販売業者等に関する情報を知る必要がある。そこで本法は、消費者がDPF提供者に対し、必要に応じてその保有する当該販売業者等につき、情報の開示を請求することができるとした(本法5条1項)。
この権利は、消費者の法定の権利であるから、消費者が開示請求してもPDF提供者がこれに応じなかった場合は、裁判所に提訴することができる。
6 内閣総理大臣(消費者庁)に対する申出制度
本法は、「何人も、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣(消費者庁)に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。内閣総理大臣(消費者庁)は、この申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。」旨規定する(本法10条1項2項)。
申し出ることができる者は、被害を受けた消費者に限らないことから、消費者団体等もこの申出制度を利用できることになった。法的知識のない一般消費者が救済措置をとることが困難な場合は、消費者保護団体等が代行することができる。
7 官民協議会の創設
国の行政機関、DPF提供者の業者団体、消費者団体等により構成される「官民協議会」が創設された(本法6条~9条)。本協議会では、悪徳販売事業者等による消費者被害の解決方法の他、消費者被害のおそれがあるとして申し立てられた場合における適切な「措置」等について協議されるであろうが、それだけではなく、DPF提供者の努力義務としての措置に係る指針のバージョンアップ等についても協議対象になるとされる。
本協議会の構成員には守秘義務が課され、これに違反した場合は、罰則がある(以上、衆議院ホームページ「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案」;消費者庁「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案概要」;消費者庁消費者政策課説明資料「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」;染谷隆明=川崎由里「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案の解説」等参照)。
以上は、DPF保護法に関する概要であるが、DPF取引を巡って、以下のような別個の法律問題がある。
8 PDF提供者(事業者)と独禁法
独禁法は、元々は事業者間の自由かつ公正な競争の確保を目的に制定されたものであるが、DPF保護法の関係においても個人情報等を提供する消費者との取引において,独禁法の優越的地位の濫用が問題なることが指摘されている。個人情報保護法の対象になる個人情報は、生存する個人を特定できる個人情報を対象にしているが、ここでは、これから漏れた「個人に関する情報」も対象になるので、よりきめ細かい保護を検討できる。
DPF事業者が個人情報等を提供する消費者に対して優越的地位にあるとは,消費者がDPF提供者から不利益な取扱いを受けても,消費者が当該DPF提供者の提供するサービスを利用するためにはこれを受け入れざるを得ないような場合には、独禁法の優越的地位の濫用が問題になる。どのような行為がこれに該当するか、公取委で検討されている(公正取引委員会「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」参照)。
9 デジタルプラットフォーム透明化法
DPF保護法と似て非なるものに、「デジタルプラットフォーム透明化法(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律)」が令和2年5月に制定され、すでに施行されている。
この法律は、一部の(巨大)PDF事業者が規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、販売事業者等との間の取引において、透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指摘されていたことに対処するために、立法された経緯がある。すでにEUで立法されていることに倣ってわが国でも導入された(BtoBの取引が対象)。この法律は、PDF保護法と異なり、経産省が所轄官庁で同省が指定するごく一部の大規模PDF事業者(アマゾン、楽天市場(イチバ)、ヤフーショッピング等)を「特定デジタルプラットフォーム提供者(以下、特定DPF提供者)という」として規制対象にしている。
本法の規制は、大きく分けると、①開示規制、②措置規制、③監督規制からなっている。
「開示規制」は、特定DPF提供者は、商品等提供利用者(出店者)に対して、取引を拒絶する場合や取引条件の変更をする場合、利用すべき有償サービス等がある場合は、その内容等について開示をしなければならないというものである。
「 措置規制」は、特定DPF提供者は、商品等提供利用者との相互理解のために、紛争解決のための手続き等を設ける措置を講じなければならないというものである。これらの措置がなされない場合は、経済産業大臣が是正勧告等を行うことができる。
「監督規制」は、年度ごとに特定DPF提供者が経済産業大臣あてに報告し、経済産業大臣は、必要に応じて検査を行うことができるというものである。
なお、特定DPF提供者の透明性および公正性を阻害する行為があり、それが独占禁止法に違反すると認めるときは、経済産業大臣は、公正取引委員会に適切な措置(公正取引委員会への措置請求)を求めることができる(詳しくは、松澤登「デジタルプラットフォーム透明化法案の解説-EU規制と比較しながら(日生基礎研究所 )」を参照されたい)。
以上