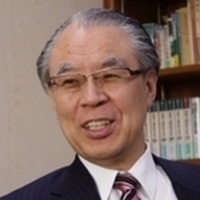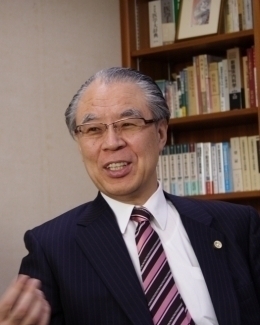ロータリー9 ロータリーでは、心緒乱れる経験は貴重
ロータリーは、むろん、明確な理念や目的を持って、始まっています(コラム32参照)。ロータリーの黎明期には、当然ながら、試行錯誤の時期はあったでしょうが、やがてロータリーの活動を学問として体系化したのは、ガイ・ガンディカー(Guy Gundaker)です。そして、その教科書というべきものは、1916年に著した『A·Talking Knowledge of Rotary』(小堀憲助訳『ロータリー通解』)です。
ガイ・ガンディカーは、1902年に弁護士になり、その後レストラン経営に転じ、全米商工会議所のレストラン業者代表として長い間活躍し、その間に、レストラン経営学ともいうべき理論を打ち立てています。そして、その経験と学びでもって、ロータリー学ともいうべきものを作り上げたのです。かれは、その理論的功績のゆえに1923-24年度の国際ロータリー(RI)の会長になっています。
このようにロータリー運動も、試行錯誤の時期を経ると、理論的体系的な仕組みを作り上げているのです。これを学問と言わずして何の学問ありや、と思います。
ここで、フランチャイズシステム(FC)学を、構築した人の例を挙げてみたいと思います。雑誌「プレジデント」(2021年9月3日号)の「人間邂逅 日本初のフランチャイズ講座」という見出しの記事には、日本フランチャイズチェーン協会会長をされた山本善政さんが、FCビジネスは26兆円産業といわれ、日本社会のインフラを形成しているにもかかわらず、FCを教える講座がどこの大学にもないことに気づき愕然となり、急遽ご自分が卒業した大学に申し入れて、日本初のFC講座を開講してもらい、以後、その講座からフランチャイズビジネス論が生まれるに至ったことなどが書かれています。
ここからも明らかなとおり、学問は、人知の発達そのものなのです。文明を進化させてくれる原動力なのです。ですから、「明日どのような学問が生まれるか?」「既成の学問がどう進化するか?」は誰も予想すらできません。学問は学問それ自体にその必要性を考えてもらえばよく、政治や行政は、いっさい容(よう)喙(かい)してはならないのです。特定の学問を捉えて、それについてはそれ以上の必要はないなどという政治や思想があってはならないのです。政治や行政がすべきことは、学問の自由を認め、学問の多様性を認めることなのです。