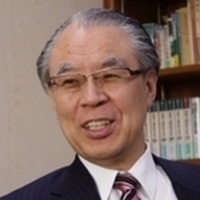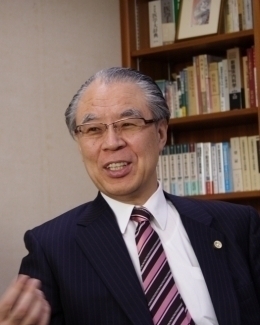1. セクハラと降格処分と減給について
1.日本の企業の成長力の失墜と言葉の伝達力
「我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるため・・・」という一文は、2014年(平成26年)1月20日に施行された「産業競争力強化法」第1条の目的規定に書かれた言葉である。
企業の成長力を量る各種の経済指標を見ても明らかだが、日本経済の長期的低迷は顕著である。
その原因は何か。
次のような新聞記事を見ると、言葉の伝達力の弱さも、その一つに挙げうるのではなかろうか?
すなわち、その新聞記事とは、2023年2月10日付け日経新聞記事加藤勇志郎氏(キャディCEO)の語る「 私見卓見 ものづくりの『暗黙知』打破 」である。
加藤氏は、
➀日本の技術は言語化できる部分を言語化していないこと、
②それによる暗黙知は、かつては競争力の源泉となっていたが、
③現在では外国企業との競争上不利になってきていること、
④少なくとも汎用的な金属加工品の素材では、指定がない限り日本製は使われてはいない状況であること、
という現状を紹介された上で、
⑤日本のものづくりを再び活力を取り戻せるようにするには、暗黙知を形式知に変えていくことが必要だ。
⑥そのためには図面は企業間を超えた標準を作ることが大切になってきた。
との趣旨のことを書かれているのである。
ここから理解できることは、日本の企業は、暗黙知を形式知に変えていくことが必要だ、ということである。
ところで、形式知と暗黙知という言葉は、大辞泉の書くところでは、ハンガリーの哲学者マイケル・ポランニーのつくった言葉であり、
「形式知」とは「客観的で言語化できる知識」のこと、
「暗黙知」とは「主観的で言語化することができない知識、たとえ言語化しても肝要なことを伝えようがない知識」とのことである。
ここから思うに、加藤氏の言は、日本の企業は、形式知にできる知識を、暗黙知のままにしている、というのであろう。
そうであれば、日本の企業は、もっともっと言葉による意思の伝達力を高める必要があるであろう。
2.契約文を“書く能力”を磨くこと
“書く能力”があるのに“書かない”
これは今、日本人に、顕著に見られる現象ではないだろうか。
日本人は、契約文章を書くことが実に下手である。
その原因は、120年間にわたる民法(債権法)の瑕疵論の下で“書かなくとも、裁判所が契約の内容は解釈してくれている”という考えに慣らされてきたからではないかと思う。
それに加えて、日本の文化の中にある「行間を読む」「忖度する」などの能力、要は文字にされていないところに意味を見いだす能力を良しとする文化があることも原因しているものと思われる。
現在は、世界を一つの市場にした中で、企業同士が、経済競争をしている時代である。その世界では、日本の法律がそのまま適用されることはない。
日本の企業は、契約書をしっかり書かないと、権利は認められず、逆に思わぬ債務を抱え込むことにならざるをえない。
日本の企業が、日本の企業を相手に取引をする場合でも、その約束事は契約書に書かないと認められない時代に入っているのである。
すなわち、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法(債権法)は、「瑕疵論」を捨てて「契約不適合論」を採用したからである。
もはや契約内容は裁判所が解釈してくれる時代ではなくなったのである。
要は、契約書の不備は致命的な欠陥になることになった。
それだけに、契約書を書く能力は、企業法務担当者には必須のものになったのである。