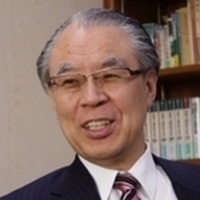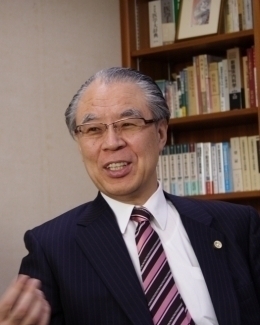科学と基準
1 横浜地判平18.9.15は、医者からアルツハイマー型老年痴呆と診断された85才の女性が平成11.11.11に作成した公正証書遺言について、遺言者には遺言書作成当時意思能力がなかったとして無効とされた事案です。
2 遺言者の精神状態(判決が認定したもの)
平成11年11月の時点で,花子は中等度から高度に相当するアルツハイマー型の認知症にり患しており,そのため恒常的な記憶障害,見当識障害等があり,しかも,記憶障害については,それまでに短期的な記憶障害だけでなく,子の数や病歴などの長期的な記憶についての障害も発生しており,また,会話についても,話しかければ応答はあるが簡単な会話のみに応答する程度であったこと,平成11年6月15日実施の花子の知的機能検査では,見当識及び記銘力のいずれの項目についても成績が芳しくなく,ミニ・メンタル・ステート法(MMS法)が30点中15点,改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS―R)が30点中9点であって,横浜市総合保健医療センターの医師によって高度の痴呆が認められるとの診断がされていたこと,
3 同遺言の内容
本件遺言の内容は,多数の不動産やその他の財産について複数の者に相続させ,しかもその一部の財産は共同して相続させ,遺言執行者の指定についても項目ごとに2名を分けて指定し,1人についての報酬は細かく料率を分けるなどという比較的複雑なものであったこと,
4 同遺言書作成当時の様子
谷川公証人は,東洋信託銀行において作成された本件遺言の原案を条項ごとに読み上げて花子にその確認をしたが,花子の答えは「はい」,「そのとおりで結構です。」などの簡単な肯定の返事をするにとどまったというものであったこと
5 裁判所の判断
中等度から高度の認知症に陥っていた花子において,その遺言内容を理解し,判断した上での返事であったか疑問があるといわざるを得ず,本件遺言作成時点において,花子が本件遺言の内容を理解し,判断することができていたとはいまだ認め難い。
6 裁判所が考慮した内容
もっとも,証人である谷川公証人及び林は,いずれも,花子に遺言能力がないとは思われず,本件遺言の内容については花子の意思に基づくものであった旨の証言をする。
しかし,前記のとおり,林らが花子に尋ねて作成したという本件遺言の内容について見るに,被告一美に対する不動産の相続内容については,東洋信託銀行が以前にかかわって作成されており,林も確認していた花子を遺言者とする平成8年遺言(甲15)と同一であって,被告一美の自宅の敷地及びその隣地を同被告に相続させるというもの,また,原告二郎に対する不動産の相続内容については,太郎の遺産分割協議の結果,原告二郎が各2分の1の持分を取得していた建物を同原告に相続させるというもの,そして,その外のほとんどの不動産を被告一郎に相続させるというものであるところ,これらは,林らが,花子から聞いていた長男である被告一郎に各不動産を相続させたいということを基本とし,ただし,平成8年遺言の内容,遺産に被告一美の自宅の敷地となっている土地があること,及び太郎の遺産分割によって原告二郎が花子の自宅建物の2分の1を相続していることなどを考慮し,花子に対し,その不動産ごとの特色を説明した結果,各不動産について相続人としてふさわしい者を少なくとも示唆する結果となってしまったことにより,中等度から高度の認知症に陥っており意思能力が十分ではなかった花子が,これをそのまま受入れる旨の応答をしたにすぎないものと考える余地があり,当時の花子の認知症の症状に照らし,本件遺言の内容が花子の意思に基づくものであったと認めるにいまだ十分とはいい難い。
また,谷川公証人は,本件遺言作成当日,花子宅に赴き,花子の生年月日を確認してその答えを得ているが,遺言内容の確認については,東洋信託銀行において作成された本件遺言の原案を条項ごとに順次読み上げ,遺産である個別不動産ごとに,原案に記載されている者に相続させることでよいかを尋ね,それについて花子から「はい」,「そのとおりで結構です。」などの簡単な肯定の返事を順次もらったというものであるところ,前記のとおり,当時,認知症に陥っていた花子も,話しかければ応答し,簡単な会話をする程度は可能であったが,複雑な会話の内容を理解することができなかったものであって,谷川公証人の証言によっても,本件遺言作成時において,花子に本件遺言の内容を理解して判断する遺言能力があったと認めるにいまだ十分とはいえない。
さらに,乙第1号証(脳神経外科医である金彪医師の鑑定意見書)において,同医師は,花子の平成9年の入院時に見られる痴呆状態,徘徊あるいは感情不安定,易興奮性などは,環境の変化に伴って見られる短期的な失見当識の症候に典型的なものであり,平成11年11月時点においても,花子につき,長期記憶に依拠するところの永らく所有してきた土地建物に関する遺産分配に関して,自らの意志で決断する能力がなかったと断定することは不可能であると考えるとする。しかし,前記1の事実によれば,花子には,入院時だけではなく,平成9年以降平成11年11月時点の後まで,日常生活も含めて継続的に記憶障害,失見当識等が認められたもので,しかも,記憶障害については,子の数,過去の病識などの記憶障害もあり必ずしも短期の記憶障害に限られるものではなかったものであって,その他,当時継続的に花子の診療に当たっていた古川病院の古川医師等が当時既に花子の認知症の症状が重篤なものである旨の診断をしていたことなどの上記1の事実を併せ考慮すると,平成11年11月時点においても,花子には遺言能力があったものと認めるに十分とはいえない。
5 以上によれば,本件遺言作成当時において花子には本件遺言の内容を理解し,判断する遺言能力があったとは認められないから,本件遺言については無効であるといわざるを得ず,原告らの請求は理由があることになる。