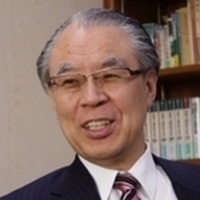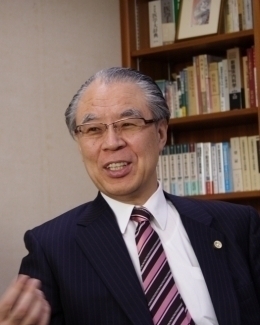科学と基準
1 遺留分を定める遺言事項は認められていない
被相続人が生前遺言によって定められることは、法律上根拠規定が置かれています。
次の①から⑮までですが、⑯は裁判上認められています。
① 推定相続人の廃除・取消(892~894)
② 相続分の指定・指定の委託(902)
③ 特別受益の持ち戻しの免除(903③)
④ 遺産分割の方法の指定・指定の委託(908前段)
⑤ 遺産分割の禁止(908後段)
⑥ 共同相続人の担保責任の減免・加重(914.911)
⑦ 遺贈の減殺の順序・割合の指定(1034但書)
⑧ 遺贈(964)
⑨ 一般財団法人設立のための寄付行為
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律164)
⑩ 信託の設定(信託法3)
⑪ 認知(781)
⑫ 未年者の後見人指定(839①)
⑬ 未成年後見監督人の指定(848)
⑭ 遺言執行者の指定・指定の委託(1006①)
⑮ 祖先の祭祀主宰者の指定(897① 但書)
⑯ 生命保険金受取人の指定・変更(東京高裁平成10年3月25日判決)
2 寄与分は遺言事項にはない
遺言で寄与分を定めことは法律上予定されていません。
しかし、これを無効とするのは、遺言者の意思に反します。
そこで、寄与分を定める遺言は、遺言者が、相続財産の中から、寄与相続人に対し、遺言者が考える寄与分を遺贈し、その遺贈財産は持戻しを免除する意思があると表明したものと考えられることになります。
3 寄与分の遺言文例と遺贈の遺言文例の比較
寄与分:
遺言者は、長男がよく遺言者の家業を助けかつ遺言者の療養看護に尽くしてくれたので、長男の寄与分を全遺産の20%と定める。
遺贈:
遺言者は、長男がよく遺言者の家業を助けかつ遺言者の療養看護に尽くしてくれたので、全遺産の20%を遺贈する。この遺贈分については持戻しを免除する。
4 寄与分の定めを無効とするのは不合理
前項の寄与分と遺贈とは、趣旨は同じです。遺言者は、法律家でないので、3項の寄与分を定める遺言は法律上の根拠がないので無効になり、遺贈は法律上根拠があるので有効になる、とは考えないでしょう。
5 遺言は意思解釈の問題
遺言を書くのは法律家ばかりではありません。正確な法律用語を用いて遺言書を書くことを期待すべきではないのです。そこで、遺言の解釈がなされるのですが、本件もそうなのです。