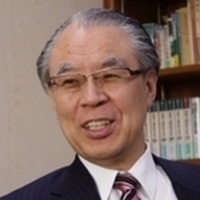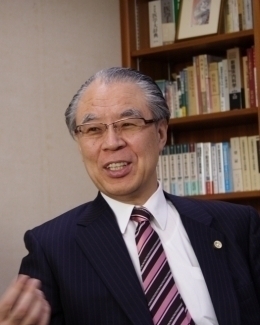科学と基準

1 相続人の配偶者や子が寄与した場合にも寄与分は認められるか?
⑴ 相続人が亡くなっておれば、相続人の配偶者や子には、独自の寄与分というものは認められません。秋田大曲支審昭37.6.13は、長男の死後に,その妻(相続人ではない)が義父の遺産の「維持管理に多大の寄与をしたことは…認められる」が、妻には法律上寄与分は認められないと判示しました(秋田家大曲支審昭37.6.13)。
⑵ 相続人が存命であれば、相続人が配偶者や子の寄与を自分の寄与として寄与分を主張できます。東京家審平12.3.8は、脳梗塞の後遺症が残る被相続人を、被相続人の妻とともに介助した相続人の妻子の行為を、相続人の寄与と認定しました。その理由付けは、相続人の妻は相続人の履行補助者だというものです。
⑶ 相続人は亡くなっているが代襲相続人がいる場合、相続人の妻の寄与を代襲相続人の寄与分と認めた裁判例があります(東京高決昭54.2.6)。
2対価を得ていた場合は、寄与分は認められないのか?
対価を受けていても少額の場合は、「支払われた賃金や報酬等が提供した労務の対価として到底十分でないときは、報いられていない残余の部分については寄与分と認められる、と考えられます(大阪高決平2.9.19)。
3 特別受益者にも寄与分は認められるか?
前記最高資料は「寄与した相続人に対して既に生前贈与又は遺贈がなされている場合において、当該生前贈与等が、明示的であるかどうかを問わず、寄与に対する実質的な対価としてなされたものであることが認められるときは、寄与分は認められないということになろう。」この場合は、「寄与の対価と認められる限度において、生前贈与等を持戻しの対象としない取扱をすることになるものと考えられる。」
と寄与分に関する解釈運用指針を示しています。
東京高決平8.8.26も、夫である被相続人が生前妻へ土地を贈与していたことに関して、「妻として長年にわたる貢献をしてきた事実は認められるが、上記の贈与によって妻が得た利益を超える寄与があった事実は認めることができない。」として、寄与分を否定しました。ただ、この審判は、妻が受けた贈与については「暗黙のうちに持ち戻し免除の意思表示をしたものと解するのが相当である」として、寄与分を認めない代わりに贈与の持戻しを免除しています。
これは、実質的には、贈与財産を寄与分に対する対価と評価したとも言えるでしょう。
4 相続開始後の寄与にも寄与分は認められるか?
⑴ 原則
寄与があったかどうかの判断の基準時は、相続開始時です。相続開始後の貢献は、寄与分として評価されません。
⑵ 例外を認めた裁判例
東京高決昭54.3.29は、相続人が、相続開始後、大学を中退して被相続人たる父の家業を継ぎ、一家の生計を支えて弟妹を学校へ行かせ、遺産である建物を改修・増築をし、遺産である借地の賃料を支弁し、公租公課等を負担してきた貢献度を金銭に見積り、予め遺産から控除するのが相当であると判示し、事実上、相続開始後の寄与分を認めています。
5寄与分の認定はだれがするのか?
全相続人の合意でするか、家庭裁判所の審判で決めてもらいます。
6 遺留分の減殺請求の際に、寄与分の請求もできるか?
寄与分を定める審判は、遺産分割の審判の申立がないと、申立はできません。ですから、遺留分減殺請求訴訟の中で、寄与分の主張は認められません(最判平8.1.26)。