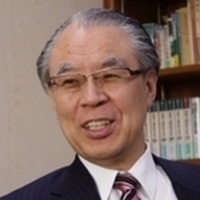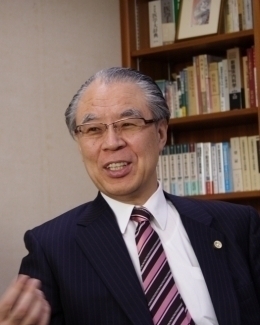科学と基準
1 認知とは?
法律上の夫婦の間に生まれた子は「嫡出子」と呼ばれます。
そうでない男女の間に生まれた子は「非嫡出子」と呼ばれます。
嫡出子は、当然に父の子ですが、非嫡出子は「認知」されないと、父の子にはなりません。つまり、認知とは、父が非嫡出子との間に親子の関係を築く意思表示のことなのです。
認知は、父が自らの意思表示でする「任意認知」と、子が訴訟を起こして裁判所に父の子と認めてもらう「強制認知」があります。
父がする任意認知には生きている間にする「生前認知」と遺言でする「遺言認知」があります。
裁判で認知してもらう強制認知は、父が生きている間にする「生前認知」と父の死後訴訟を起こして認知してもらう「死後認知」があります。
2 認知された子の相続分
民法900条は、但し書きで、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の1/2と・・・とする。」と定めていますので、同じ子でありながら、嫡出子と非嫡出子の間に倍・半分の差が設けられています。
これについては、憲法14条の法の下の平等に反するのではないかという議論があること、最高裁は平成7年7月5日大法廷で、婚姻関係の保護のためにこの差別は許されるという判示したこと、しかしこの裁判では15人の裁判官のうち5人の裁判官が反対したこと、その後も最高裁は3回小法廷で、この差別的扱いは合憲であるとの判断をしているが、そのいずれの事案でも5人の裁判官のうち2人の裁判官が反対していること、は、本連載コラム「相続4」で解説したとおりです。
3 死後認知を受けたとき、遺産分割がまだなされていないとき
死後認知を受けたときとは、被相続人である父が亡くなった後に認知されたとき、という意味ですので、その時点では、すでに遺産分割が終了している場合も、まだ遺産分割がなされていない場合もあります。後者の場合は、非嫡出子として遺産分割に当然関与できます。
4 死後認知を受けたとき、すでに遺産分割が終わっている場合
民法910条は「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」と定めていますので、遺産分割のやり直しを求めることはできません。
認知された子の相続分に相当する「価額」を請求できるだけになります。
5 価額の基準日
認知された非嫡出子が価額を請求する場合の価額とは、いつの時点の価額か?
⑴ 価額請求時の時価を基準にすべきとの見解(東京高裁昭和61.9.9審判)
⑵ 訴訟の事実審口頭弁論終結時(訴訟の中で主張・立証などの訴訟行為をしうる最終段階)とする見解(福岡高裁昭和54.12.3判決)
⑶ 家裁の審判の時とする見解(大阪高裁昭和45.3.29決定)
などがあります。
6 債務は控除すべきか?
相続人として、妻、長男、長女(いずれも嫡出子)だけだと考え、遺産分割をしてしまった後に、死後認知をされた非嫡出子が「価額」の支払請求をしたときを考えてみます。
相続財産は、資産が1億円、負債が3000万円の場合を前提にします。
遺産分割では、法定相続分のとおりに、妻が5000万円相当の遺産を取得し、長男と長女は各2500万円相当の遺産を取得したとします。
その後で、認知された非嫡出子が登場してきたのです。非嫡出子の相続分は、遺産の1/10(子が全体で1/2。長男、長女の嫡出子は各1/5、非嫡出子はその半分の1/10)ですから、資産の1/10である1000万円の価額の支払いを請求できるのか?、債務を控除した純資産7000万円の1/10である700万円を「価額」として請求できるのか?という問題です。
福岡高裁昭和54.12.3判決は、負債は控除すべきではないと判示しました。
負債を控除しなくとも、非嫡出子は、負債も法定相続分の割合で相続し、債権者へ支払う義務があるのですから、ここで、債務を控除する必要はなく、仮に、この時点で相続人のうちの誰かが負債を全額すでに弁済しておれば、そのうちの非嫡出子の負担分については清算を求めることができるので、負債を控除する必要はないのです。
7 価額請求権は5年で消滅時効にかかる
遺産分割請求権は消滅時効にかかりません(「相続89」で解説)が、遺産分割が終了した後でする、死後認知を受けた非嫡出子がする価額請求は、消滅時効の対象になります。
その期間は、認知されたときから5年間です。
民法884条前段で「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」との規定があることから、これに準じて5年間とされているのです。