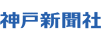英検1級取得者によるオンライン個別指導のプロ
英語パーソナルジム HIET(ヒート)/ High Intensity English Training
- お電話での
お問い合わせ - 090-3825-5237
コラム
英文記事を読む:外国語を司る脳部位特定《東大/マサチューセッツ工科大》
2024年1月21日
本記事は独学・国内学習による
英検1級保持者が書きました。
東京大学大学院総合文化研究科の酒井邦嘉教授と梅島奎立助教は、マサチューセッツ工科大学言語哲学科のスザンヌ・フリン教授との共同研究において、新たな言語に触れた時に「誰が、何時、何を」習得したかを司る脳部位を初めて特定しました。
論文の Abstract (要約)を紹介します。
この論文で私が注目するのは
言語獲得の累積増進モデル
という外国語習得における脳科学的知見です。
先ず前提知識として概要を紹介します。
話がやや堅苦しくなるため先に結論です。
思い切ってザックリ言えば、次のとおり。
科学的に英語の学習効率は上がり続ける!
私自身、英語学習には悩みが尽きませんが、
明日から少し前向きになれるので紹介します。
言語獲得の累積増進モデル(Cumulative-Enhancement Model)は、言語学習において異なる言語を獲得する過程での脳の変化を説明するモデルの一つ。このモデルは、特に第二言語およびそれ以降の言語の習得に焦点を当てている。
以下、言語獲得の累積増進モデルの主要ポイント:
前提:
このモデルの出発点は、第一言語の習得が行われると、脳の特定の領域が言語処理において特化するという前提にあります。この特化された領域は、言語に関する情報を処理するのに最適化されています。
第二言語の獲得:
既に第一言語を獲得した後、第二言語を学習するプロセスでは、初めての言語獲得によって形成された脳の言語処理領域が、新しい言語の獲得においても活用されると仮定されています。
累積効果:
このモデルでは、異なる言語の獲得が脳の言語処理領域に累積的な影響を与え、それが次の言語の獲得においても有利に働くと考えられています。すなわち、新しい言語を学ぶ際には、既に獲得した言語の経験が積み重なり、学習を助けるとされています。
神経可塑性:
モデルは、脳の神経可塑性(ニューロプラスチシティ)が言語学習において重要な役割を果たしていると仮定しています。言語学習に従事することで、脳の構造や機能が変化し、言語処理の効率が向上すると考えられています。
異なる言語の影響:
モデルによれば、最初に獲得した言語と新しい言語との間には共通点があり、これが言語獲得の効率を向上させる要因となるとされています。この共通性は、文法構造や単語の類似性など、異なる言語間での共通の要素に関連しています。
言語獲得の累積増進モデルは、言語学習が単なる個別の言語に留まらず、複数の言語の獲得が相互に影響し合うという観点から言語学習のプロセスを理解しようとするものです。
発表者:
2024年1月19日
東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻
酒井 邦嘉 教授
梅島 奎立 助教
マサチューセッツ工科大学 言語哲学科
スザンヌ・フリン 教授
一般財団法人 言語交流研究所
鈴木 堅史 代表理事
発表のポイント
● 英語やスペイン語等の習得経験のある日本語母語話者が、新たにカザフ語の文に音声で触れた時、その文法習得を司る脳部位を特定しました。
● この新たな言語習得を司る脳部位は、これまで母語や第2言語の文法処理に関わる「文法中枢」として研究チームが特定してきた「左下前頭回の背側部」と完全に一致しました。
● 多言語の習得効果が累積することで、より深い獲得を可能にするという仮説「言語獲得の累積増進モデル」が、脳科学によって明確に裏付けられました。
<社会的意義>
日本では初等教育から英語が教科になっていますが、日本人の英語力は毎年常に下降を続けています。この傾向は特に18~20歳の若年層で顕著であり、彼らの英語のスコアは直近の数年で「標準的 → 低い → 非常に低い」と最も顕著に低下しています(出典:「EF EPI英語能力指数」イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社https://www.efjapan.co.jp/epi/regions/asia/japan/)。その原因として、個々の単語の記憶や文法の学習に頼るような従来型の勉強法や、SNSなどで大量の文字情報に晒されて音声に触れる機会が乏しいことなどが考えられます。多言語の音声に触れることで、日本人でも新たな言語を柔軟に習得できる、という本研究の成果は、多言語を同時に習得することの相乗効果を明確に示唆しています。これは、言語の「自然習得」という考え方と合致しており、語学教育全般に一石を投じるものです。詳しくは、酒井著『勉強しないで身につく英語』(PHP研究所、2022年)を参照して下さい。
他の原因として、「外国語を教える」という誤解が挙げられます。ベルリン・フンボルト大学の創設者であり、言語学者でもあったヴィルヘルム・フォン・フンボルトは、「言語を本当の意味で教えるということは出来ないことであり、出来ることは、言語がそれ独自の方法で心の内で自発的に発展できるような条件を与えることだけである。(中略)各個人にとって学習とは大部分が再生・再創造の問題、つまり心の内にある生得的なものを引き出すという問題である」(Chomsky,1965;福井・辻子訳,2017)と1836年に結論づけています。これはアメリカの言語学者ノーム・チョムスキーが提唱する「言語生得説」の基礎となる考え方であり、あらゆる自然言語の背後にある普遍性を裏付けるものです。この仮説の脳科学的な根拠については、酒井著『チョムスキーと言語脳科学』(インターナショナル新書、2019年)を参照して下さい。
論文情報
Keita Umejima, Suzanne Flynn, Kuniyoshi L. Sakai*, "Enhanced activations in the dorsal inferior frontal gyrus specifying the who, when, and what for successful building of sentence structures in a new language(新たな言語の文構造を正しく構築する上で「誰、何時、何」を規定する背側下前頭回の活動上昇)," Scientific Reports (Nature Portfolio Journal):
Enhanced activations in the dorsal inferior frontal gyrus specifying the who, when, and what for successful building of sentence structures in a new language
Abstract
It has been argued that the principles constraining first language acquisition also constrain second language acquisition; however, neuroscientific evidence for this is scant, and even less for third and subsequent languages. We conducted fMRI experiments to evaluate this claim by focusing on the building of complex sentence structures in Kazakh, a new language for participants having acquired at least two languages. The participants performed grammaticality judgment and subject-verb matching tasks with spoken sentences. We divided the participants into two groups based on the performance levels attained in one of the experimental tasks: High in Group I and Low in Group II. A direct comparison of the two groups, which examined those participants who parsed the structures, indicated significantly stronger activations for Group I in the dorsal left inferior frontal gyrus (L. IFG). Focusing on Group I, we tested the contrast between the initial and final phases in our testing, which examined when the structures were parsed, as well as the contrast which examined what structures were parsed. These analyses further demonstrated focal activations in the dorsal L. IFG alone. Among the individual participants, stronger activation in the dorsal L. IFG, measured during the sentence presentations, predicted higher accuracy rates and shorter response times for executing the tasks that followed. These results cannot be explained by task difficulty or memory loads, and they, instead, indicate a critical and consistent role of the dorsal L. IFG during the initial to intermediate stages of grammar acquisition in a new target language. Such functional specificity of the dorsal L. IFG provides neuroscientific evidence consistent with the claims made by the Cumulative-Enhancement model in investigating language acquisition beyond target second and third languages.
用語説明
(注1)MRI装置
MRI(磁気共鳴画像法)は、脳の組織構造を、水素原子の局所磁場に対する応答性から測定し画像化する手法で、全く傷をつけずに外部から脳組織を観察する方法として広く使用されています。そのために使用する医療機器が、超伝導磁石によって高磁場(3テスラ程度)を発生させるMRI装置です。注3で述べる「fMRI」でも、このMRI装置を使用します。
(注2)左下前頭回の背側部
下前頭回の背側部(ブロードマンの44/45/6野)は、脳の前頭葉に左右それぞれある領域です。左脳のこれらの領域は、人間の言語処理に関わる「言語野」の一部であり、特に文法処理を司る「文法中枢」の機能があります。右脳の方は文法中枢を補助する働きがあります。
(注3)fMRI(機能的磁気共鳴画像法)
脳内の神経活動に伴う血流変化を、局所磁場の変化から測定し画像化する手法で、時間的に変化する脳活動を、脳組織に全く傷をつけずに外部から精度良く観察する方法として、1990年代から広く使用されています。
・Enhanced: 強化された
・activations: 活性化
・dorsal: 背側
・inferior frontal gyrus: 下前頭回
・specifying: 特定する
・successful: 成功した
・building: 構築
・sentence structures: 文構造
・Abstract: 要約
・argued: 主張されています
・principles: 原則
・constraining: 制約する
・first language acquisition: 第一言語獲得
・second language acquisition: 第二言語獲得
・neuroscientific evidence: 神経科学的な証拠
・scant: 乏しい
・even less: なおさら
・third and subsequent languages: 第三およびそれ以降の言語
・conducted: 行いました
・fMRI experiments: fMRI実験
・evaluate: 評価する
・claim: 主張
・focusing on: 焦点を当てる
・complex: 複雑な
・Kazakh: カザフ語
・participants: 被験者
・having acquired: 獲得している
・at least: 少なくとも
・two languages: 2つの言語
・performed: 実施しました
・grammaticality judgment: 文法判断
・subject-verb matching tasks: 主語-動詞の一致タスク
・spoken sentences: 話された文
・divided: 分けられました
・two groups: 2つのグループ
・based on: に基づいて
・performance levels: パフォーマンスレベル
・attained: 達成された
・one of the experimental tasks: 実験的なタスクの一つ
・High in Group I: グループIは高い
・Low in Group II: グループIIは低い
・direct comparison: 直接比較
・examined: 調査しました
・those participants who parsed the structures: 構造を解析した被験者
・indicated: 示されました
・significantly stronger activations: 有意に強い活性化
・left inferior frontal gyrus (L. IFG): 背側左下前頭回(L. IFG)
・Focusing on: 焦点を当てて
・contrast between: ~の間の対照
・initial and final phases: 初期と最終フェーズ
・testing: テスト
・examined: 調査しました
・structures were parsed: 構造が解析された
・what structures: どの構造
・analyses: 分析
・further demonstrated: さらに示しました
・focal activations: 局所的な活性化
・individual participants: 個々の被験者
・measured during: ~中に測定された
・sentence presentations: 文の提示
・predicted: 予測しました
・higher accuracy rates: より高い正答率
・shorter response times: 短い応答時間
・executing the tasks: タスクを実行する
・followed: 後続
・results: 結果
・cannot be explained by: ~で説明できない
・task difficulty: タスクの難易度
・memory loads: 記憶負荷
・instead: 代わりに
・critical: 重要な
・consistent role: 一貫した役割
・initial to intermediate stages: 初期から中間段階
・grammar acquisition: 文法獲得
・functional specificity: 機能的な特異性
・investigating: 調査する
新しい言語の文構造を成功裏に構築するために、被験者が少なくとも2つの言語を獲得している場合における主語、時制、および内容を特定する背側上側前頭回の強化された活性化
要約
第一言語獲得を制約する原則が第二言語獲得にも制約を与えると主張されていますが、これに対する神経科学的な証拠は乏しく、第三およびそれ以降の言語についてはなおさらです。我々は、少なくとも2つの言語を獲得した被験者を対象に、新しい言語で複雑な文構造を構築することに焦点を当て、この主張を評価するためのfMRI実験を行いました。被験者は、話された文に対する文法判断と主語-動詞の一致タスクを実施しました。被験者は実験的なタスクの一つでの達成レベルに基づいて2つのグループに分けられました:グループIは高いパフォーマンスで、グループIIは低いパフォーマンスでした。構造を解析した被験者を調査した両グループの直接比較では、グループIの背側左上側前頭回(L. IFG)で有意に強い活性化が示されました。グループIに焦点を当て、我々のテストの初期と最終フェーズの間で構造が解析された時点を調査した対照と、解析された構造を調査した対照を検討しました。これらの分析は、背側L. IFGだけで焦点を当てた局所的な活性化をさらに示しました。個々の被験者の中で、文の提示中における背側L. IFGの強い活性化は、後続のタスクの実行においてより高い正答率と短い応答時間を予測しました。これらの結果は、タスクの難易度や記憶負荷では説明できず、代わりに、新しい目標言語の文法獲得の初期から中間段階における背側L. IFGの重要で一貫した役割を示しています。この背側L. IFGの機能的な特異性は、対象となる第二および第三言語を超えた言語習得を調査するCumulative-Enhancementモデルによって提唱された主張と一致する神経科学的な証拠を提供しています。
今後も英語学習に関わる情報、体験談を発信していきます。
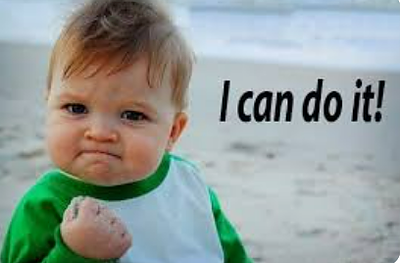
関連するコラム
- 英文記事を読む:日本のGDP ドイツに抜かれる 2023-11-18
- 英文記事を読む:New York Times 韓国は消えゆくのか / 日本 対岸の火事ではない / 韓国メディア反応 2023-12-18
- 英語記事を読む 【 EVの現状を考える 】 電気自動車のメリットはデメリットを上回るか 2023-10-14
- 英文記事を読む:北朝鮮 4代世襲 事実上確定か【基本的人権 VS 国家主権】 2023-12-09
- 英文記事を読む:★ 岸田首相談話 ★ 官邸 ★ 日本国民が外国人に放火していると英文発信 2024-02-24
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
TEX 二井原プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。