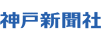英検1級取得者によるオンライン個別指導のプロ
英語パーソナルジム HIET(ヒート)/ High Intensity English Training
- お電話での
お問い合わせ - 090-3825-5237
コラム
英文記事を読む:大阪万博 ★英国 Fianancial Times がツッコミ入れる ★準備の見世物ショー
2023年12月22日
本記事は独学・国内学習による
英検1級保持者が書きました。
「これだけはっきり言っておきます。
IR、カジノには一切税金使いません」
2016年12月22日、都構想説明会にて
当時の松井一郎大阪府知事がそう断言して
「大阪維新」が進めてきた大阪IR関連事業の公費負担が、
ここに来て青天井の膨張を続けています。
大阪万博はゴミの埋め立て地にカジノ建設するための
鉄道・道路・水道・下水等インフラ整備の隠れ蓑として
国家予算確保に利用した維新の詭弁です。
関西人なら誰でも吹田に広大な万博跡地があることを
知っています。
カジノ誘致の為に鉄道を引くとは口が裂けても言えない
ので、維新は現時点でもカジノと大阪万博は無関係で
あるという立場で徹底しています。
次はコントでもフェイクニュースでもありません。
★ 世界最大&最高額の日よけ大屋根リング1度1億円!
★ 清水寺と同じ伝統的抜き工法 -釘&ボルト留め仕様!
★ 経済効果6兆円!(松井氏4年前)
★ 経済効果2兆円!(吉村氏現在)
★ 経済効果の算出法及び根拠 …不明
大阪万博 インフラ整備費9.7兆円 政府 全体像示す
毎日新聞 2023/12/19
政府は19日、2025年大阪・関西万博の費用の全体像を発表した。関連するインフラ整備費は約9・7兆円に上り、うち万博会場に直接関係するものは計8390億円だった。これらインフラ整備費とは別に会場建設費など万博に直接資する国費負担は計1647億円で、さらに来年度以降、機運を高めるためのイベント費用なども加わる見通しだ。
万博会場に直接関係するインフラ整備費の内訳は、会場となる人工島・夢洲(ゆめしま)と市街地を結ぶシャトルバスのルートとなる阪神高速「淀川左岸線」2期整備事業など「会場へのアクセス向上費用」が7580億円。他に万博会場の最寄り駅となる「夢洲駅」までの大阪メトロ中央線延伸など「会場周辺の整備費」が810億円となった。また、ほかのインフラ整備費として「安全性の向上」2兆5490億円▽「にぎわい・魅力の向上」3410億円▽「広域的な交通インフラの整備」5兆9280億円――などを挙げた。
「にぎわい・魅力の向上」3410億円ってなんやねん?
とかケチ臭いツッコミはやめてね。
まだまだ行きまっせ!
機運醸成費用 約38億円!
途上国の出展支援 約240億円!
大阪府民は万博の為ならタンパク質は要りまへん!
【大阪府豊中市 学校給食】
刑務所の飯の方がマシやんって言いまへん!
【網走刑務所 栄養バランスご飯】
。。。さて、
英検1級ライティングの観点としては次が重要です。
論点整理:カジノがもたらす利益は不利益に勝るか
Benefits:
Economic boost:
Casinos can generate significant revenue, create jobs, and stimulate local economies through tourism and spending.
Entertainment and amenities:
They often offer entertainment options, restaurants, and hotels, providing a range of amenities for both locals and tourists.
Tax revenue:
Casinos contribute to tax income for local governments, supporting public services and infrastructure development.
Employment opportunities:
They provide job opportunities across various sectors, including hospitality, gaming, and management.
Drawbacks:
Problem gambling:
Casinos can lead to addiction and financial problems for individuals and families affected by compulsive gambling behaviors.
Problem gambling:
Increased crime rates, particularly related to theft, fraud, and addiction-driven crimes, might occur in areas with casinos.
Economic volatility:
Dependency on casino revenue can make the local economy susceptible to fluctuations in the gambling industry.
Negative impact on local businesses:
Some local businesses might suffer as casino visitors primarily spend within the casino premises, limiting income for other establishments.
Please note that the impact of casinos on local communities can vary significantly based on various factors, including regulations, community dynamics, and the overall management of the casino operations.
● 経済的な活性化: economic boost
● 娯楽施設と設備: entertainment and amenities
● 税収: tax revenue
● 雇用機会: employment opportunities
● ギャンブル依存症: problem gambling
● 社会問題: social issues
● 経済的な不安定性: economic volatility
● 地元企業への悪影響: negative impact on local businesses
利点:
経済的な活性化: カジノは観光や支出を通じて著しい収益を生み出し、雇用を創出し、地域経済を刺激することがあります。
娯楽と施設: よく娯楽オプション、レストラン、ホテルなどを提供し、地元住民や観光客にさまざまな設備を提供することがあります。
税収: カジノは地方政府の税収に貢献し、公共サービスやインフラの開発を支援します。
雇用機会: カジノはホスピタリティ、ゲーム、管理などのさまざまな分野での雇用機会を提供します。
弊害:
ギャンブル依存症: カジノはギャンブル依存症やそれによる個人や家族の金銭的問題を引き起こす可能性があります。
社会問題: カジノの存在が増加した場所では、盗難や詐欺、依存による犯罪などの犯罪率が上昇することがあります。
経済的な不安定性: カジノ収入への依存は、地域経済が賭博産業の変動に影響を受けやすくする可能性があります。
地元企業への悪影響: カジノの訪問者が主にカジノ内での支出に限定されるため、他の施設への収入が制限される可能性があります。
カジノが地域社会に及ぼす影響は、規制や地域社会の状況、カジノ運営の全体的な管理など、さまざまな要因によって大きく異なることに留意してください。
What is the point of an expo in today’s world?
The chaotic build-up to Japan’s event suggests it is a relic of a past global order
Financial Times
2023/12/19
Mexico and Estonia have pulled out but Denmark, Cameroon and Jamaica still want in. Construction costs are spiralling so fast that Brazil, Argentina and Poland are said to be considering moving their showcases into a glorified warehouse. A European nation was told by one of Japan’s biggest contractors that, yes, they will certainly complete the desired pavilion — a month after the event is finished.
The preparations for the Osaka 2025 World Expo, in the era of binge-watchable docudrama, are going perfectly. If organisers really put in the effort, they may even get a two-season box set out of it.
From many angles, even officials directly involved admit, the scene on the artificial island of Yumeshima in Osaka bay less than 18 months before the world expo is due to open looks less than ideal. Work has finally started on the wooden ring that will encircle the national pavilions, but visitors to the site are still standing in what feels like an empty, 155-hectare car park.
A vast summit this week bringing together organisers and the more than 150 countries involved has gone somewhat better than expected, say participants, but those expectations were remarkably and grumpily low.
This month, the government approved the projected $1.6bn cost for building the main venue — a figure running at almost twice the original estimate and inviting speculation that it could go higher still. This approval, justified by the soaring costs of labour and materials, represented an act of fiscal largesse, which prompted local TV stations to provide yen-by-yen breakdowns of the enlarged burden on already grumbling, inflation-battered taxpayers.
An increasing number of diplomats, griping in private about the task that lies ahead, are even more scathing and hint that, if they felt they could get away with doing so, they would withdraw or downgrade. Quoted costs for pavilion construction are in some cases significantly higher than first envisaged and half of the countries booked to build the premier pavilions have not yet submitted plans. Many, confronting byzantine Japanese building regulations, are struggling to secure the local contractors and approvals they need to build pavilions. The prospect of building something “practical but pointless”, says one Asian diplomat, is very real.
Swirling around all this is the question of what the purpose of the whole expo enterprise really is, and how best to generate the sort of enthusiasm that, in the case of wildly over-budget sports events such as world cups or Olympics, is ultimately provided by the sport itself. The fact that, after its six-month run, the entire expo will be completely demolished presents additional communications challenges around sustainability.
World expos, dating back to London’s Great Exhibition of 1851, once had a much clearer purpose: they were truly thrilling international showcases for inhabitants of a world that travelled less and had limited exposure to the food, technology and culture of “abroad”. The Osaka expo, along with many of the participating countries, are doubtless earnest in the desire to provide a modernised version of that thrill. The difficulty lies in defining “global reach” in an era when a single YouTube video of how to bake a Minecraft cake village, or how to cook chicken biryani, receives more views than the 28mn visitors the expo organisers are expecting.
But, whether disastrous or delightful, this will all be extraordinarily watchable. And perhaps that is how expos must evolve: as spectacles of preparation, rather than completion.
Many of the problems confronting the Osaka expo are, fascinatingly, Japan’s in microcosm: the acuteness of the labour shortage, regulatory intransigence and budgetary slippage prominent among them. But the faith in the meaning of the event itself is exquisitely Japanese too. World expos are emotionally anchored in an old global order from which Japan has benefited enormously; the looming replacement of that order — both technological and geopolitical — is likely to be far less kind. Japan’s nostalgic passion for this sort of project is a driving force which should not be underestimated, and which will be a white-knuckle pleasure to watch.
The manifest chaos and public backlash around the expo put us, the viewers, exactly where we should be at this point for the story arc to work. If expos are to remain relevant, they must do so in an era where the world, its viewing tastes shaped by emotion-churning documentaries on catastrophic music festivals or celebrity-owned underdog football teams, wants to see these things framed as a crisis or a crisis overcome. A multibillion-dollar world expo, in a world that doesn’t really need them, guarantees at least one of the two.
● Expo: エキスポ
● chaotic build-up: 混沌とした準備
● relic of a past global order: 過去の世界秩序の遺物
● construction costs: 建設費
● spiralling: 急速に増大している
● glorified warehouse: 格調高い倉庫
● pavilion: パビリオン
● binge-watchable: 一気見できる
● box set: ボックスセット
● artificial island: 人工島
● site: 現場
● car park: 駐車場
● summit: 首脳会議
● fiscal largesse: 財政的寛容
● labor and materials: 労働力と資材
● inflation-battered taxpayers: インフレに苦しむ納税者
● diplomats: 外交官たち
● regulatory intransigence: 規制の頑固さ
● communications challenges: コミュニケーション上の課題
● emotional-churning documentaries: 感動を呼ぶドキュメンタリー
● catastrophic: 破滅的な
● underdog: 劣勢の立場にある者
● spectacular: 見応えのある
● microcosm: 縮図
● nostalgic passion: 懐古的な情熱
● geopolitical: 地政学的
● white-knuckle pleasure: 白熱した喜び
● story arc: 物語の展開
● multibillion-dollar: 数十億ドルの
● relevance: 関連性
今日の世界におけるエキスポの意義は何か?
日本のイベントへの混沌とした準備は、過去のグローバル秩序の遺物であることを示唆しています。
メキシコとエストニアが撤退しましたが、デンマーク、カメルーン、ジャマイカはまだ参加を望んでいます。建設費が急速に増大しているため、ブラジル、アルゼンチン、ポーランドは自国のショーケースを格式のある倉庫に移すことを検討していると言われています。日本の大手建設業者からある欧州の国に、「イベントが終了した後、1か月後には確実に望まれるパビリオンを完成させます」と告げられました。
2025年の大阪万博の準備は、見ていても完璧に進行しています。もし主催者が本当に努力をすれば、それで2シーズン分のボックスセットを手に入れるかもしれません。
多くの角度から、直接関与している公式すら認めるように、開幕まで18か月を切った大阪湾の夢洲島の現場は、理想とは程遠い状態です。国立パビリオンを囲む木製のリングの工事はようやく始まりましたが、現地を訪れる人々はまだ155ヘクタールの空き地のように感じられる場所に立っています。
今週行われた大規模な首脳会議は、参加国の150以上の組織者との間で予想以上にうまくいったと参加者は言いますが、それらの期待は非常にぶすっとしたものでした。
今月、政府は主会場の建設費について160億ドルを承認しました。これは元の見積もりのほぼ2倍に達しており、さらなる増加の可能性が取りざたされています。労働力や資材の費用が急騰していることを正当化するこの承認は、もはや不満とインフレに苦しむ税金を支払っている人々に負担をかけるとして、地元のテレビ局が円単位で拡大された負担を提供しています。
多くの外交官たちは、彼らが逃げられると感じたら撤退したり格下げしたりするだろうと示唆し、私的に不満を言っています。パビリオン建設の見積もり費用は、初期の見込みよりもかなり高く、最高のパビリオンを建設する予定の国の半分がまだ計画を提出していません。多くの国々は、複雑な日本の建築規制に直面し、パビリオンを建設するために必要な現地の請負業者や承認を確保するのに苦労しています。あるアジアの外交官は、「実用的でありながら無意味なものを建設する見込みが非常に現実的である」と述べています。
このすべての中で渦巻くのは、エキスポ企画全体の目的と、ワールドカップやオリンピックのような予算超過のスポーツイベントの場合に最終的にはスポーツそのものが提供する感動を最良に生み出す方法です。エキスポが6か月間開催された後、完全に解体されるという事実は、持続可能性に関する追加のコミュニケーション上の課題を提起します。
1851年のロンドン万国博覧会から始まるワールドエキスポは、かつてはよりはっきりとした目的を持っていました。それは、旅行が少なく「外国」の食べ物、技術、文化に限られた世界の住人にとって本当にワクワクする国際的なショーケースでした。大阪万博は、参加国の多くと共に、その興奮の近代版を提供することを熱望していることは疑いの余地はありません。難しいのは、1本のYouTube動画がエキスポ主催者が期待する2800万人の訪問者よりも多くの視聴回数を得る時代において、「グローバルリーチ」を定義することです。
しかし、失敗であろうと成功であろうと、これは非常に見応えのあるものでしょう。そして、おそらくエキスポは進化すべきなのです:完成ではなく準備のスペクタクルとして。
大阪万博に直面している多くの問題は、興味深く、日本全体の縮図でもあります。労働力不足、規制の頑固さ、予算の逸脱などがその中心にあります。しかし、イベント自体の意義への信念は、日本独特のものです。ワールドエキスポは、日本が莫大な利益を得た旧世界秩序に感情的に根ざしています。その秩序の代替が迫っており、それは技術的、地政学的にともに、はるかに寛容ではなくなるでしょう。日本のこの種のプロジェクトへの懐古的な情熱は、過小評価されてはならず、白熱した喜びをもたらすでしょう。
エキスポの周囲に渦巻く混乱と一般市民の反発は、私たち視聴者を物語の展開において正確な位置に置いてくれます。エキスポが関連性を保つためには、音楽フェスティバルの崩壊やセレブ所有のアンダードッグフットボールチームに関する感動的なドキュメンタリーによって形作られた視聴嗜好に沿った、危機とそれを克服した姿として提示されなければなりません。世界が本当にそれらを必要としない世界で数十億ドルのワールドエキスポは、少なくともそのうちの一つを保証してくれるのです。
今後も英語学習に関わる情報、体験談を発信していきます。
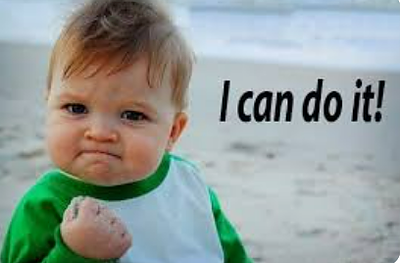
関連するコラム
- 英語記事を読む 電気自動車のメリットはデメリットを上回るか 2023-11-10
- 英文記事を読む:性別変更の手術要件は違憲 日本の最高裁が決定 2023-10-26
- 【発達障害 クラスに3人】っていう前に「医学的定義」を示すべき 我、教育の端くれ専門家として想う 2023-12-26
- 英文記事を読む:性転換手術望む英国少女 10年で4400%増! 性転換手術禁止への動き 2023-12-08
- 英文記事を読む:文科省調査 「発達障害 8.8%」と言うが「発達障害」の定義が。。。 2023-12-22
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
TEX 二井原プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。