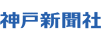英検1級取得者によるオンライン個別指導のプロ
英語パーソナルジム HIET(ヒート)/ High Intensity English Training
- お電話での
お問い合わせ - 090-3825-5237
コラム
東北大学 入試問題で「実証主義」を考える
2023年10月24日 公開 / 2023年10月25日更新
前回、京大英作文をめぐる英語講師とのやり取りの1部を紹介しました。
講師が自力答案を作成するのは英作文に限らず、読解問題でも同様です。
その際の思考回路が授業準備になるためです。
予備校のテキストには「模範答案」が用意されていますが、
その答案は講師にとって「借り物の理解」なので、
下手に頼ると授業がグタグタになってしまうのです。
だから、予備校が用意した模範答案は授業で配布するだけになります。
以下、講師とのやりとりです。
<ある英語講師のコメント>
東北大学の長文で答案作ったからコメント貰えますか。
【第6講】
次の英文を読み,下の問いに答えなさい。(2020 東北大学 2/25,前期)
The English Renaissance philosopher, politician, and scientist Francis Bacon is widely credited with establishing the fundamentals of the experimental method in science. ‘The best demonstration by far is experience, if it go not beyond the actual experiment,’ he wrote in his book Novum Organum. Bacon showed in words how science proceeds by trial and error, and in deed how some of its errors prove to be fatal. Travelling by coach and horse with one of the king’s physicians to Highgate in London, it suddenly occurred to Bacon that the snow lying all around him might be as effective as salt at preserving flesh. Desiring to test (A)the theory without delay, the pair went into a poor woman’s house at the bottom of Highgate Hill, bought a hen off her which they got her to *eviscerate, and then stuffed it with snow. In the process, however, Bacon caught such a sudden and extreme chill that he couldn’t even make it home. The Earl of Arundel, who lived locally, put him up but unfortunately in a (1)damp bed that did more harm than good. A few days later, he died of pneumonia.
Given that Bacon helped establish the *empirical principle that conclusions should be grounded in evidence, it is ironic this well-known story about him is probably untrue. The irony, however, goes deeper than that. Bacon’s supposed cause of death exemplifies the difficulties of taking a scientific, evidence-based approach in the first place. Folk wisdom has for centuries insisted that it is possible to ‘catch a chill’. But when modern science examined the evidence for this, it seemed to be no more than a superstition. A number of laboratory experiments introduced cold viruses into people’s noses, exposing some to cold air and others not, and they repeatedly showed that the temperature had no effect at all. The reason for this seemed simple enough: the common cold is caused by *rhinoviruses, flu by influenza viruses, pneumonia by bacteria. Temperature has nothing to do with it. If you get extremely cold for too long you can get *hypothermia, but you can’t ‘catch a chill’.
Then in January 2015, headlines like ‘Mom Was Right: You’ll Catch a Cold from Being Cold’ appeared in serious newspapers and magazines. A team at Yale University led by Ellen F. Foxman had found that ‘the innate immune response to the rhinovirus is (2)impaired at the lower body temperature compared to the core body temperature.’ In other words, whether the cold virus is present in your nose does not depend on the temperature, but your immune response to it does, and that means you may indeed be more likely to catch a cold if you get cold: or rather, more likely to develop a cold if your nose has already caught the virus.
(B)These examples don’t look like good evidence for the reliability of evidence-based truth. We are left without enough evidence to reach firm and final conclusions both on an historical question about the cause of a particular death and a scientific question about causes of deaths in general. We seek evidence but often, perhaps usually, it is elusive, absent, ambiguous and inconclusive. *Etymologically, empirical means ‘from experience’, and experience seems to be telling us that an empirical approach leaves us with uncertainty, rather than knowledge.
Far from being a weakness, however, (C)the open-endedness of empirical inquiry is actually its strength. David Hume made this point wonderfully when he observed that ‘all the objects of human reason or inquiry may naturally be divided into two kinds, namely, Relations of Ideas, and Matters of Fact.’ Relations of ideas concern truths of mathematics, geometry, and pure logic. Such truths are, in effect, true by definition, but they tell us nothing about the real world. Matters of fact, in contrast, cannot be established by pure logic. That also means they cannot be established with 100 percent certainty. ‘The contrary of every matter of fact is still possible,’ warned Hume. ‘That the sun will not rise tomorrow is no less (3)intelligible a proposition, and implies no more contradiction than the affirmation, that it will rise.’ Indeed, we can easily imagine circumstances in which we would have to accept that the sun is unlikely to rise tomorrow, such as if a massive asteroid were about to hit the Earth.
A lack of certainty is therefore part of the deal with empirical truth. We need to give up on it in order to take up the possibility of knowledge of the world. Absolute certainties can only be obtained about purely conceptual matters, such as *axioms of mathematics and laws of logic. If we want to know about the world then there is potentially no end of discoveries ― for ourselves or the entire human race ― that might force us to alter our opinions. (D)What we hold to be true is constantly open to being tested, which makes the truths that pass the test more reliable. The strength of empirical truth resides in the fact that it is always open to (4)scrutiny, revision and rejection.
(Adapted from Julian Baggini, “Empirical Truth,” in A Short History of Truth: Consolations for a Post-Truth World)
(注)
*eviscerate 動物の内臓を抜く*empirical 実証的な
*rhinoviruses ライノウイルス(風邪を引き起こすウイルスの一種)
*hypothermia 低体温症*etymologically 語源的には
*axioms 公理
問1 下線部(A)が指す内容を日本語で説明しなさい。
問2 下線部(B)は具体的にどのようなことを意味しているか,本文に即して日本語で説明しなさい。
問3 下線部(C)は具体的にどのようなことを意味しているか,本文に即して日本語で説明しなさい。
問4 下線部(D)を日本語に訳しなさい。
問5 下線部(1)~(4)の意味として最も適切なものを,それぞれ与えられた選択肢から選び,記号で答えなさい。
(1) damp
(ア) cold (イ) dusty (ウ) moist (エ) uncomfortable
(2) impaired
(ア) intoxicated (イ) weakened (ウ) lacking (エ) bruised
(3) intelligible
(ア) comprehensible(イ) evident(ウ) irrational (エ) inexplicable
(4) scrutiny
(ア) persuasion(イ) investment(ウ) acceptance (エ) inspection
【訳例】
「英語ルネサンスの哲学者、政治家、そして科学者であるフランシス・ベーコンは、科学における実験的方法の基本を確立したと広く認められています。彼は自著『新機関』で、「最も優れた証拠は経験であり、それが実験の範囲を超えない場合」と述べました。ベーコンは言葉で科学が試行錯誤によって進む方法を示し、その誤りの一部が致命的であることを実証しました。ロンドンのハイゲートへの馬車で王の医師の一人と一緒に旅行している最中、ベーコンは周りに積もる雪が肉を保存するために塩と同じぐらい効果的かもしれないと突如として思いつきました。この理論をすぐに検証したいと考え、2人はハイゲートの坂の下にある貧しい女性の家に入り、彼女から鶏を購入し、鶏を解体させ、それから雪で詰めました。しかし、この過程でベーコンは突然の激しい寒さにかかり、さえ帰宅できないほどでした。地元のアランデル伯爵が彼を収容しましたが、残念なことに湿気のあるベッドで休ませたため、むしろ害をもたらしました。数日後、彼は肺炎で亡くなりました。
ベーコンが証拠に基づく原則を確立するのに役立ったことを考えると、彼に関するこの有名な話がおそらく事実ではないというのは皮肉です。しかし、この皮肉はそれ以上に深刻です。ベーコンの死因とされるものは、科学的で証拠に基づくアプローチを取る難しさを示しています。何世紀にもわたり、民間の知恵は「風邪を引く」ことが可能であると主張してきました。しかし、近代の科学がこれに対する証拠を調査すると、それが迷信に過ぎないように見えました。数々の実験で、寒い空気にさらされた人々に風邪ウイルスを導入し、他の人々にはさらされなかったところ、温度はまったく影響を与えなかったと繰り返し示されました。その理由は非常に単純でした。風邪はライノウイルスによって引き起こされ、インフルエンザはインフルエンザウイルスによって引き起こされ、肺炎は細菌によって引き起こされます。温度とは何の関係もありません。非常に寒くなりすぎると低体温症になるかもしれませんが、「風邪を引く」ことはできません。
しかし、2015年1月、『お母さんは正しかった:寒さから風邪を引く』という見出しが真面目な新聞と雑誌に登場しました。イェール大学のエレン・F・フォクスマン率いるチームが、「ライノウイルスへの先天性の免疫応答は、体の中心部温度と比較して低い体温では妨げられる」と発見しました。言い換えれば、鼻に風邪ウイルスが存在するかどうかは温度に依存しないが、それに対する免疫応答は依存するということです。つまり、寒くなると風邪を引きやすくなる可能性がある、あるいはむしろ、鼻が既にウイルスを捕らえている場合、風邪を引きやすくなるかもしれません。
これらの例は、証拠に基づく真実の信頼性を示すものではないように見えます。私たちは特定の死因に関する歴史的な質問と一般的な死因に関する科学的な質問の両方について、確かで最終的な結論に達するための十分な証拠がないままです。語源的には、「実証的」は「経験に基づく」という意味であり、経験は実証的アプローチによって知識の代わりに不確実性をもたらすと思われます。
しかし、実証的探求の開放性は実際にはその強みです。デイヴィッド・ヒュームは、『人間の理性または研究対象の対象は、自然に2つの種類に分けることができる。すなわち、アイデアの関係と事実の問題である』と素晴らしい指摘をしました。アイデアの関係は数学、幾何学、および純粋な論理の真実に関係しています。そのような真実は実質的に定義によって真実であり、実世界については何も教えてくれません。一方、事実の問題は純粋な論理で確立することはできません。それはまた100パーセントの確実性で確立できないことを意味します。ヒュームは「事実の反対はまだ可能である」と警告しました。明日太陽が昇らないという主張は、明日太陽が昇ると主張することと同じ程度に理解可能であり、矛盾を含まないと言いました。実際、地球に巨大な小惑星が衝突しようとしている場合など、太陽が明日昇らない可能性を受け入れる必要がある状況を簡単に想像できます。
したがって、確実性の欠如は実証的真実の一部です。私たちはそれを受け入れて、世界の知識の可能性を追求する必要があります。絶対的な確信は、数学の公理や論理の法則など、純粋な概念に関してのみ得ることができます。世界について知りたい場合、自分自身または人類全体にとって、意見を変更させるかもしれない無数の発見の可能性があるかもしれません。私たちが真実と考えるものは常にテストの対象となる可能性があるため、テストを通過した真実がより信頼性があるのです。実証的な真実の強さは、常に検討、改訂、拒絶の対象となることにあります。」
〔語彙リスト〕
● 実験的方法 - Experimental method
● 経験 - Experience
● 新機関 - Novum Organum (The title of Francis Bacon's book)
● 試行錯誤 - Trial and error
● 帰宅 - Return home
● 低体温症 - Hypothermia
● 語源的には - Etymologically
● 公理 - Axioms
● 実証的 - Empirical
● ライノウイルス - Rhinoviruses
● 検証 - Scrutiny
● 事実の問題 - Matters of fact
● 純粋な論理 - Pure logic
● 確実性 - Certainty
● 仮説 - Theory
● 疾患 - Illness
● 病気 - Disease
● 免疫応答 - Immune response
● 不確実性 - Uncertainty
● 知識 - Knowledge
● 主張 - Assertion
● 寒冷感 - Chill (in the context of catching a chill)
● 真実 - Truth
● 真実の信頼性 - Reliability of truth
● 理論 - Theory
● 概念 - Concept
● 矛盾 - Contradiction
● 強み - Strength
● 受け入れる - Accept
● 確信 - Confidence
<僕のコメント>
了解です。
しかし最近の東北大学は東大、京大よりも優れた英文を使ってきますね。
この大学は設問の焦点が基礎的やから一般に誤解されてると思う。
実は、問題
難度が高いというより高いレベルの教養を突いてくる。
近年の入試問題で同じことが言える大学は、
● 九州大学
● 京都大学
● 大阪大学 外国語学部
● 一橋大学
● 東京工業大学
● 慶応大学 法学部
とかですかね。
<ある英語講師のコメント>
だいたい同じ意見やけど、英文の質は東北大学が突出してますよ。
その事が全く指摘されてないのが不思議です。
ご指摘のとおり、設問の焦点が基礎的であることで
本質が浮き彫りになりにくいのかもしれません。
<僕のコメント>
確かに今回の英文も「実証主義」の弱点を万人が納得する形で
指摘していて、出題者の意図と信念を感じますね。
<ある英語講師のコメント>
答案の話に入るけど、
赤本等の答案がポイントから外れてるようにも思いますね。
第6講:解答例(東北大2020年)(赤本)
問2:ベーコンが寒さが原因で風邪をひき肺炎になって亡くなったと思われており、風邪は寒さではなくウイルスが原因だと判明しある時点まではそれが真実ということになっていたが、最近の研究では低温では免疫力が下がり鼻の中にいるウイルスの活動が活発になることで風邪をひきやすくなるということが新たに示されたということ。
問3:証拠に基づく実証的な研究は、その証拠の不確実さゆえに完全な確証をもたらすことなく絶えず変更される可能性があるということ。
(ある講師作成の別解)
問2:ベーコンの死因は「風邪をひいた」ことからの肺炎の罹患によるものと言われてはいるが、(昔のことゆえ)何らかの証拠によっては検証できない。一方、昔から常識的に語られていた「風邪をひく」というのは迷信に過ぎず、風邪はウイルスによるものと証拠による科学的な検証で真実だとこれまでは判定されていたが、最近の研究によって、「風邪をひく」という表現はその現象を説明する言葉として(は間違っていないということが)改めて認められたというように、真実の認定が確定しないということ。
問3:実証的探究には終わりがないということ。
⇩
実証的探究は、起こった事実に基づいて検証し結論を出すので、
異なる事実が出てきたとき、その事実に基づいて検証すると、これまでの結論とは変わってしまうというように、真実を確定するための検証は絶えず続いていくということ。
<僕のコメント>
内容は脇に置いて、両方の答案とも一文が長くないですか。
採点の際には予めセットされた焦点を機械的にカウントして
いくと想定されますよね。
だとすると、採点者に対して「採点基準」をシンプルに列挙して
アピりたいです。
ここから、内容の話です。
実証主義が持つ uncertainty を示すための examplesであることを
意識した答案を作ってみました。
問2:【別解の別解②】
昔からの民衆の知恵によると「寒さから風邪をひく」とされる。 実際、ベーコンの死因は寒さのため風邪をひき肺炎になったことであるとされていた。 しかし肺炎は「寒さではなく細菌に因る」という近代科学の実証から、 これは迷信ということになる。 ところが、エール大学の研究によってこの科学的知見は覆された。 この研究が「寒さから風邪をひく」ことを実証したためである。 このような実証主義による事実認定の変化の難しさを 典型的に示す事例を意味している。
問3に関しては、
答案に対比を含めたいです。
対比によって実証主義の本質を掘り下げているからです。
【問3:別解の別解②】
数学、幾何学では公理によって真理を確定する。 一方で、
実証主義では科学的事実は常に反証される余地があるため最終確定に至らない。
関連するコラム
- 大学入試 アウトプット英単語50 ① 2023-11-03
- 大学入試 アウトプット 英単語 ④ 2023-11-05
- 大学入試 アウトプット英単語 ⑨ 2023-11-06
- アウトプット英文法 5分トレーニング【不定詞③】 2023-11-10
- 京都大学英語 2023 【駿台予備校 VS 河合塾】 模範答案 考察 ① 2024-01-18
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
TEX 二井原プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。