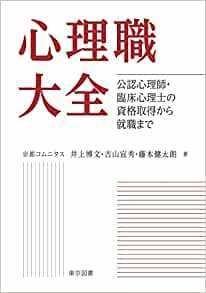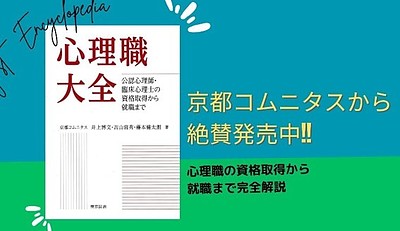コムニタスの名前の由来
1 迷いの宇宙空間
「公認心理師って何ですか?」
その質問を耳にするたび、私は、いまだにざわつきます。それは、心理職を目指そうと志した人が宇宙空間に放り出されたような気持ちになるのを何度も目にしてきたからだと思います。現代社会は、それはそれでストレス社会で、多くの人々が心の問題を抱えており、道に迷う・・・
近年、特に公認心理師ができて以来、心のケアに対する社会のニーズは高まっているという実感があります。一方、情報過多、人間関係の希薄化、経済的な不安、少子化、大学倒産、変な政治家もどきの出現、それに熱狂するカルト集団の復活、ストレス社会と呼ばれる現代において、人々の心は疲弊し、道に迷い、助けを求めている人の声は、異常者の大声にかき消されます。SNSを開けば、他者の成功や幸福が目に飛び込み、自己肯定感を蝕む。そんな時代だからこそ、心理の専門家である「心理職」の役割はますます重要になっていると考えています。
しかし、心理職の世界は複雑で、資格の種類も多岐にわたる。臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士、産業カウンセラー……。それぞれの資格がどのような役割を担い、どのように連携しているのか、一般の人々には理解しにくいのが現状です。
特に、2017年に誕生した国家資格「公認心理師」は、第8回試験が終わり、社会的な認知度はまだ十分とは言えないものの、徐々に高まってきました。だからこそなのか、臨床心理士との違いは何か、どのような活動ができるのか、多くの人々が新たに疑問をもちつつあります。公認心理師制度は、心理職の専門性を高め、国民の心の健康を支えるために創設されました。しかし、その真価が発揮されるまでには、いましばらく時間がかかるでしょう。
私自身も、公認心理師となりましたが、厚生労働省は、公認心理師の業務を以下のように定義しています。
1.心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
2.心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
3.心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
4.心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
何度も見たこの定義は、やはり抽象的で、解釈の幅が広いですが、その分、公認心理師は汎用性が高く、様々な場所で働くことができることがアドバンテージになっています。
日本心理研修センターは、公認心理師について「社会の変化に沿って生じるさまざまな課題に対応できるために、今後更にその資質の向上を図ることが求められています」と述べています。
つまり、公認心理師は、人々の心の健康をサポートする専門家として、常に自己研鑽を怠らず、社会の変化に対応していく必要があるということです。AI技術の進化、グローバル化の進展、自然災害の頻発など、社会は、常に変化し続けており、心理職もまた、時代に沿った変化に対応していく必要があります。
2 京都コムニタスは心理職の道標たらんとす
京都コムニタスを設立して以来、私が一貫して抱いている思いは、「どの人も大学院に行こう」というものです。それには「大学院を出て食べていける人になろう」ということが必要になります。もちろん、大学院に進学することが全てではありません。大学院に進学することだけが成功への道ではありません。しかし、近年、大学で学んだ知識をさらに深め、専門的な力を保有し、高度な専門知識とスキルを持つ人材が求められています。
臨床心理士や公認心理師の資格を取得するためには、指定された大学院を修了する必要があります。実は、日本の指定大学院システムは、様々な分野から評価が高く、とても信頼されています。こんなに全国に同じシステムが浸透した大学院教育システムは、他に類を見ません。
しかし、大学院に進学するためには、学費や生活費など、経済的な負担が大きいのは間違いありません。私立大学の大学院に進学する場合、2年間で200万円以上の学費が必要となることもあります(海外よりは安いのですよ)。また大学院での学びは、決して楽なものではなく、相応の覚悟と努力が求められます。そのため、「大学院に行っても食べていけない」という不安を抱く人も少なくないし、学費を払い終えて、本当に就職できるのか、生活していけるのか、多くの学生が不安を抱えているのも事実です。
私は、そのような不安を払拭し、「大学院に行けば食べていける」社会を実現したいと考えています。そのためには、大学院で学ぶことの価値を社会に広く伝え、どの人大学院に行ける社会になれば、リスクも少なくなります。少子、高齢化社会において、とても利点の多いことです。
しかし、近年、日本では学問が軽視される傾向にあり、「安い日本」になってしまいました。様々な要因が重なり、日本経済低迷・・・人件費抑制・・・中抜き・・・中身なき株価上昇(いつか急落するのはすでに通った道)・・・これでは、優秀な人材が育ちません。何とかしたい・・・そんな気持ちで『心理職大全』にたくさんの思いを込めました。
3 心理職大全の構成
『心理職大全』は、これから心理職を目指す人々にとって、教科書のような存在になることを目指して企画されました。単なる資格取得のための参考書ではなく、心理職としての生き方、考え方、倫理観などを総合的に学べる本を目指しました。
本書は、以下の三部構成となっています。
•第1部 日本の心理職と資格
oはじめに 大学院と心理職:なぜ大学院に進学する必要があるのか、大学院での学びが心理職にとってどのような意味を持つのかを解説する。
o第1章 大学院資格として成功した臨床心理士:臨床心理士の歴史、資格取得のメリット、キャリアパスなどを紹介する。
o第2章 臨床心理士の歴史:臨床心理士制度がどのように誕生し、発展してきたのか、その背景にある社会的なニーズや課題を解説する。
o第3章 国家資格公認心理師とは何か?:公認心理師の資格概要、業務内容、臨床心理士との違いなどを解説する。
•第2部 心理職資格取得後の仕事の実際
o第1章 心理職は食べていける:心理職の給与水準、就職状況、キャリアアップの可能性などを紹介する。
o第2章 現場で働くの心理職たちの声:様々な分野で活躍する心理職のインタビュー記事を掲載する。
公認心理師って仕事はあるの? 生活していけるの?(京都コムニタスGM 公認心理師・臨床心理士 吉山 宜秀):公認心理師としての仕事のやりがい、苦労、将来展望などを語る。
教育領域における実践とその魅力(公認心理師・臨床心理士 山川 祐介):学校現場での心理支援の実際、子どもたちの成長をサポートする喜びなどを語る。
大学の学生相談室で働く公認心理師(公認心理師・臨床心理士 小川 亜希子):大学生の抱える悩み、相談室での支援活動、学生たちの成長をサポートする喜びなどを語る。
いつか出会う誰かのために何ができるだろうか(公認心理師 岨中 庸子):様々な経験を通じて得た学び、心理職としての使命感などを語る。
スクールカウンセラーの役割・魅力(公認心理師・スクールカウンセラー 栗本 淳子):スクールカウンセラーの仕事内容、子どもたちとの関わり方、保護者や教員との連携などを語る。
公認心理師という生き方を考えてみた(臨床スキル研究所 公認心理師 武藤 有佑):公認心理師としてのキャリアパス、自己成長の重要性などを語る。
公認心理師として働く(公認心理師・臨床心理士・キャリアコンサルタント 室屋 賢士):キャリアコンサルタントとしての経験、心理学の知識を活かしたキャリア支援などを語る。
スクールカウンセラーの仕事(公認心理師・臨床心理士 岡田(上杉)寿之):スクールカウンセラーとしての仕事のやりがい、子どもたちの成長をサポートする喜びなどを語る。
新人の公認心理師が感じた心理職の魅力(公認心理師 松田 祐輝):新人心理師としての戸惑い、成長、心理職の魅力などを語る。
心理職は食っていけない?(精神科単科病院勤務・公認心理師・臨床心理士 Y):精神科病院での仕事内容、心理職としての苦労、やりがいなどを語る。
もし、未来が見えていないとしたら…そんな、あなたへ(精神科クリニック勤務・公認心理師 D):精神科クリニックでの仕事内容、患者さんとの関わり方、心理職としての使命感などを語る。
公認心理師を目指すあなたへ(公認心理師 A):公認心理師を目指す人へのメッセージ、資格取得のためのアドバイスなどを語る。
公認心理師の発達支援(公認心理師 B):発達支援の現場での仕事内容、子どもたちの成長をサポートする喜びなどを語る。
公認心理師の魅力(公認心理師 C):公認心理師としての仕事の魅力、やりがい、将来展望などを語る。
o第3章 独立独歩の心理職の仕事(インタビュー記事):独立して活躍する心理職のインタビュー記事を掲載する。
「カウンセリング・ルーム輝(かがやき)」代表 古宮 昇 先生:カウンセリングルームの経営、クライアントとの関わり方、独立して働くことのメリット、デメリットなどを語る。
司法・矯正領域 A 先生:司法・矯正領域での仕事内容、犯罪者の心理、更生支援などについて語る。
フリーランスカウンセラー 日並 昭夫 先生:フリーランスカウンセラーとしての働き方、クライアントの獲得方法、自己管理の重要性などを語る。
•第3部 公認心理師養成大学院・臨床心理士指定大学院への道
o第1章 臨床心理士指定大学院受験総論:大学院受験の概要、必要な準備、受験対策などを解説する。
o第2章 研究計画等書類作成・面接対策各論:研究計画書の作成方法、面接での注意点などを具体的に解説する。
o第3章 心理学の勉強方法:心理学の勉強方法、おすすめの参考書などを紹介する。
o第4章 英語の勉強方法:大学院受験に必要な英語力、英語の勉強方法などを紹介する。
o第5章 公認心理師試験に合格するための勉強法5ヵ条:公認心理師試験の概要、合格するための勉強法などを解説する。
•公認心理師試験 出題分野別 参考文献一覧:公認心理師試験の出題分野別に、おすすめの参考文献を紹介する。
本書では、大学院とは何か、大学院に行くとはどういうことか、大学院資格の臨床心理士とは何か、後発の公認心理師とは何か、養成大学院とは何か、といった基本的な疑問に答えるとともに、心理職者の声や独立独歩の心理職へのインタビューを通じて、心理職のリアルな姿を伝えています。
特に、第2部第3章の独立独歩の心理職の仕事は、これまで多くの方から反響をいただいています。開業の心理職や刑務所で働く心理士の声を聞ける機会は滅多にありません。現代社会で生き抜くとはどういうことか、リアルな姿を知ることができます。
また、第3部では、養成大学院受験のための勉強方法を総論、各論で解説し、公認心理師試験の勉強法も紹介しています。
心理職は、人々の心の健康をサポートする仕事で、皆さん「やりがいのある仕事」だと言います。しかし、その道は決して平坦ではありません。資格取得のための勉強、大学院での研究活動、現場での実践……など多くの困難を乗り越えなければなりません。時には、クライアントの苦しみに寄り添い、自分自身の心が疲弊してしまうこともあります。私も数名スーパーヴァイズをしています。
しかし、困難を乗り越えた先には、自分の知識や技術が、誰かの役に立ち、心の支えになっているという実感は何物にも代えがたい喜びだと言ってくれる人も、京都コムニタスのOBにもたくさんいます。「クライアントとともに生きた10年でした」と最近OBが「引っ越したんですね」と訪ねてきてくれ、その時に聞いた言葉です。その人は生きている限りこの仕事をするということでした。私は、この本を通じて、心理職のそういった面も伝えたいと思って書きました。一人でも多くの人が、心理職の世界に足を踏み入れ、人々の心の健康をサポートし、心理職は、社会にとって不可欠な存在であり、彼らの活躍が、より良い社会の実現に繋がることを信じています。
おわりに
心理職大全は、始まりに過ぎず、心理職の世界は、常に変化し続けている。公認心理師の登場によって、日本の心理職もこれから大きく変わると思います。AI技術の進化、グローバル化の進展、社会構造の変化……まだ私にも想像がつかないことがたくさんあり、変化に対応していく能力の習得が求められます。
京都コムニタスは、今後も、心理職の最新情報を収集し、発信していきます。心理職を目指す人々が大学院に入って学び、その後資格を得て、食べていけるようになるまでの支援を続けていきたいと考えています。
心理職大全のご購入はこちらをご覧ください