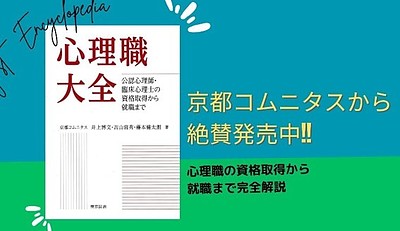主治の医師
公認心理師試験が近くなってきました。私たちも緊張してきましたが、受験をする人はかなり緊張が高まってきていると思います。よくお問い合わせいただくのは、残り期間の勉強方法です。ここから大切になるのは、事例問題も含めて、重要キーワードと、そこを足がかりに他分野と連動させていくことが良いのではないかと考えています。
今回は児童相談所を取り上げます。
児童相談所は、ブループリントでは「23 公認心理師に関係する制度」の小項目にでます。少ないですが、関連項目はたくさんあります。「司法・犯罪分野に関する法律・制度」にももちろん関連します。
北海道試験の問55
児童福祉法で定めている児童福祉施設として、正しいものを2つ選べ。
① 少年院
② 乳児院
③ 教育相談所
④ 児童相談所
⑤ 母子生活支援施設
正答は②と⑤です。私は児童相談所が入ると思ってしまいましたが、公認心理師過去問詳解 2018年12月16日試験完全解説版によれば、児童相談所は児童福祉施設には含まれないとのことです。よくできた問題です。要注意です。その他、ここでは割愛しますが、北海道試験では児童相談所に触れた問題がたくさんありました。
児童相談所は児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関です。児童福祉法は社会福祉六法であり、社会福祉六法生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の総称です。
児童福祉法は、
第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第二条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
以下、長くなりますが、児童福祉法が定める児童相談所に関する記述を引用します。重要ワードには【】を入れます。
(児童相談所の設置及び業務)
第十二条 【都道府県】は、児童相談所を設置しなければならない。
2 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに【障害者自立支援法】 (平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項 に規定する業務を行うものとする。
3 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
4 児童相談所長は、その管轄区域内の【社会福祉法】に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
(児童相談所の組織)
第十二条の二 児童相談所には、所長及び所員を置く。
2 所長は、【都道府県知事の監督】を受け、所務を掌理する。
3 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
4 児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
(児童相談所の所長等)
第十二条の三 児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
2 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
【一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三 社会福祉士
四 児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの】
3 所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
4 判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
5 相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
(児童の一時保護施設)
第十二条の四 児童相談所には、必要に応じ、児童を【一時保護】する施設を設けなければならない。
(命令への委任)
第十二条の五 この法律で定めるもののほか、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
(保健所の業務等)
第十二条の六 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
2 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。
児童相談所について言及する法律として、「児童虐待の防止等に関する法律」があります。その第6条(児童虐待に係る通告)において、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない」とあります。
また、同条第3項、「刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない」とあり、通告することが優先されます。
このあたりは公認心理師の守秘義務にも参考になりそうです。
第8条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第6条第1項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。
1児童福祉法第25条の7第1項第1号 若しくは第2項第1号 又は第25五条の8第1号の規定により当該児童を児童相談所に送致すること。
2当該児童のうち次条第1項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第9条第1項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第33条第1項 若しくは第2項の規定による一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知すること。
2 児童相談所が第6条第1項の規定による通告又は児童福祉法第25条の7第1項第1号 若しくは第2項第1号又は第25条の8第1号 の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ同法第33条第1項の規定による一時保護を行うものとする。
3 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれを行うものとする。
以上、児童相談所は主に前回の児童福祉法と今回の児童虐待防止法に言及があります。
厚労省の児童相談所の運営方針も参照ください。
****************************
公式ホームページ
大学院・大学編入受験専門塾 京都コムニタス
入塾説明会情報
公認心理師国家資格対策講座
公認心理師 全国模擬試験
ご質問・お問い合わせはこちら
自分磨きのための仏教
龍谷ミュージアム
REBT(論理療法)を学びたい方はこちら
日本人生哲学感情心理学会の理事長を務める心理学者
日本人生哲学感情心理学会