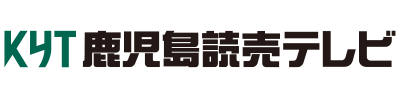目線を変えよう―考えかたと視点を変えなければなにも変わらないよ―Ⅰ
というのは、会社の主要分野(会計経理は特に)にコンピュータを取り入れるか否かは単に社内体制の問題ではなく、会社が生き残れるか否かの対外的な死活問題だからです。
「私が元気なうちは、今まで通り手書きの帳簿でゆっくりと私にやらせて欲しい。」
というのは残念ながら叙情的我儘というしかありません。
息子が背負った会社は今やそんなに生やさしい状況にはないのです。
常にギリギリの競争の中で生き残れるかどうかの瀬戸際にあります。
ましてや、コンピュータ導入すら遅れた状態で、外部の様々な勢力とまともに戦っていくことなど考えられないのです。
さて、今までのいろいろなケースを見ていると、こういうとき、決裁権を手元に残すためには旧勢力はありとあらゆることを持ち出します。
現社長(息子)の未熟さへの非難、世間との比較、自分たちの苦労の歴史、義理人情、ありとあらゆる理屈をもって手放さないことを正当化しようとします。
ここで大抵の後継経営者は、嫌気がさして諦めてしまうかめげてしまうのです。
元々彼らには「経理に関してあまり自信がない。」という事情もあるにはありますが。
従がって、後継経営者にも努力しなければならない(会計や財務の勉強をするという)条件もあることはあるのです。
「経理はお袋に任せてたからなあ。」
では済まないのです。
つづく