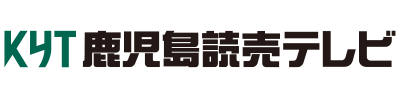2つの結婚披露宴―悪いことしちゃったなあ・・・遠い昔のほろ苦き思ひで―Ⅱ(おしまい)
このコラムには祖母の話が度々出てきます。
私が小さいころ祖母に育てられたお婆ちゃん子ということもあるのだが、明治生まれの祖母の人格がとても魅力的なことや、その言動に何とも言えない味わい深さがあるからです。
そういう意味で、私にはもう一人忘れることのできない年配の女性がいます。
確か、祖母とあまり年が変わらないくらいの人だったと記憶しています。
残念ながら、彼女の最晩年にはもう会うこともなく、亡くなったことは後から聞いただけでした。
そのK女史は、街中でほんの1坪くらいの小さな化粧品店を開いていました。
化粧品のほかに自分で仕入れてきたちょっとした婦人服や小物なども店先に置いていたのです。
いわゆるモダンな婆さんで、昔の女子大出という鹿児島の片田舎の街では貴重な経歴の持ち主でもありました。(何という女子大だったか… どうしても思い出せない。)
このお婆ちゃんと私はどういうきっかけだったか仲良しで、子供のころから時々遊びに行っていたのです。
遊びに行った、といっても店先に座って、お婆ちゃんの東京時代など昔話を聞くくらいのことでした。
しかしながら、その話法は標準語と鹿児島弁が瞬時に入れ替わるという、器用というか不思議というかとても面白い語り口で、話題も様々で幅広かったことを覚えています。
このK女史の店は徹底的に暇だったので、いつ行っても大歓迎であった。彼女は店先のコンセントで電気ポットのお湯を沸かし、必ず紅茶をわざわざいれてくれました。
そしてどういう訳か、いつも都会土産らしいおしゃれなお菓子がストックしてあって、それを「今日はうれしいからこれを食べましょ。」と出してくれたのです。
モダンな婆さんと言ったのは、店の奥からは常にモーツアルトの調べが流れており、話題も芸術系の話などが多かったからです。
元々店は暇だったのだが、商売っ気もあまりなかったようでした。
ある日、たまたま私の母が見ていたとき、店先にあった婦人物のブラウスを欲しがる客に
「貴女は色が黒いからこれは似合わないわよ。」
と売り渋ったことがあったそうで、これには母も驚いていました。
自分の主義主張は随分とはっきりしていたようでした。
つづく