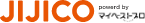旅行前に必ずやるべき防犯対策
- カテゴリ:
- くらし
旅行の予定をカレンダーに記すのは危険

ゴールデンウィークの連休を利用して、旅行を計画している人も少なくないと思いますが、おでかけの際は戸締りをお忘れなく。といっても、旅行などで長期間にわたって自宅を留守にする場合、防犯対策はどうしていますか?一般的には、「雨戸を閉めて戸締りをしっかりとする」「新聞や牛乳、そのほか宅配物を止める」など、留守をさとられない手法が良く知られています。しかし、それだけでは不十分です。
旅行の日程をカレンダーに書き込んではいませんか?また、冷蔵庫の中を整理せずに出かけていませんか?
泥棒が空き巣に入る理由は、盗みだけではありません。実際、このようなケースがありました。侵入に成功した泥棒が目にしたのは、赤マルのついたカレンダー。住人の帰宅日がわかり、ゆとりが生まれた泥棒が次に向かったのは冷蔵庫。そうです、「腹ごしらえ」です。この泥棒は、住人が帰宅するまでの間、食事をしながらのんびり物色と品定めをして、住人が帰宅する前日に逃げたそうです。帰宅した住人は空き巣被害に気づき、数日間、泥棒が滞在していたことを知って不安と恐怖が倍増し、引越しをしました。このように、空き巣被害は財産だけでなく、自身の心も守らなければなりません。
泥棒が嫌う3つの防犯対策
泥棒が最も嫌うのは、「捕まる」ということです。つまり「この家に侵入したら捕まってしまう」「逃げることが容易ではない」といった想像をさせることが重要です。そして、忘れてはならないのが、泥棒も私たちと同じ「人」であるということ。神経を逆なでする過剰な対策は、被害を拡大(放火など)させることもしばしば見受けられます。
ここで、有効な防犯対策をいくつかご紹介します。
(1)近所に留守であることを知らせる
監視の目を増やす効果があります。定番ではありますが、留守の間、ご近所さんに気にかけてもらいましょう。
(2)新聞や牛乳、ほか宅配物を止めずに親しい近所にお裾分け
監視の目を増やし、不在をさとられない効果(不在がさとられても、いつ取りに来るかわからないという牽制になります)があります。留守の間も環境を変化させないことが大切です。
(3)旅行前には、必ず整理整頓を
屋外では、脚立や工具などを屋内に入れて、エアコンの室外機や給湯設備の清掃、落ち葉などを片付けて外観をキレイにします。ゴミ箱(ストッカーほか)、ダンボールや新聞・雑誌類も屋内に収納しましょう。侵入するための道具を収納し、侵入した形跡(証拠)が残るようにすることが牽制につながります。
また、屋内では、掃除をして貴重品、個人情報記載物の保管状況を確認します。侵入された場合の被害拡大を防ぐ効果があります。これは、泥棒が最も嫌う「捕まる」きっかけを作り出す対策です。一般的には、道具(タイマー付き照明、転送電話、貸金庫、ホームセキュリティなど)を活用した方法に目が行きがちですが、防犯カメラは110番通報してくれないため即時性はありません。泥棒は姿を撮影されるより、ごまかせない証拠(指紋や足跡など)を残すことが嫌う傾向にあります。
コミュニティーの形成と整理整頓は万能な対策
このように、コミュニティーの形成と整理整頓は、泥棒に狙わせない、近づかせない(泥棒が嫌う)対策であり、最も効果を発揮する対策です。そして、犯罪(空き巣や放火など)の抑止だけではなく、災害時にも力を発揮するなど、そのほかにも効果が見込めます。
犯罪を取り締まる警察では「検挙に勝る防犯なし」という合言葉のもと、私たちの安全と安心を守るため職務にあたっているそうです。私たちひとりひとりも被害に遭わないために、コミュニティーの大切さを見直さなければならないのではないでしょうか。

関連するその他の記事
コウモリの生態とは?被害状況や効果的な予防・駆除方法について解説

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家
イタチの生態とは?被害状況や効果的な予防・駆除方法について解説

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家
ハクビシンの被害、増加の一途|対策はどうすべき?駆除方法を解説

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家
トコジラミを予防するには?最新の駆除方法で快適な睡眠を取り戻そう

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家