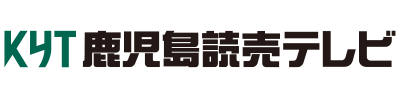悲しき旋律「ブーベの恋人」―またもや少年時代のトホホな思い出―
煙草の吸殻を見てふと思い出したこと
社内喫煙禁止のわが社では、玄関横の屋根はあるけど半分外(そと)、みたいなスペースで喫煙組は煙草を吸っている。(私は吸いません。)私自身めったにその場所に行くことはないのだが、先日、そこにおいてあるスタンド式灰皿の中の吸い殻を見ていてふと思い出した歌謡曲がある。
昭和49年に大ヒットした「うそ」という曲である。「中条きよし」という歌手が歌っていた。当時、「中条きよし」は歌手として人気もあり、結構活躍していたが、その後、本格的に俳優に転向して、「新・必殺仕事人」にも出演していた。歌手としての彼よりも「仕事人、三味線屋の勇次」の方を覚えている人が多いのかも知れない。(なんと、今は国会議員ということで驚いた!)
さて、煙草の吸殻を見ていて何故「中条きよし」の「うそ」を思い出したかというと、その曲の歌詞が次のようなものだったからである。
うそ 中条きよし
折れた煙草の 吸いがらで
あなたの嘘が わかるのよ
誰かいい女(ひと) 出来たのね 出来たのね
あー 半年あまりの 恋なのに
あー エプロン姿が よく似合う
爪もそめずに いてくれと
女があとから 泣けるよな
哀しい嘘の つける人
作詞:山口洋子 作曲:平尾昌晃
リリース: 1974年1月25日
リリースが1974年ということは昭和49年である。まあまだ、昭和ど真ん中と言ってもいいくらいの時代だ。
歌詞からすると、浮気をされた女性が、男の部屋(おそらく)の煙草の吸殻からそれを察し、めそめそしているという風情を表現しているようである。あの時代、女性にこんなマインドがまだ残っていたんだ、と驚かされる。
いや、いくらあの頃でも、そんなものはとっくに無くなっていたから、あえてこんな歌にしたのかも知れない、とも思う。ただ、作詞が「山口洋子」という女性なので、あながち虚構の世界とばかりは言えないのだろうか。いずれにしても、令和となった現在の世相からはかなり遠い意識のような気がする。
わが社の喫煙スペース
煙草の吸殻を見てさらに思い出したこと
ところで、「煙草の吸殻」といえば、思い出すことが一つある。あれはまだ学生の頃だったと思うから、22,3歳くらいだっただろうか。友達何人かと、Ⅿの車に同乗していた。Ⅿは中学時代からの同級生である。
当時、学生の身分で車を持っていたのは、Ⅿともう一人くらいしかいなかった。とにかく、その車の中でワイワイ騒ぎながら、まだ喫煙していた私たちは煙草に火をつけて、車載の灰皿を使おうと、閉じていた灰皿を引き出した。
すると、中には何本かの吸い殻が残っていたが、そのうちの数本に我々は目を奪われた。なんと、その吸い口に鮮やかな口紅の紅色が付着していたのである。
「おっ!な、なんだ、これはっ!」友人の一人が声を上げた。すると、その様子に気づいた運転中のⅯの顔色が変わった。そして「灰皿を閉じろ!閉じろ!その灰皿は使うなっ!」と、すごい勢いで慌てふためいたのである。
「なんだよ。なんだよ。なんで使っちゃダメなんだよ。」と、我々はすでに薄々なにかを察しながらも、ニヤニヤとからかいモードに入り始めていた。「いいから灰皿閉めろよ!」と、Ⅿはますますいきり立つ。「ふーん・・・」と我々。
すると、誰からともなく、次の歌が口をついて出始めたのである。
折れた煙草の吸殻でぇ~♪
あなたの嘘がわかるのよぉ~♪
中条きよしのヒット曲「うそ」の出だしの歌詞である。
Ⅿ以外、二人か三人乗っていたと思うが、ほぼみんなで合唱みたいになった。動揺したのか、わざとなのか、Ⅿが2,3回急ハンドルを切る。
「おい、おい、あぶねーな。まあ、落ち着け落ち着け。で、この彼女とはどうなったわけ? そんな風にこだわるということは、吸い殻だけは思い出にとっておきたいの?」
「うるせぇな。ほっとけ。とにかくその灰皿は使うなっ!」
・・・我々の推理は図星だったようで、Ⅿはこのとき多くを語らなかったが、どうやらこの吸殻を残したドライブのあと、その女の子には振られたらしい。
にもかかわらず、その彼女の吸殻を捨てられない、という男心。まあ、ここだけ聞けば、気持ち悪いとか、なんて情けない、ということになるのだろうか。
しかし、あの頃、同世代だった私たちは、Ⅿの傷心が妙に可笑しくて、共感するところもあった。それに、ちょっぴり同情なども入り交じって、当時のヒット曲だったあの歌とともに心に刻まれたのである。とはいえ、このエピソード、たまたま私は思い出したが、Ⅿも同乗していたほかの友人たちも、たぶん覚えてもいないだろうな。
昔流行った歌と、その頃体験したほかの思い出がシンクロする、というのは、このことに限らずおそらくよくある話だろう。中条きよしの「うそ」、懐メロ番組でもなければ、もう聞く機会などほとんどないかも知れない。ふと目にした「吸い殻」をきっかけに、遠い記憶からよみがえった、他愛もないお話でした。
まだ若かった頃、真ん中でサングラスかけて煙草を持っているのが私です。