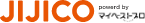五月病をどう克服するか?長引かせないためにも気をつけたいこと
- カテゴリ:
- 医療・病院

環境の変化は人にストレスを与える
4月から新年度ということもあり、色々な新しい変化を感じている人も多いのではないでしょうか。
別れがあったり出会いがあったり、新しい挑戦や人間関係が始まった人も多いと思います。
しかし3~5月というのは、一年で最も自殺者が多いのです。
新しい変化というのは、よいこともあるかもしれませんが、人間にとって”変化”というのは、適応していくためのストレスを感じさせます。
知らず知らずでも、変化にストレスを感じ続けてからのゴールデンウィークという長期連休にホッとして、ゴールデンウィーク明けを「社会復帰」なんていうくらい会社や学校に行くしんどさを感じている人も多いのではないでしょうか?
そもそも五月病ってなに?
五月病という名称はよく聞きますが、五月病とはどんな病気なのでしょう。
実は「五月病」という病気はなく、先に述べたように、新しい環境や人間関係の変化などをストレスに感じて、それに起因する精神的な症状を総称して「五月病」と呼んでいるのです。
「サザエさん症候群」なんてことばがあるくらい、休みの後って辛いと感じやすいですよね。
そんな5月あたりに発症しやすいからそう呼ばれるだけなのです。
どんな症状がサイン?
朝起きて、ベッドから出られないとか、学校や会社の入り口から入れないといった人は、心療内科を受診しましょう。
基本的には早めに身体的な”サインに気づく”ということが大切です。
□ほとんど毎日が憂うつで仕方ない
□ほとんど毎日が楽しくない、楽しかったことも楽しめない
□食欲に異常がある
□眠れない、一日中眠い
□早朝に目が覚めるようになる
□集中力に欠けるようになり、ミスが増える
□微熱、だるさや疲労感が続く
□身だしなみや部屋の雑然さがどうでもよくなる
このようなことが2週間以上続くようでしたら、身体にストレスの症状が出始めています。
ストレスには早目の対処を
毎日、気を張ったストレス状態が続くと身体に影響を及ぼし始めます。
大体のネガティブな事象について言えることですが、とても大切なのが…。
- 早目の対処
- まめな対処
そして、その対処として有効な例として挙げるのであれば…。
- 心理カウンセリング
- 聴き上手な身近な人に話す
- 誰かと自然にふれる
です。
とにかく新しい環境であったとしても孤独にならないこと。
「ツナミ」という言葉が世界共通語になっているように「カロウシ」も世界的に通じる言葉になっています。
それぐらい、日本人はギリギリまで我慢し易い民族とも言えます。
そうではなく”未病段階”に早めに対処をすることで、元気に動くほうが効率的なのです。
独自手法で短期解決をもたらす心理カウンセラー
青柳雅也さん(カウンセリングルーム アンフィニ)
関連するその他の記事
コロナワクチンの副反応防止に鍼灸治療は有効かも!!副反応の長期化を防ぐことは可能なのか!?

清野充典さん
東洋医学と西洋医学の融合を目指す鍼灸師・柔道整復師
授乳中に冷たい物を飲食すると赤ちゃんに影響が?授乳中のお母さんが気をつけるべき生活習慣について

清野充典さん
東洋医学と西洋医学の融合を目指す鍼灸師・柔道整復師
産後の体調を良くする方法は?産婦の日常生活開始時期が大きく関与する!?

清野充典さん
東洋医学と西洋医学の融合を目指す鍼灸師・柔道整復師
柱の角に足の指を引っ掛けた後痛みが引かない!! その腫れは骨折かも!?

清野充典さん
東洋医学と西洋医学の融合を目指す鍼灸師・柔道整復師