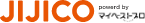「本当にそれはマナーなのか?」正しいマナーを見抜く方法
- カテゴリ:
- くらし

マナーに振り回されないためには正しいマナーを見抜く力が必要
社会人にとって最初に必要なことは、正しいビジネスマナーを身に付けることです。グローバル時代と言われて久しい昨今ですが、日本人がその性質をベースに長く育んできたマナーは確実に在り続けます。もちろん普遍的なマナーがある一方で、世の中の移り変わりと共に変遷していくマナーもあります。中には「本当にそれはマナーなの?」と言いたくなるこじつけマナーがあることも事実です。そこで今回は、正しいマナーとは何か?そして、正しいマナーを見抜く方法について解説します。
正しいマナー「ハンコは斜めではなくまっすぐに押す」
数か月前、「ハンコを押す時は、上司にお辞儀をするように斜めに押すのがマナー」という投稿が話題になりました。
これに対する大半の意見は「ナンセンス」というもの。同感です。上下関係がことさら厳しい会社はありますし、上司に対して度を過ぎた敬意の表し方をする会社もあります。そのような環境で、ハンコの角度がさも重要なマナーであるかのように根付いたのでしょう。ビジネスマナーは周囲への思いやりであり、円滑に仕事を進めるための仕事のやり方です。それを履き違えると、このようなこじつけマナーになってしまいます。ハンコは、切手を貼る時と同様、まっすぐに押すのがマナーです。人は本能的に、歪んでいたり斜めになったりしているものを気持ち悪いと感じます。見た目の印象を考えれば、「まっすぐ」が正解なのです。
正しいマナーには汎用性がある
マナーとして正しいかどうか、重視するべきか否かを判断するには、「汎用性があるかどうか」がひとつの目安になります。そのマナーは、広く浸透しているのかどうか。みんなが当たり前に取り入れているのかどうかを考えてみて下さい。
先のハンコの例は残念ながら、とても少数派と言えます。一方で例えば、24時間いつでも「おはようございます」と挨拶するマナーがあります。これは芸能・放送業界に加え、飲食・宿泊業界にも拡がっています。つまり「おはようございます」の挨拶は、特定の業界で広く使われていることから、「汎用性のあるマナー」と言えるのです。
時代と共に変化して「汎用的」に成長するマナーもある
さて冒頭で述べたように、マナーにはいつの時代も変わらない普遍的なものと、時代に寄り添う形で変わっていくものがあります。
例えば、挨拶や言葉使いは普遍的なマナーですが、通信に関するマナーは時代と共に変わるマナーの代表ではないでしょうか。数年前には、会社の固定電話、PCメール、FAXの使用を前提としたマナーでした。しかし現在では、それらのツールに代わり個人のスマホやタブレットによるメッセージのやり取りが一般的です。
マナーという観点からはカジュアルすぎるように感じられても、「速い」「簡便」という理由からこれが主流になれば、それに沿ったマナーが生まれます。さらにはそのマナーが広まり一般的になるにつれ、「汎用的」なマナーに成長していくのです。
必要なのは、ビジネスに直結したマナー
正しいマナーは、「今汎用的なもの」と「汎用的になるであろうもの」の2つです。多くの人が知っていて取り入れているマナーは、それだけ広範囲に定着しているということ。小さな狭い世界だけで通用するマナーとは違います。
ビジネスマナーは、一緒に仕事をする人への思いやりですが、その目的はひとつ。ビジネスを円滑に動かし、利益を出すという効果につながることです。見当はずれの丁寧さばかりがクローズアップされがちなマナーですが、真にビジネスに役立つマナーを見定めて、身に付けることを心がけましょう。
関連するその他の記事
コウモリの生態とは?被害状況や効果的な予防・駆除方法について解説

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家
イタチの生態とは?被害状況や効果的な予防・駆除方法について解説

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家
ハクビシンの被害、増加の一途|対策はどうすべき?駆除方法を解説

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家
トコジラミを予防するには?最新の駆除方法で快適な睡眠を取り戻そう

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家