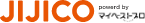第一印象の重要性。第一印象はたった7秒で決まる?
- カテゴリ:
- くらし

たった7秒の関門を突破するには「第一印象」
ノンバーバルコミュニケーションの観点から書かれた竹内一郎氏の著作、「人は見た目が9割」がベストセラーになったのは約10年前のことです。中身こそが大事という文化が根差していた日本で、このセンセーショナルなタイトルは話題になりました。そしてこれを機に、中身同様に見た目も大事だという事実が注目され今に至っています。
7月2日付けの朝日新聞朝刊オピニオン欄、見た目に関するアンケート結果によると、人を見た目で判断することがあるか?という問いに対し、「よくある」「たまにある」と答えた人は全体の88%。今の社会では人は見た目で判断されていると思うか?に対し、「強く思う」「ある程度思う」と答えた人は全体の93%です。ほとんどの人が見た目で判断し、判断されていると思っていることがわかります。
実際、人は初めて会う人を見た目で判断しますが、それはたった7秒で決まると言われています。つまり第一印象が決まるこの関門を突破できなければ、中身を知ってもらう次のチャンスはないという事です。もちろん中身は大事ですが、その前に第一印象で相手に良い印象を与えることを考えなくてはいけません。
ステップ1. 自分に似合うものを知る
第一印象で良い印象を与えるには、見た目を良くすることです。これは生まれつきの美醜のことではありません。もちろん素材が美しい人はそれだけアドバンテージがありますが、それに安心して努力をしない人よりも、平凡な容姿でも日々努力している人のほうが好印象を与えられます。
見た目を良くする努力は、社会人に必要な努力です。具体的には、清潔感を保つ、似合う色の洋服を着る、サイズの合う洋服を着る、似合う形の洋服を着る、似合う形のメガネ・アクセサリーを身に付ける、似合う髪型を維持する、髪色を均一にする、カバンや靴など手入れの行き届いた小物を持つ等です。
まずは自分の外見と向き合い、似合うものを知るところから始めましょう。
ステップ2. 第一印象を戦略的に作りこむ
似合うものを身に付けて見た目を良くするのが第一段階だとすると、次はより戦略的に第一印象を制することに取り組みましょう。初めての人に会う時には、どのようなシチュエーションで会うのか、又その時相手が自分に求めるイメージはどのようなものかを考えることが大事です。
例えばつい先ほど辞職した女性大臣、リボンのついたスーツやミニスカートに網タイツといった洋服選びは、自身のポストに求められるイメージとはかけ離れたものでした。見た目のイメージの悪さが、評価の悪さにもつながった例のひとつです。
戦略的なイメージ作りとは、自分がどのような場に臨み、どのようなポジションかを認識した上で、自分が求められるイメージを見た目に反映させることです。
その際は、笑顔、姿勢、話し方にも注意しましょう。笑顔は自分が思うより2割増しの笑顔で、立ち姿座り姿も印象に大きく影響します。常に姿勢良くいましょう。話し方は、社会人としての成熟度を表すことを忘れずに。正しい言葉使いでゆっくりはっきり話すようにしましょう。
SNSの発展に伴い、個人が自由自在に自分の情報を発信できる時代です。その環境で、見た目は言葉を連ねて説明するよりもはるかに素早く効果的に自分の魅力を伝えてくれます。第一印象を良くすることが、これまで以上にビジネスにもプライベートにも大きく貢献することは言うまでもありません。
今までは「好きだから着る」だった人は「似合うものを着る」へ、さらには「どう見せたいか考えて着る」にシフトしてみてはいかがでしょうか。
関連するその他の記事
コウモリの生態とは?被害状況や効果的な予防・駆除方法について解説

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家
イタチの生態とは?被害状況や効果的な予防・駆除方法について解説

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家
ハクビシンの被害、増加の一途|対策はどうすべき?駆除方法を解説

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家
トコジラミを予防するには?最新の駆除方法で快適な睡眠を取り戻そう

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家