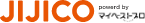日銀追加緩和で日本経済はどうなる?バブル再びになりつつあるのか?
日銀が追加の金融緩和策を決定

7月29日まで日本銀行の金融政策決定会合が開催されましたが、英国のEU離脱などで海外経済の不透明感が高まりつつあることなどから、ETF(上場投資信託)の年間の購入額をこれまでの約3.3兆円から6兆円に引き上げることや、海外展開を行っている企業に対するドル調達の円滑化を行うなど追加の金融緩和策を決定しました。
しかし、この追加の金融緩和策の中には一部で期待されていたヘリコプターマネーの導入は含まれておらず、また現在年間80兆円のペースで行っている国債購入による市場への資金供給(マネタリーベース)やJリートの買い入れ方針、マイナス金利の金利幅に変更はありませんでした。
そのためETF購入拡大で株価こそ上昇したものの、市場の期待を裏切った形となってしまい、リスク敬遠の流れから円高が進みました。
数字上からはバブル懸念は行き過ぎと思われる
今回とくにJリートの買い入れ方針に変更がなかったことなどから、「不動産はバブル期の状態にあるのではないか」という懸念の声を聞きましたが、これは日本銀行がJリートの保有比率の上限を発行残高の5%としているためだと思われます。
現在のJリートの平均分配金利回りは約3.49%(2016年8月10日時点)で、国債利回りとのスプレッド(金利上乗せ幅)は目安となる3%超を保っています。
すでにある程度の高値圏にきているとは思いますが、マイナス金利の環境下で利回りを得られる数少ない手段として、今のところはJリートの魅力は保てているものと考えられます。
また、株式市場に関しては、バブル期には日経平均のPER(株価収益率)は80倍を超えていることもありましたが、現在は13.95倍(2016年8月9日時点、予想値)となっていて割安感すら漂うような水準にとどまっています。
このような数字から「バブル期の状態にあるのでは」というような声は、少々行き過ぎた懸念であると思います。
金融緩和は時間稼ぎに過ぎない
しかし、金融緩和というのは需要の先食いを促す政策でもあります。
日銀による市場への大量の資金供給によって溢れたマネーは、本来ならばもっと先に発生したであろう需要を前倒しで発生させているのです。
景気が低迷しているタイミングで金融緩和を行うことはけっして間違いではありませんが、これは時間稼ぎのような政策であり、本来ならば時間を稼いでいる間に潜在的な経済成長率を引き上げるような政策(成長戦略)を政府が行わなければならないのです。
ところが今は日本銀行による金融緩和と、財政出動(いわゆるバラマキ政策)ばかりに頼っていて、政府は効果的な成長戦略を打ち出せていません。
第二次安倍政権の当初のアベノミクスの3本の矢とは「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」でしたが、前者2つの政策ばかりに頼っていて、肝心の潜在成長率を引き上げるような成長戦略の実施は不十分な状態が続いています。
そのため先月発表されたIMF(国際通貨基金)の世界経済見通しでは、日本は2016年の成長見通しを0.2%下方修正され0.3%の成長見通しとされるなど、年々その成長見通しは下がっていく一方です。
日本銀行の総括的な検証の評価に注目
金融緩和と財政出動で時間稼ぎだけをしておいて、効果的な成長戦略を行えないままの状態がこのまま続いてしまうと、その先にあるのは先食いをして少なくなってしまった需要と、国の莫大な借金、それに日本銀行のバランスシートの悪化が残ってしまいます。
日本銀行は次回9月の金融政策決定会合までに「総括的な検証」を行うと述べており、過去の金融政策の効果についての確認が行われることになっています。
そこでどのような評価が行われるのかについて、ぜひ注目しておきましょう。
関連するその他の記事
副業のためのサイト売買という選択肢

中島優太さん
サイト売買に特化したM&Aアドバイザー
空き家が増える時代の賢い不動産投資信託投資術「REIT」とは?
中山聡さん
プロもうなずく不動産のプロ
不動産融資バブル期上回る バブル崩壊は再び起きるのか?
森田伸幸さん
個人向け不動産コンサルティングのプロ
東証・大証統合による株価への影響
山中伸枝さん
年金・資産運用に強い独立系ファイナンシャルプランナー