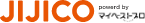全国各地で展示会が活況。ガラスアートの魅力とは?
- カテゴリ:
- くらし
様々なデザインに対応可能なガラスが魅力を創出

ガラスは個体のような見た目をしていますが、性質としては液体に近いという説もあり、加工により様々な姿を見せてくれます。
溶かす、削る、磨くなどの樹脂では不可能な加工も可能なため、自在なデザインに対応出来るのが大きな魅力です。
それにより、作り手の創造性を膨らませることで様々な作品が生まれ、そして多くの人を魅了するガラスアートが生まれるのです。
ガラスアートの代表として「ステンドグラス」「エッチング」の二つを例に、その魅力を紹介したいと思います。
ステンドグラス
教会で使われていることの多い印象があるステンドグラスですが、最近では公共の建物や輸入住宅など、身近な場所でも見るようになりました。
歴史ある建物として名高いノルダム大聖堂のドーム型の天井は直径13m程もあり 花をモチーフにしてつくられたステンドグラスは「バラの窓」と呼ばれています。
北のバラ窓は聖母マリアを中心として、旧約聖書の預言者や王をステンドグラスで描かれています。
歴史の重みを感じるモチーフで作られたステンドグラスは、歴史の重みを感じる幻想的な美しさで、時間を忘れて魅入ってしまう方も多いようです。
ステンドグラスの魅力は、透明感と鮮やかな色でしょう。
そのままで見ても十分美しいのですが、透過した光はキラキラと輝いて神々しいほどです。
昼間の太陽の光、夜の人工の照明、時間や場所で全く違う表情を見せてくれるのも、
ステンドグラスの魅力の一つです。
一般的なステンドグラスは鉛線で囲ったガラスをハンダで繋げるのですが、他にもいくつか手法があります。
・ガラスの表面にエナメル系顔料等を焼き付け着色する絵のようなステンド
教会のステンドグラスなどの顔や服の陰影部分
・ハンマーで厚いガラスを砕きモルタル状の樹脂で繋げる重厚なステンド
砕かれたガラスの断面が独特の光を生み出す。
・他にもステンドグラスを何層にも重ねたり、ガラスで立体的なモチーフを作ったりとアイデア次第で表現の幅が広がります。
ステンドグラス教室などで作品を作って楽しむこともできます。
エッチング
ガラスの表面に砂を吹き付ける「サンドブラスト」加工を重ね 深く立体的に彫ったもの。
平面のガラスに奥行きを作り半立体のような表現を可能とし、幾何学模様から名画まで、どのようなデザインでも再現出来ます。
ガラスの彫刻で頭に浮かぶのは、ルネ・ラリックが手掛けた東京都庭園美術館/旧朝香宮邸ガラス扉の『翼を広げる女性像』が多いかと思います。
このガラスの彫刻はエッチングの技法ではなく型押ガラス製法で作られた大きな作品です。
日本でエッチングガラスが認知されたのは、クルーズトレイン「ななつ星in九州」を手掛けた水戸岡永鋭冶氏の功績も大きいでしょう。
木とガラスを組み合わせた和モダンなインテリアは、どこか懐かしくて新しい飽きのこないデザインです。
JR九州の「或る列車」の扉などにもエッチングガラスが使用されており、その繊細さや透過する影の美しい魅力は多くの人の目に触れています。
素材のガラスの質感や透明感がエッチングすることで更に輝きを増し、扉とは思えない芸術作品のような雰囲気です。
光線や色彩を受けて、透かしてみると浮かび上がるエッチングの美しさはとても魅力的です。
ガラスの美しさをより引き立て、繊細にして華麗で幻想的でドラマチックです。
ガラス工芸は作り方によって色や質感が大きく変わります。
他の素材には無い透明感、光の反射による様々な色彩を楽しんでいただきたいです。
関連するその他の記事
コウモリの生態とは?被害状況や効果的な予防・駆除方法について解説

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家
イタチの生態とは?被害状況や効果的な予防・駆除方法について解説

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家
ハクビシンの被害、増加の一途|対策はどうすべき?駆除方法を解説

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家
トコジラミを予防するには?最新の駆除方法で快適な睡眠を取り戻そう

内田翔さん
快適な暮らしを取り戻す、害獣害虫駆除の専門家