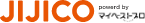所得の低い年金受給者に3万円給付は高齢者優遇のバラマキか?
- カテゴリ:
- お金・保険
公的年金受給者の3割以上が対象

政府は2015年度補正予算案に、所得の低い年金受給者を対象とした一人3万円の給付金を盛り込む方針を固めました。賃金引き上げの恩恵を受けられない年金受給者への対策と、低年金者の家計を支援することによって個人消費を活性化する狙いがあるものとみられます。
対象者は、65歳以上の公的年金受給者約1,100万人と障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者約150万人で、いずれも住民税非課税者であることが要件になるようです。平成25年度末現在、公的年金の実受給権者数は約3,950万人(厚生労働省「平成25年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」)ですから、公的年金の受給権者の3割以上の人々が給付の対象になるということです。
高額な給付金は高齢者優遇?バラマキ?
平成21年には「定額給付金」が、昨年からは消費税率引き上げの影響を考慮して住民税非課税者への「臨時福祉給付金」と子育て世帯への「子育て世帯臨時特例給付金」が導入されました。定額給付金は一人12,000円、臨時福祉給付金は一人6,000円(平成27年度)、子育て世帯臨時特例給付金は子供一人につき3,000円(平成27年度)です。それらと比較した場合、今回の給付金が高額であることがわかります。
現役世代は賃金引き上げの恩恵を受けられなくても、または低所得であってもこの給付金を受給することはできません。そのような給付金に子育て世帯臨時特例給付金の10倍もの額が支給されるのですから、「高齢者優遇」はもちろんのこと、投票率の高い高齢者への給付ということで「選挙対策のバラマキ」との批判が出るのも仕方ないことかもしれません。
一時的ではない政策こそ重要なのでは
厚生労働省の被保護者調査によれば、今年9月時点で生活保護を受けている65歳以上の高齢者世帯は約80万世帯で、生活保護受給世帯のおよそ半数を占めています。また、生活保護を受けていなくても、「下流老人」とも呼ばれる生活が厳しい高齢者が多くいることも事実です。
一方、現役世代にも非正規雇用としての就労が長期間続いたり、育児や介護のために退職せざるを得ないなど、安定した雇用と収入の確保が難しい人も多く存在します。そのような人々は、保険料免除や未納などの期間が長くなり、将来年金受給額が低くなることも予想されます。いわば「下流老人予備軍」です。
給付金で助かる人が多いのも確かでしょうが、給付金はあくまでも一時的に支給されるものであり、その効果も一時的なものです。非正規雇用で働く労働者の処遇改善やワークライフバランスの推進など、長期的な政策により注力することこそが重要であり、そうでなければ低年金の問題も解決されず、今後も「下流老人」が増え続けることになるのではないでしょうか。
関連するその他の記事
主婦の新しい副業!“売れるサイト”を自宅で育てる方法
中島優太さん
サイト売買に特化したM&Aアドバイザー
夢を叶えたいなら、「収入」より「お金の残し方」に目を向けよう

新井一さん
稼ぎ力を引き出す起業支援キャリアカウンセラー
サラリーマン勝ち残り戦略:起業×投資で切り開く新時代の資産形成術

新井一さん
稼ぎ力を引き出す起業支援キャリアカウンセラー
従業員が“お金の不安”を抱えている? ― 福利厚生としての金融教育のすすめ ―

吉井徹さん
法人財務と個人資産の最適化を同時に図るお金のプロ