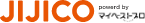青色LEDがもたらしたパラダイムシフト
- カテゴリ:
- ビジネス
白色LEDの開発には青色LEDこそが必要であった

今年のノーベル物理学賞を日本の3人が受賞し、一躍「青色LED」という言葉が一般紙面やお茶の間のニュースを飾りました。おかげで、LEDとは何か、初めて理解した人も多かったのではないでしょうか。
簡単に言えば、LEDとは、光を発する半導体の一種です。光は、様々な色が集合したものですが、半導体であるLEDは、その構成材料に特有の色しか出せません。色の3原色である赤、緑、青のうち、前者2つの色は比較的早く実用化されたのですが、青色LEDの開発は難しく、今回受賞された3人の功績により、1993年にようやく実用化されたのです。
これで3原色が揃い、3つのLEDを組み合わせて白色を出せるようになったことが、今日のLED産業の隆盛を築いた、と思ってしまいがちですが、実はそうではありません。現在のLEDによる白色光は、青色LEDに黄色い蛍光体をかぶせて作られており、これが良質な白色光を出せるようになったことが、現在のLED市場の本当の要因です。これを実現したのが、徳島の日亜化学工業であり、1997年のことでした。すなわち、現在の白色LEDの開発には青色LEDこそが必要であったということなのです。
蛍光灯、白熱灯の代替が可能となり、劇的な変化を引き起こした
この白色LEDが開発されたことにより、それまで蛍光灯、白熱灯の代替が可能となり、その用途分野に劇的な変化が起こりました。一つは、携帯端末やTVに使用される液晶パネルへの応用です。液晶パネルは、裏からバックパネルという照明源で液晶を照らす構造になっていますが、光源として蛍光灯や特殊な照明管が使われていました。白色LEDの実用化により、これを裏面に万遍なく敷き詰めて照らす方式が実用化され、大型液晶TV1台に500個~1000個のLEDが使用されるようになりました。2000年代に入り、LED市場は液晶TVの市場とともに急拡大したのです。市場が拡大すれば、規模の経済が働き、LED製造装置産業も発展、そして大幅なコストダウンが可能となります。
この恩恵を受けたのが、商業施設や住宅用の照明市場です。コストが下がり、一般照明にしては不十分とされていた光の強度、輝度が改善され、さらに日本では、2011年の原発事故による電力危機という特殊要因もあり、省エネルギーに優れたLED照明器具の普及が一挙に進みました。ほとんどの照明器具製造企業は、従来照明からLED照明に事業を切換え、LED照明市場は今後の有望市場とみなされるようになりました。
デジタルかアナログかの二者択一ではない。新たな市場の出現も?
良いことずくめのLEDですが、今年に入り、市場が予想以上に伸びていません。原因は様々ですが、従来電球からの置き換えが進まない理由に、LED照明の欠点が影響しているかもしれません。照明の良し悪しは人の感性に依存しますが、LED照明は眩しく、色合いも優しく無く、太陽光と比べての演色性も高くありません。乱暴な言い方をすれば、LEDはデジタル的照明であり、従来照明はアナログ的照明です。デジタル的照明が全ての人々に受け入れられるかどうかは、より高機能・高品質LEDの技術開発成果によるのかもしれません。
オーディオの世界では、かつてのアナログレコードが、デジタル技術の粋を集めたCDに完全に駆逐されたように見えました。しかし、昨今、アナログレコードの温かい音が見直され、一部消費者の回帰がみられるとの報告もあります。人に係る市場は、デジタルかアナログかの二者択一ではなく、一定の共存が必要なのかもしれず、その意味でも、また新たな市場が出現するかもしれません。いずれにしても、青色LEDが、社会、企業にパラダイムシフトをもたらしたことは確かだと言えましょう。
関連するその他の記事
4月施行の労働条件明示ルールの変更が働き方に及ぼす影響

小嶋裕司さん
就業規則の整備による人事労務問題解決社労士
4月施行の労働条件明示ルールの変更は労使関係にどのような影響を及ぼすか?

小嶋裕司さん
就業規則の整備による人事労務問題解決社労士
コロナ禍後の勤務形態変更の問題点 ~テレワーク廃止を会社は決定できるか?

小嶋裕司さん
就業規則の整備による人事労務問題解決社労士
創業100年以上企業数世界一の日本!これからの事業承継を考える

小嶋裕司さん
就業規則の整備による人事労務問題解決社労士