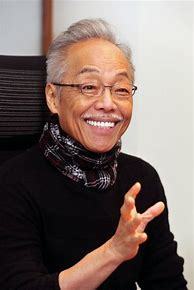ローコストなエコの家の7年後
木造建築の構造が強化されます
2025年4月1日より木造建築の構造規定が強化されます。今まで建築確認申請は一般的な木造住宅に関しては、フリーパスでした。建築士の裁量に任せて国や検査機関は関与しないと云うやり方です。それが2025年4月1日より関与する様に法改正がなされました。方法は3種類認められています。
①仕様規定のみで安全性を確認する方法
②簡易計算を行い壁量や柱の太さをチェックする方法
③許容応力度計算を用いる方法
の三種です。
①仕様規定のみで安全を確認する方法
住宅の構造に関し、構造仕様書(自社建物について平面図や立面図等に記載されていない、構造的内容は全てこの仕様に基づくと定めた書類)を取りまとめ、それを添付する事により、その家の構造図書を省く方法。
この方法が最も従前のカタチに近い、申請方法で仕様書さえつければ一切の構造図書の添付を省略出来ます。
メリット
1、構造審査期間が省ける為、建築確認申請の申請期間を短縮する事が可能になります。
2、構造図書の添付義務がありませんので、申請費用を抑える事が出来ます。
デメリット
1、構造審査が省略される為、住宅ごとの安全性を確認出来たわけではない。
2、構造図書の添付義務が無くなるだけで、構造図書を作成せず家を建てても構わないと云われたわけではない。
簡易計算を行う方法
日本住宅・木材技術センター発行の、表計算ツールを利用して柱の小径や壁量を算出する方法。
多機能版を用いれば住宅性能評価の耐震等級2・耐震等級3にも対応可能。
構造図の添付が必要になる。
メリット
1、簡単に壁量が算出可能
2、耐震等級の算出にも対応
デメリット
1、簡易計算で安全の根拠が曖昧。設計者が簡単便利なだけで、建築主にとってメリットが無い。
2、梁背等の算出や、水平構面の剛性チェック、耐力壁線間距離のチェック等がなされていない。
3、構造図の添付が必要。検査機関によっては構造図の根拠性を問う機関もある。
許容応力度計算を用いる方法
従来と変わらず、許容応力度計算を行って詳細に木構造をチェックする方法。
詳細に計算を行って、基礎の設計から、柱・梁・耐力壁の妥当性を数値で算出して安全を確認する方法。
メリット
1、今回の法改正で定められた、三種類の検討の中で、最も建築主が安心出来る方法。
2、検査機関が、構造に関与し設計者の独善を質す機能がある。
デメリット
1、検査機関が関与する為、工事途上で変更が生じた場合、再申請が必要になる可能性がある。
2、木構造に熟達した構造設計者が少ない
今後30年以内に80%の確率で発生すると云われている東南海地震。これから建設する建物は80%の確率で遭遇するという事です。
仕様規定や、簡易計算にて建築確認申請を許可する方法は、数少ない木構造技術者の負担を軽減する暫定措置と云っても過言ではありません。
新築を検討されている方は、安全を詳細に検討する許容応力度計算を行って、万全を期すべきです。
許容応力度計算に掛かる費用は、総建設費の1%程度です。1%を惜しんだ為に後々後悔する事のない様にしましょう。