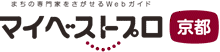- お電話での
お問い合わせ - 075-611-3600
コラム
ハイ&ロー
2016年10月22日 公開 / 2017年3月3日更新
昨今,自動車を運転する際に,ロービームの危険性を喚起し,「ハイビームが原則」ということを告知するような内容の新聞記事を多数目にします。
それらの論調はだいたい,「ロービームは40m先までしか照らさないので,それより先にいる歩行者などの発見が遅れて危険である」という感じです。
今回は,その理由を,さらに,説明します。
「車はすぐに止まれない」という言葉はご存知かと思いますが,車の運転者が,歩行者や自転車などに気づき,危険を察知しても,車がすぐに停止できるわけではありません。
この,「危険を察知してから停止までの動き」を細かく分析して見ていくと,次のように分類できると思います。
1 危険の対象(歩行者等)を目で見る。
2 その情報が脳に行く。
3 脳で危険と判断する。
4 危険回避措置として適切な行動を判断する。
(例えば,ブレーキが適切であれば,ブレーキを踏むと判断する)
5 脳から,足に対し,ブレーキを踏むという指令を発し,それが神経で伝わる。
6 足が実際に動いて,ブレーキを踏む。
7 ブレーキにある「遊び」の部分を超えて,ブレーキ動作が車に伝わる。
8 車が作動して,実際のブレーキが利きだす。
9 ブレーキが利いて,実際に停止する。
もちろん,1~8までの動作は,一瞬といえば,一瞬なのですが,実際には,早い場合でも0.7~8秒程度,平均すると約1秒弱かかるとされます。
つまり,この間はブレーキが利かずに車は走行することとなります(これを「空走」と言います)。
この空走する距離と,9のブレーキが利き始めて,実際に停止するまでに走行する距離(「制動距離」と言います)を合わせた距離が,危険を察知してから,実際に停止するまでの距離ということになります。
とすると,危険を察知した対象物がそのままの位置にいて,車がその位置に進んでいくとすると,最初にあった両者の間隔より,停止に要する距離が長い場合に,両者は衝突してしまうこととなります。
詳しい算式は,省略しますが,危険を察知して停止するまでの距離は,時速により変わり,以下の数字がひとつの目安となります。
・ 時速40キロの場合 約20m(路面が濡れている場合は,約26.5m)
・ 時速50キロの場合 約28.7m(同上,約38m)
・ 時速60キロの場合 約36.5m(同上,約51.4m)
以上でおわかりかと思いますが,時速60キロで走行していた場合,ロービームで40m先の危険の対象物しかわからないとすると,本当にギリギリ手前でしか停止できません。
逆に言うと,少しでも発見が遅れれば,衝突してしまいます。
また,雨等で路面が濡れている場合は,時速50キロでもギリギリということになります。
以上から,スピードを出すことの怖さと雨の時の危険性の大きさも同時にご理解いただけたと思います。
関連するコラム
- GWの谷間です 2015-05-01
- ゴールデンウィークは危険!?(2) 2013-05-06
- GW終了 2015-05-07
- 滋賀県の死亡交通事故 2013-07-18
- ドライブレコーダー 2013-06-03
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
笠中晴司プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。