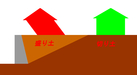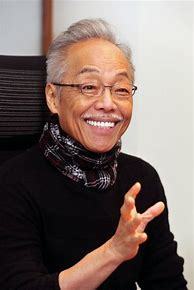地震が起きたら大阪平野に安全な場所はない。
(塔状比)法律ではない揺れない建物の目安
建物の高さを間口幅で除したものを塔状比と言います。例えば間口3.6m高さ9mの建物であれば9/3.6=2.5となりこの建物の塔状比は2.5となります。
木造の場合、この塔状比が2.5よりも大きくなってしまうと、様々な要因で建物が揺れやすくなります。
この揺れは、耐震等級とは無関係に発生します。耐震等級1の建物と耐震等級3の建物を同じ条件で揺らしてみると、耐震等級3の建物の方が揺れ幅は少なくなるでしょうが、耐震性とは無関係の揺れが発生します。
考えられる要因は?
①まず初めに考えられるのは、風による揺れです。塔状比が2.5を超えてしまうと建物の形状が帆船の帆の状態に近くなります。風と言うのは同じ風速で一定に吹くものではありません。波の様に強弱がありそれが建物にぶつかります。間口が広ければ影響は少ないですが、塔状比の大きい建物は波状的に押し寄せる風の力により揺れてしまいます。
②地盤による揺れ。軟弱地盤とされる地盤の上に建つ建物はよく揺れます。この揺れは塔状比に関係なく建物を襲います。付近に幹線道路や線路があった場合、大型車両や電車が通るたびに揺れます。杭工事や地盤改良と頑丈な基礎の設計を行う事により、この揺れは解消させることが出来ます。
③固有振動周期による揺れ。全ての個体には固有振動周期が存在します。建物の場合も同様で、鉄筋コンクリート造の様な固い建物は周期が短く、木造の様な柔構造の建物では固有振動周期が長いのが一般的です。その長い周期が災いして、例えば階段を一定の速度で下りたり上ったりすると、そのリズムが建物の振動周期と一致してしまい、敏感な人であれば、気になるほどの揺れとして現れます。
対策はあるのか
風や固有振動周期が原因の場合は、抜本的な対策はありません。原因となっている部位を鉄骨や鉄板で補強すれば、揺れは止まる可能性はありますが、今度は建物が固くなりすぎて、地震が発生した際に上手く撓ってくれず、建物がパタンと倒れてしまう可能性が出てきます。
揺れが気になる部位が机や家具などの場合は家具の四隅に防振ゴムを敷くとか、床全体の場合であれば、防振性の高い裏にゴムの張ってあるフローリングに変えるとか、対処療法するしかないでしょう。
揺れるからと言って、耐震性能が悪い訳ではないので、問題はありませんが、揺れが気になるのであれば、木造・鉄骨造に関わらず塔状比の大きな建物は避けるべきです。