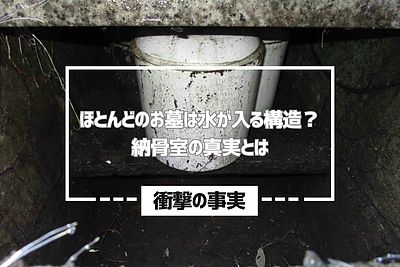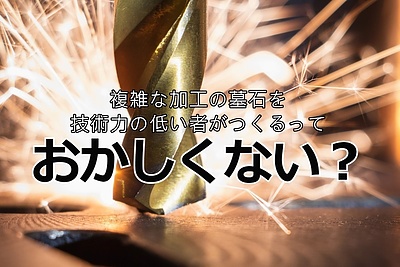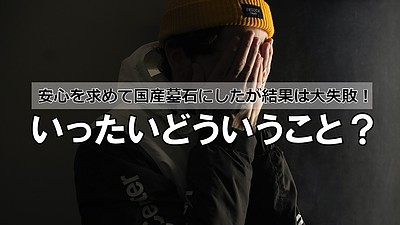【衝撃の事実】ほとんどのお墓は水が入る構造?納骨室の真実とは
一般的に「お墓」を買う、とよく言われますが、
正確には墓地使用権を取得することをいいます。
法的解釈に基づくと、墓地使用権といった場合の墓地とは、
「墓地」として都道府県知事の許可(政令都市の場合は市長の許可)を受けた地域をいいます。
そして、その地域の一角の使用権を得て、死体を埋葬(土葬)したり、
焼骨を埋蔵(火葬後の遺骨をお墓に納骨)したりする施設を墳墓(ふんぼ)というのです。
一般には、「お墓」といった場合、狭義には「墳墓」、
広義には「墓地」と両者を混同して用いるのです。
一方、納骨堂は墓埋法2条6項によりますと
「他人の委託を受けて焼骨を収蔵(火葬後の遺骨を建物内に保管)するために、
都道府県知事の許可を受けた施設」をいいます。
このように、「墓地」という名称は、墓埋法によりますが、
法律的には「墓園」という言葉も使用されています。
都市計画法11条でいう「墓園」です。
墓園は都市施設の一つとして、特殊公園として位置づけられています。
墓園は、従来の墓地からイメージされる
故人を葬り、偲ぶ場としての機能に加えて、
地域住民が参拝と同時に散歩、休息などの
レクリエーション機能を充足できるよう配慮されて、
都市計画上の名称として明治時代の「共葬墓地」、
大正時代の「墓地」であったのを、
昭和43年の都市計画法の成立に伴って改められたものです。
法律用語の「墓地」「墓園」に加えて、
今日一般的に用いられるようになったのは「霊園」の名称です。
従来の暗いイメージがつきまとった墓地とは異なり、
霊の永遠の憩いの場所を、造園的修景によって
明るく清浄な環境のなかに置く、
いうならば公園墓地という明るいイメージを持つ
「霊園」という呼称に変えたといえましょう。
お墓を建てるには、墓地、墓園、霊園の
いずれの名称であってもかまいませんが、
「墓地」として都道府県知事の許可を受けた地域以外には墓地を造ることはできません。
最近では、よく「死後は墓を造ることはしないで、死んだら遺骨を海に流して欲しい。」
と遺言する人がいますが、慎重であってほしいと思います。
※「墓地・納骨堂をめぐる法律実務」
(藤井正雄・長谷川正浩 共著/新日本法規出版株式会社発行)参照
神戸・大阪・阪神間のお墓のことなら第一石材へ
http://www.daiichisekizai.com
神戸市営鵯越墓園のお申し込みについてはこちらまで
http://www.daiichisekizai.com/boshu/