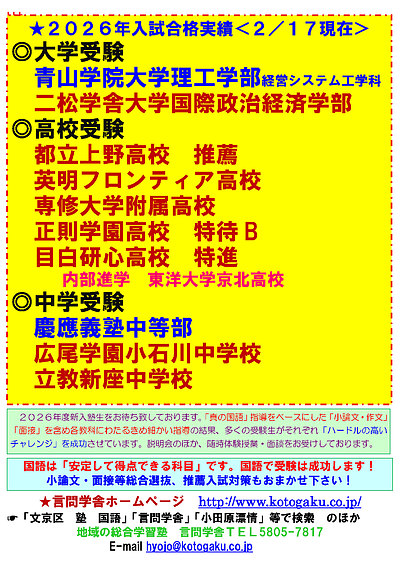<決定版!読書感想文の書き方>を公開致します!<後篇>
ひきつづき、『レモン哀歌』を読み進めます。
⑧・⑨ 単独行の二連
「正常」をとり戻した智恵子の生ける姿を、ふかく目に刻み胸に収めようとしながら、なお、智恵子の生きる力を思いその命をつなぎとめようとするかのような言葉運び。この二行ではおもに3音・4音の短い文節が繰り返され、9行目の行末を5音(半)で締めています。前後の5音・7音中心のリズムから、ここだけがゆるやかなリズムの破調となっており、Aの読者には、「ついの別れ」を噛みしめるような鎮魂の思いが、Bの読者には、いまわの際にようやくもどって来た「もとの智恵子」と、二十四年間のこもごもを振り返り、もはや一時しか残されていない二人での時間をいつくしもうとする詩人の痛切な思いが感じとれるでしょう。
⑩~⑬
作中で唯一、四行が一文となっています。ついに「命の瀬戸ぎは」を迎える一瞬のために、前二行から一転して7音のリズムが多用されて緊張が高まり、二人の別れは、「生涯の愛を一瞬にかたむけた」13行に昇華されます。
この13行目の絶唱は、光太郎と智恵子の生涯を知る読者も、知らぬ読者をも、震えさせずにはおかないでしょう。選びぬかれた表現のきびしさ、言葉の力は、それだけで読者の心を強く打つものです。
あえて言うならば、Bの読者は、この四行において、ここまで述べて来た光太郎と智恵子の人生という「行間」を、一瞬のうちに読みとるのです。
⑭~⑯
Aの読者にも、若かった二人が山のいただきで澄んだ空気を歓びあったむかしが読みとれるはずです。幾十年をともに生きた夫婦のついの別れが、慟哭を誘うでしょう。
そしてBの読者は、上高地滞在中の光太郎を智恵子がたずね、生涯をともにすると誓いあった行程から、世間と乖離し、世俗と闘い、ひたすらにお互いと芸術だけを見すえつづけた二人の生涯が、回想されます。
引用した北川太一編・旺文社文庫『高村光太郎詩集』(昭和44年3月1日初版発行、昭和52年第29刷)の「レモン哀歌」の項には、智恵子の死の床に付き添った斎藤徳次郎医師の回想が、掲載されています。
<ほんとうにそうでした。あかるい死の床、レモンの香、静寂をふるわせるものは咽喉の嵐、それだけでした。この情景はいまでも眼に映ります。夕方から脈が次第に細くなり、呼吸が乱れ勝ちになりますと、光太郎氏はもうお注射はおやめ下さいと力をこめておっしゃいました。そっとしておかれたかったのでしょう。しばらく眼をとじられて瞑想されたと思います。それからしばらくのちに「昔山巓でしたような深呼吸」を一つされました。それと同時に黒の和服に袴をつけた光太郎氏の巨大な身体が大きくゆれだしました。私は思わず外にとび出して、静かにご冥福を念じ上げました。このように荘厳な、力に溢れた臨終を、私は今日まで知りません。恐らく一生経験出来ないと存じます。>(『高村光太郎詩集』より引用、原典は「高村智恵子さんの思い出」昭和34年)
⑰・⑱
この二行は回想であり、智恵子を死の床に見送ってからしばらく時を経た時点の感懐だと、すべての読者が気づくでしょう。かなしい永遠の別れの時を思いえがきながらも、智恵子の魂を解き放ったあのレモンは、つねに詩人の心を浄める存在なのです。
『レモン哀歌』を光太郎が発表したのは昭和14年(1939)2月、智恵子の死から4ヶ月を経たのちのことです。Bの読者は、この作品が智恵子の死後数ヶ月を経て書かれたものであることはもとより、光太郎がやがて『元素智恵子』の境地を獲得し、戦後岩手の山口村に山小屋をかまえたのちも智恵子とともに生きたこと、さらに昭和28年(1953)に原型が完成した「十和田湖畔の裸婦像」までもが智恵子をモチーフとしていることに、思いをはせることでしょう。
つづく