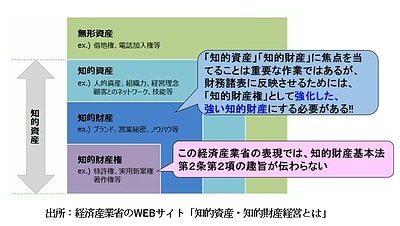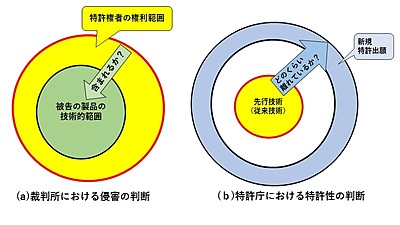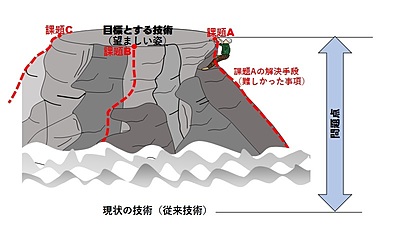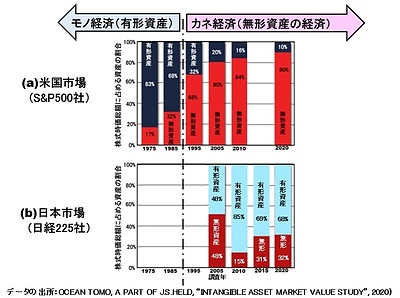第85回(前編) 知的財産経営とは何か? 知的財産の弱みとデザイン経営の趣旨を理解しなければ、財務諸表に反映できる強い知的財産経営を実現し、知的財産経営による日本経済の復活はない
1. あとは知恵者が知恵をだす
2013年8月26日付け毎日新聞に、「逆だよ、逆。今ゼロという方針をださないと将来ゼロにするのは難しいんだよ。野党はみんな原発ゼロに賛成だ。総理が決断すればできる。あとは知恵者が知恵を出す。」「必要は発明の母って言うだろう。敗戦、石油ショック、東日本大震災。ピンチはチャンス。自然を資源にする循環型社会を、日本がつくりゃいい」という小泉元首相の談話が記載されている。
小泉元首相は、「知恵者」とは誰かを明言していない。しかし、「知恵者」とは科学技術者であろう。科学技術者の発明が原発ゼロを可能にするという意味であろう。実は、後述するように、平成18年6月に西澤潤一元東北大総長が当時の小泉純一郎内閣総理大臣に「原発ゼロ」を可能にする知恵を提供しているのである。
2012年2月15日、衆議院の東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) 第4回委員会で、野村委員が「あの…、私はちょっとびっくりしているんですけども、原子力の規制行政庁のトップは原子力についての知見を持たない方がなっておられるということなんでしょうか。」と質問したところ、参考人として招致された前原子力安全・保安院長 寺坂信昭氏は、「知見といいましょうか、原子力工学その他理科系の学問をつんで原子力安全行政をずっとやってきたわけではないということで、もともとは事務系の人間でした。次長になったときに、初めて原子力安全行政を担当したということでございます。」と回答している。
寺坂信昭氏は経済学部の出身で、理科系ではない。当時、毎日テレビに出ていた原子力安全・保安院の西山英彦審議官も、文系出身で原子力に関しては技術的なことは殆どわからず、東電が調査したデータをただタレ流しているだけであったと言われている。
1955年12月に成立した原子力基本法に基づき、故正力松太郎氏に請われて、1956年1月1日に湯川秀樹博士は原子力委員会委員に就任したが、考え方が違うことが分かり1年後に抗議の辞任をしている。正力氏が「研究などしなくても外国から炉を導入すればいい」と言っていたようだ(2007年1月24日 毎日新聞(夕刊))。
1955年といえば、通商産業省自動車課が国産自動車技術の開発を前提とする「国民車育成要綱案」を発表した年でもあり、我が国の技術水準が欧米諸国に比し極めて低いレベルにあった時代ではあるが、正力松太郎氏の発言はあまりにも安易な見識と視座を示している。
湯川秀樹博士は、「動力協定や動力炉導入に関して何等かの決断をするということは、わが国の原子力開発の将来に対して長期に亘って重大な影響を及ぼすに違いないのであるから、慎重な上にも慎重でなければならない」と辞任直前に述べている(『原子力委員会月報』57年1月号)。実は我が国の原子力政策は、ノーベル賞受賞科学者の金言を無視し、理系主導ではなく文系主導で極めて強引に推進されてきてしまっている。
湯川秀樹博士は戦後米国に渡り、コロンビア大学の客員教授を務めていたが、アインシュタインから原爆の日本への投下を止めきれなかったことを涙を流して謝られたと言われている。
歴代の東京電力の社長の出身学部を見ると、法学部、経済学部と文系出身者が独占してきており、取締役会の構成も文系63%、理系37%と文系が優位である。理系トップが1人も見当たらないのは電力10社のなかでも東京電力だけらしい。文系のトップには「想定外」の原発事故の対応は不可能であろう。
それでは、理系のトップであれば、「想定外」の原発事故の対応は可能であったであろうか。2011年3月15日午前6時12分に福島第1原発4号機の原子炉建屋が大爆発している。河北新報(2012年08月10日)によれば、当時の吉田昌郎所長や部下の運転員がそれまで着用していなかったヘルメットを、15日の早朝の午前6時よりずっと前のタイミングには、突然全員かぶっていたとのことである。文系のトップとは異なり、現場の運転員たちは午前6時の前に自分の近くで爆発が起きることを正確に予測していたのである。
東電の発表によれば津波到達2分前に電源喪失しており、実は、主蒸気逃がし安全弁(SRV)が動作しなくなっていたという事情もあるが、政府や東電の事故調では吉田所長や原発運転員全員が、誰一人も非常用復水器の作業マニュアルを知らず、非常用復水器を動かした経験も無かった、ということになっている。理系のトップであっても、原発の設計や非常用復水器の構造等を含めた原発の全体を熟知していなければならないのである。
この意味では大学等における理系の教育にも問題がある。恩師西澤潤一先生(元東北大学総長)は独創的な研究をするためには、既存の設備やメーカーから購入できるような装置での研究では駄目で、実験装置から世の中にない新規な装置を自作しなくてはならないとのご指導をされた。したがって、研究室は手作りの装置だらけであった。
私は、毎日、油だらけになって付属の機械工場に通い、旋盤加工やフライス盤加工による実験装置の自作をした。更に、専門業者から無理と言われたクリーンルームを製作したし、廃液の中和槽の製造に必要なコンクリート工事もした。
このような西澤研究室の教育思想があれば福島の事故も別の結果であったかもしれない。作業マニュアルを読んで装置を運転するような理科系の教育では、日本の将来は危ないのである。理科系の人間は、単なる作業マニュアルだけでなく、自分の扱う装置の構造や原理原則をすべて熟知していなければならない。非常用復水器の構造や主蒸気逃がし安全弁(SRV)の構造を熟知している人間がトップにいれば、結果は違ったはずである。
「知恵者」とはこのような原理原則が分かる理科系の科学技術者ということである。既存の設備やメーカーから購入できるような装置をただ使うのでは「知恵者」とはいえない。
福島の1号炉、2号炉、6号炉は米国GE社製の輸入品である。3号炉と5号炉は主契約者が東芝、4号炉は主契約者が日立であり、3号炉から国産化が図られたがすべての原子炉の基本設計は米国GE社のものである。
福島の事故は、故正力松太郎氏が「研究などしなくても外国から炉を導入すればいい」と言っていたことの負の遺産による人災である。湯川秀樹博士の金言に従い、非常用復水器の構造や主蒸気逃がし安全弁等の構造や原理の分かる人間を養成しておくべきであったのであるが、「時既に遅し」である。
2. 知恵者の「知恵」は「技術」に対して用いる
「技術」とは、以下の4つの要件を満足するものであろう:
(a)一定の目的を達成するための具体的手段であって、設計可能な複数の「要素技術(構成要件)」の有機的結合からなるもの(第1原則);
(b)客観性と再現性があり、「従来の技術」を基礎に「新たな技術」に発展させることができるもの(第2原則);
(c)フェイルセーフであるもの(第3原則);
(d)産業廃棄物を含めて自然と調和可能なもの(第4原則)
第1原則でいう「要素技術」は、更に、下位の複数の「要素技術」の有機的結合からなっている。第1回のコラム[何が特許になるのか(進歩性という考え方)]において、「新しくても、 単なる公知技術の寄せ集めでは特許にはならない」と説明したが、殆どの発明は、従来知られている技術の組み合わせから成り立っている。従来知られている公知技術を基礎としていない発明は、皆無と言ってもよいが、新しいだけでは特許されないということである。従来知られている技術の組み合わせから成り立っていても、その新しさが、通常の人が、容易に思いつけない程度に、斬新な創造性があれば、特許として登録されて独占権が付与されるということである。
第2原則では、「新たな技術」には、その基礎となる「従来の技術」があるということである。第1原則でいう「設計可能」とは、当業者であれば、だれでも実施できる定量性を有するということであり、「設計可能」とは、客観性と再現性があるということであるので第2原則は、第1原則を言い換えたものである。しかし、第2原則でいう「従来の技術」を基礎に「新たな技術」に発展させることが特許制度の根幹をなす。
第3原則でいう「フェイルセーフ」とは事故やリスクが発生した場合、安全の側に停止できるという要請である。原子力発電を推進した理論の一つに「リスクのない技術は存在しない」という論理があるが、「リスクがあるかないか」が問題ではない。「そのリスクにどのように対応できるか」が重要である。津波もリスクではあるが、想定外の津波が襲ったから放射能汚染が発生したというのでは、「フェイルセーフ」ではない。
例えば我が国の交通信号灯が何かトラブルが発生したとき、すべて赤色の表示になるようになっているのは、「フェイルセーフ」の設計思想があるからである。
キュリー夫人の長女イレーヌ・ジョリオ=キュリー(Irene Joliot-Curie)達によってなされた日本国への特許出願を、我が国の最高裁判所は、「中性子の衝撃による天然ウランの原子核分裂現象を利用するエネルギー発生装置は、右原子核分裂に不可避的に伴う危険を抑止し、定常的かつ安全に作動するまでに技術的に完成されていないかぎり、旧特許法(大正一〇年法律第九六号)一条にいう工業的発明にあたらない」として認めなかった(最高裁判例 昭和39(行ツ)92 (1969年(昭和44年)1月28日判決))。
最近ブレーキのない自転車に乗って逮捕者が出たようだが、ブレーキのない自動車や緊急停止できない装置等は危険(リスク)を察知しても停止できないから「フェイルセーフ」ではない。原子力規制委員会の中村佳代子委員は、「管理することができない、あるいは、信頼することができない科学や技術は使用してはならない」と述べている。
大地震の発生を検知したら緊急停止のできる新幹線の技術と、大地震の発生を検知しても停止ができずにメルトダウンする可能性のある原子力発電所では、地震対策が全く異なることを十分に留意する必要がある。
アインシュタインや湯川秀樹博士は「フェイルセーフ」の問題に気がついていたはずである。残念ながら、人類は、文系主導の道をたどった結果、危険なときに停止できない物理現象を安易にも利用して、「フェイルセーフ」ではない未完成な技術を電力事業に採用するという愚を犯してしまった。
第4原則は、E.クラッコとJ.ロステンス(E. Cracco and J. Rostenne)が提案したソシオ・エコロジカル・プロダクト(Socio-ecological Product)の概念につながるものである(E. Cracco and J. Rostenne, "The Socio-ecological Product", Michigan State University Business Topics, Summer (1971))。ソシオ・エコロジカル・プロダクトとは、「自然から自然に戻るシステムの諸要素を含むトータル製品、又全世界構造への影響を考慮するシステムの諸要素を含むトータル製品」と定義される。原子力発電が始まった当初から核廃棄物の処理の問題が議論されていたが、今もって有効な処理方法が確立できていない。
上記の第3原則及び第4原則から、現在のレベルの「原子力発電は技術ではない」と断言できる。
3. エネルギー問題は、「発生技術」「分配技術」「消費技術」
小泉元首相の原発ゼロの提言には具体策がないという批判があるが、どうも、文化系の人たちは、エネルギーの発生技術しか論じていないようである。電気エネルギーは、発電所で「発生」した後、電線を介して送配電するという「分配技術」に依存したのち、家庭や工場で「消費」されている。有限な資源である電力エネルギーは、「発生技術」「分配技術」「消費技術」の3つの側面でとらえなければならないのに、文化系の人たちは、偏った議論しかしていない。
「分配技術」とは、地球上の有限な電力資源をいかに効率的・合理的に配分するということであり、「消費技術」とはLED照明等のいかに効率よく電気エネルギーを消費し無駄をなくすかという技術である。「消費技術」に関しては、今後多くの発明が期待される。
今、注目すべきは、「分配技術」である。現在の電力需要というものは非常に変動が激しく、地球上の特定の地域に着目すれば、電力使用量が混み合う夏場のピーク時とオフピーク時では、最大電力量は倍近くも異なるのが実情であろう。また、地球上の特定の地域に着目すれば、一日の時間帯でも昼間のピークと夜のオフピークでは倍近い変動がある。つまり、電力事業の稼働率の変動が著しいことが問題なのであり、電力需要のピークなど全体のほんの一部にすぎない。今議論されているのは、地球上の特定の地域における過渡現象であり、理科系の知恵である「分配技術」により電力不足は解消するのである。
電力事業というものは、どのようなときにも安定的な電力供給を行わなければならないという「供給義務」が課されているため、地球上の特定の国や地域に着目した場合、夏場数日間の昼間における一番のピーク時に対応するために、きわめて過剰な発電所設備を保有しているのである。
北半球と南半球とでは夏と冬は逆転しており、太陽に面した半球であるか裏側であるかで、昼と夜は逆転している。このため実は、特定の国や地域の局所的なピーク電力の問題は、地球全体をみたグローバルな観点から、余っている国や地域から供給するような「分配技術」によって、現在でも、発電所はあり余っている状態となるのである。原発ゼロはすぐできるのである。
原子力発電所は、経済学で「アバーチ・ジョンソン効果」と呼ばれる過剰設備、非効率の典型例の産物である。このような過剰設備を許しているのが、各国の電力会社への規制であり、我が国では、文化系の発想により「総括原価方式」の下、どのように過剰な設備をもっていてもすべて電力料金に転嫁でき、しかも地域独占によって競争相手にさらされずに、料金を引上げられることを許してきた。
我が国の各電力会社も、文化系の発想により、経済産業省の官僚も、発電所設備を拡大することで利権があるので、福島での事故が発生するまで、こうした規模拡大に拍車をかけてきた。しかしながら、グローバルな理科系の見地から、あり余っている状態の国や地域から不足の状態の国や地域に電力を供給する送配電技術に着目し、ここに理科系の英知を集中すれば、原子力発電所は現状でも不要なはずである。
4. 経済学は、理科系
ライオネル・チャールズ・ロビンズやポール・アンソニー・サムエルソンの教示するところによれば、経済学とは、地球上の有限な資源をいかに効率的・合理的に配分し、有限な資源を最も効率的に利用し、いかに価値を生産し地球上に配分し、地球上の人間がより望ましい生活ができるようにすることができるようになるかを研究する科学技術等を含めた総合的な学問であり、きわめて理科系の色彩が強い学問である。
経済学でいう「資源」とは、生産要素のことであり、土地及び資本の物的資源と労働の人的資源を意味する。経済学では、「土地」には、石油や鉄鉱石などの天然資源も含むとされる。理科系の視点からは、地球上に有限に存在する食料、鉱物資源、エネルギー資源等を含めたより広い意味の資源を考えたい。
経済学の一領域にピグーや福田徳三先生の「厚生経済学」がある。厚生経済学が理想とするのは社会全体の快適な状況であり、最適な資源配分が必要になる。経済学では「厚生」は有益性や望ましさを意味する。厚生経済学は最適な資源配分を通じて、理想的な経済を造りだし、社会的厚生の最大化を実現することを目的としている。理科系の視点からは、最適な電気エネルギーの配分を通じて、理想的な経済を造りだし、社会的厚生の最大化を実現することが経済学の目的となるのである。
5. トーマス・エジソンの失敗からグルーバルな電力供給網へ:
発明王トーマス・エジソンは、1881年、電力の供給方法として直流送電方式を発明した(米国特許第263,142号、米国特許264,642号、米国特許第266,793号等)。エジソンは、1882年にニューヨークに水力発電所を設立し電力事業を開始したが、ジョージ・ウェスティングハウスとニコラ・テスラが主張した交流送電方式との電流戦争が始まり、エジソンは敗北することとなった。
電線自体には電気抵抗が存在するので、電線を介して送電すれば、必ず電流は抵抗損失で失われる。電気エネルギーは電圧と電流の積である。電線の抵抗損失による電流の減衰を抑制して電気エネルギーを効率良く送るためには、送電時の電圧をより高くすればよい。
この点で、交流送電方式であれば、変圧器で簡単に昇圧や降圧ができる。一方、直流送電方式において、発電所側で交流を変圧器で高電圧に昇圧後、高電圧の交流を直流に変換して直流送電をし、目的地において高電圧の直流から交流へ変換後、変圧器で降圧し、工場や家庭に供給する必要がある。
交流送電方式の場合は、電線の抵抗損失だけでなく誘導損失がある。このため、交流から直流へ変換損失、及び直流から交流への変換損失を無視して送電線の損失のみを比較すれば、直流送電方式は交流送電方式より低い電力損失ではるか遠くまで送電できる利点を有している。
エジソンが電流戦争に敗北したのは、19世紀後半から20世紀前半にかけての技術レベルでは、交流から直流への高効率の変換器、及び直流から交流への高効率の変換器が存在しなかったからである。
しかしながら、西澤潤一元東北大総長は、1950年に99%以上の高効率で交流を直流に変換できるpinダイオードを発明し(特許第205068号他)、更に1976年になり99%以上の高効率で直流を交流に変換できる静電誘導サイリスタ(SIサイリスタ)を発明した(特許第1089074号他)。
人類の持つ効率99%以上のエネルギー変換装置は変圧器と、pinダイオードとSIサイリスタの3つしか存在しないが、そのうち2つが、20世紀の中頃になり、我が国で発明されたのである。エジソンの敗北から1世紀以上が過ぎたが、pinダイオードとSIサイリスタの発明という技術レベルの向上により、直流送電方式の汚名をそそぐチャンスが来ているのである。平成18年6月19日に、当時西澤潤一先生を会長とする社団法人先端技術産業戦略推進機構は、小泉純一郎内閣総理大臣宛にこの直流送電方式の提言をしている。
例えば、約1600kmの送電線で数千MWを送電する場合、交流送電方式では12~25%の電力が失われるが、直流送電方式では6~8%に抑えられる技術レベルが達成されている。
スイスに本社を置く多国籍企業であるABB社は中国の三峡ダムから広東省に向けて940キロの直流送電の送電線を整備、2004年から運用している。 ABBは、更に向家ダム上海間の2,000km強の距離を800kVの超高圧にして6,400MWの電力を供給している。2012年にABBが開発した1,100kVコンバータ変圧器を用いた技術では、10,000MW以上の電力を3,000km送電することが可能になるとのことである。
直流送電方式は、異なる電圧や周波数を用いる異なる国間での送電の促進が可能であり、グローバルなスマート・グリッド網の構築に好適な技術である。既に、1980年代に哲学者で建築家のバックミンスター・フラーが、上記のグローバルなスマート・グリッド網を"Global Energy Grid"として提案している。
現在、日本全国で総発電量の5%ほどが交流送電方式で失われていると言われている。2000年度の資源エネルギー庁の概算によれば、1年間に「100万kW級の原子力発電所6基分」の発電量に相当する約458.07億kWhを無駄に損失しているとのことである。
地球の温暖化に伴う海面上昇の防波堤を波力発電に用いるという選択もあるであろう。環境問題もあるが、地球上には水力発電に用いることの可能な水力が豊富にある地域や国がある。防災上、ダムが必要な地域もある。水力発電所の他、風力タービンや太陽光パネル等を含めて、地球上広範囲に散らばっている種々の自然エネルギーを用いた電力源からの電力供給網を結び、巨大なパワーグリッドを、スマート・グリッド網としてつくり上げれば、火力発電所や原子力発電所は不要になるであろう。
我が国の炭酸ガス排出量は2010年度には、11億9,110万トンまで下がり、総排出量も京都議定書において国際公約した基準年の目標値を下回っていたが、福島の事故のあった2011年度では、炭酸ガスの総排出量が12億4,060万トンにまで膨れあがり、基準年の目標値を達成できない状況になっている。
しかし、欧州委員会の2013年10月9日の報告書によれば、脱原発を掲げているドイツ等のいる欧州連合(EU)は京都議定書でEUに課せられた1990年比8%削減の目標を大幅に超過達成することが確実になったということである。
現在、炭酸ガスの排出量が削減された火力発電の技術も開発されつつあり、排出量ゼロという報告もあるようである。人類の叡智の使いようによっては、化石燃料を使うから直ちに地球の温暖化が進むという短絡的な議論にはならないかも知れないが、化石燃料には限界がある。
1995年のアメリカ合衆国内務省開拓局長官ウィリアム・ピアーズの「アメリカではダム建設の時代は終わったという避けがたい結論を得た。最早従来型の大規模な建設プロジェクトを遂行するだけの一般大衆の支援も政治的支援も当てには出来ない。現在遂行されているダム事業は速やかに完成させるが、今後新規の大規模事業が遂行される可能性はほとんどない」との発言は、日本のダム反対に影響を与えるものとなった。
しかし、本当に水力発電用のダムがどのような問題を発生するのかは、環境問題を含めて、グローバルな観点から、慎重な議論が必要である。又、水力発電はダムがなくても可能である。
現在、アジアスーパーグリッド構想をはじめ、北アフリカ-中東-ヨーロッパを結ぶデザーテック計画やサハラ・ソーラー・ブリーダー計画など多くの直流送電網の検討が世界中で進められている。しかし、不思議なことに、上述したABB社が政府筋に「やろうと思えば3ヵ月で海底ケーブルは敷ける」と既に説明したらしいが、我が国の電力関係者は首を縦に振らなかったそうである。
今こそ、政治家の決断が必要なときなのであるが、故正力松太郎氏の負の遺産から脱却した理系の英知が求められているのである。平成18年に西澤潤一先生が小泉純一郎内閣総理大臣宛に提言した、エジソンの直流送電方式に注目すべきときなのである。
辨理士・技術コンサルタント(工学博士 IEEE Life member)鈴木壯兵衞でした。
そうべえ国際特許事務所ホームページ http://www.soh-vehe.jp