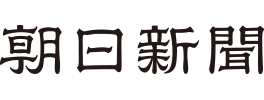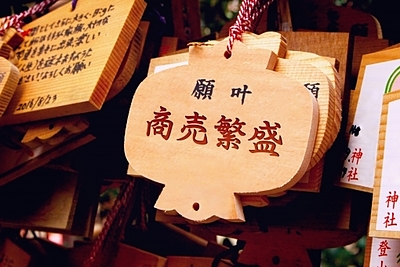部下を持ったら考えましょう! 人を動かす、人を育てる とは?
【はじめに】
昭和の子供時代には「漫画ばかり読んでると碌な大人になれないよ!」
等と言った指摘(叱責?)を家庭では親から、学校では教師から言われたものです。
自分自身も高校生になった頃には
電車やバスの車内で大の大人が漫画週刊誌を読んでいるのを見ると
「いい大人が…」と若干冷めた目で見たものでした。
それが60をとっくに過ぎた今でも欠かさず定期購読している始末です。
~確かに、私に関してはろくな大人にはなっていませんでした~
勝手な思い込みですが、昭和の中盤以降に生まれた世代と紙媒体の週刊漫画本は
同じように進化(変化?)を続けてきた仲間、なのではないでしょうか?
今日は、4月、新年度最初のコラムとして
かなり砕けた内容の話を進めたいと思います。
【昭和の漫画はあくまでも少年少女向けが主体】
以前にもこの傾向についてブログで書いたところ
ある新聞社からインタビューを受けたことがありました。
漫画世代の年齢に合わせる週刊誌の思惑?
的な内容の記事として朝刊にインタビュー記事が掲載されました。
その時には中間管理職の主人公の日々、仕事にまつわるあれこれを
採り上げたものでしたが、令和の今では後期高齢者の日々が主題となった作品が
連載開始となっています。
個人の勝手な推測ですが、昭和漫画世代第一期生?の
人生に寄り添うようなテーマをピックアップして漫画化しているのではと
考える次第です。
正直な話、昭和の時代3~40年代には
漫画と言えば「少年・少女」漫画が週刊漫画の主体でした。
いわゆる「学園もの」「スポ根もの」「ラブロマンスもの」「SFもの」等など
同時代の子供たちがこうありたい、こういう生活に憧れるといった
夢を与える内容だったと思います。
さすがの私もこの時代にはまだ街中で見受けられた「貸本屋」は経験しておらず、
そこには大人向けの漫画もあったと聞いたことはありますが、
ここでは週刊少年漫画等の週刊誌の変遷に焦点を当てていきたいと思います。
【気が付けば中高年シニア向け雑誌に?】
そのような中、少しづtづ漫画のテーマに今までとは違う潮流が生じてきました。
今に続く「身近な職業」をテーマにした漫画です。
料理人や落語家、それこそ漫画家を目指す青年が様々な経験を経て最後には目出度く独り立ち。
という内容は小中学生というよりは高校生以上の、社会との接点がより濃密になってきた世代を
ターゲットにしたものと思えました。
同様にラブロマンス物も秘めた恋や愛と憎しみの交錯するようなリアルな内容が目立ち
スポーツものでも主人公の敗北という「綺麗ごとでは済まない」現実を取り込んでました。
先の職業をテーマにした内容でも寄り身近な「サラリーマンもの」が登場し
ここでも醜い出世競争の世界や競合他社との終わりなきビジネスウォーズといった
多くの学生には「あと何年か後には自分たちが属するであろう社会」がテーマとなってました。
さらに進んで詐欺師や街金、闇金といった「裏社会のヒーロー」が漫画として登場、
漫画の世界から多くの社会のタブーや詐欺の手口等を学んだ方も少なくないと思います。
高校生レベルになれば「勧善懲悪の世界」は漫画の中でも夢物語、机上の空論といった
冷めた見方をする層がいても不思議ではありません。
大学生や20代の社会人ともなればその傾向は一層深まるのは当然でしょう。
今では世界のミリタリーバランスや政治情勢、政界の裏表、不動産業界の裏表など
タイムリーな話題がそのまま登場するような作品も登場しており
下手な参考書を読むより手軽に、容易に知識を得るきっかけが漫画となっています。
その結果、令和の今はサラリーマンものでも
「定年退職後」や「定年目前の」仕事や日常生活をテーマにしたものや
「熟年離婚」や「老いらくの恋」さらには「相続問題」から「葬儀・お墓」の
問題をテーマにしたものから社会問題となっている「おひとり様」や「孤独死」まで
いよいよ昭和の漫画少年第一期生の「最終コーナー」に向けた内容が登場してきたのです。
【終わりに~紙媒体の雑誌の将来】
以上は私の経験したマンガ遍歴からの独断ですが、
先に書いた新聞のインタビュー以降に交流を持つようになった
出版関係の方々ともこの傾向についていろいろ話をしました。
それによりますと
担当する分野は違えど、漫画以外の週刊誌にしても
競合誌が毎週のように類似したテーマ、それも高齢社会を
採り上げた特集記事を掲載しています。
その理由は「その方が売れるから」に尽きるとのことでした。
いわゆる一般週刊誌においても
昭和の時代には芸能界の話題やギャンブル・ナイトスポット等の遊びの記事や
若い男性を狙ったお色気路線の記事を掲載すれば「売れた」ようです。
その世代が管理職になる時代にはサラリーマンの悲哀や、ボーナス活用術、
子供の教育問題や住みたい街ランキングといったテーマが「売れた」ようです。
そして今では「熟年離婚」「相続トラブル」「空き家問題」「終活」
といったテーマに人気が集まってきた・・・
要するに漫画週刊誌も含めて「紙媒体の雑誌関連」の固定客は
10代20代の頃から60,70代の今に至るまで一貫して固定客となっているのです。
若い頃の読書という習慣、それも書籍という形で習慣となった世代にとっては
紙をめくって次を読む、大切に保管して後から何度も読み返す、同じ嗜好の知人に貸して
感想を語り合うといったことが生活の一部となっていました。
それが今では書店の閉店、廃業のニュースが連日記事になっています。
ひとつの自治体、それも市のレベルで書店がゼロというニュースには
正直現実味がありませんでした、「本屋のない街が増えている!」
さらに「あらすじだけ読めば十分」「トレンド本は誰かの紹介文でわかったつもり」
といった傾向が若い世代に増えているという事実にもショックを受けました。
その要因のひとつが「ネットの普及」というのを
先の出版関係の方からも聞きました。
先ず紙の本でなくて「電子書籍」は読んでいる、
紙の書籍を買わなくなってもう何年もという傾向です。
曰く「持ち歩くのに嵩張らない、家に置き場所がない、好きな時に読める」
「一度読めば即消去でお手軽」など等が主な理由でした。
さらにネット上にある「〇〇のネタバレ、あらすじ、書評」といった
サイトを読めば大体の内容が把握出来る、友人との会話でボロが出ない、
といったことで「読書」を済ませたことにするといった傾向です。
そういう流れに掉さすのが我々のような「生え抜きの漫画世代」であり
おカネを惜しまず紙媒体を定期的に購入してくれる「VIP」なんだそうです。
そうであればお得意様の気を惹く、関心が集まる様なテーマを漫画化する、
それで一定数の部数は確実に計算できるのですから。
ただ、我々世代が遠くない将来、確実に表舞台から退く時が訪れます、
その時紙媒体の書籍はどうなっているのでしょうか?
逆に言えば今の40代以下の世代、さらにその下のネット読書世代に
紙媒体で読書する為には今から何をするべきなのか?
当時の出版社の方からは明快な答えは返ってきませんでした。
当然ながら私にもこれといった見通しもアイデアもありません。
機会あれば改めて出版社の方に紙媒体の将来について尋ねてみたいと思います。