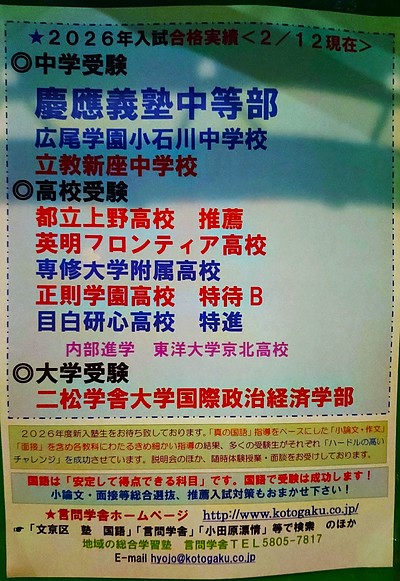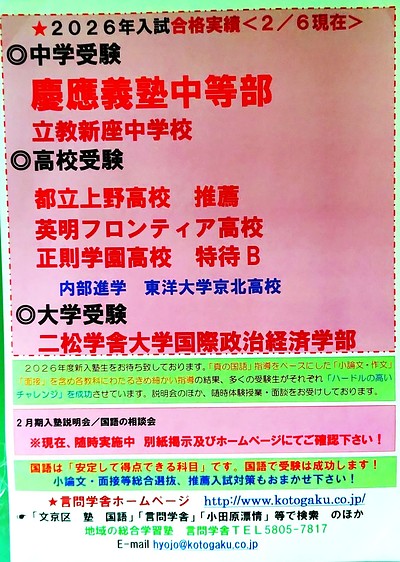三陸の鉄道に捧げる頌(オード)の完結作『志津川の海』を書きました!
各地の豪雨、さらに台風と、なかなか夏らしい日がやって来ません。「詩の朗読」をはじめた一昨年以来、夏休みは立原道造の詩を朗読するならいでしたが、今年は「智恵子の半生」の朗読が7月の終りまでかかりましたので、少々遅くなりました。立秋を迎える前には、と思いまして、本日初期詩篇の中から代表的な「村ぐらし」を読ませていただきました。
作品中、「あの人はそのまま黄色なゆふすげの花となり」という一節があります。のち昭和11年(1936年)には、「ゆふすげびと」という作品がありますが(「詩の朗読」既発表)、この頃から「あの人」は「ゆふすげの花」になぞらえられていたようです。この女性について、室生犀星の文章を引用します。
「追分村の旧家に一人の娘がいて、立原はこの娘さんを愛するようになっていた。(略)私はその娘さんを一度も見たことはないが、一緒に散歩くらいはしていたものらしく、その途上にあった雑草とか野の小径や、林の上に顔を出している浅間山なぞが、娘さんのからだのほとぼりを取り入れて、匂って来るような彼の詩がいたるところにあった。娘さんとの交際は一、二年くらいの短さで終り、東京の人と結婚したらしい、いわば失恋という一等美しい、捜せばどこにでもあってしかもどこにもないこの愛情風景が、温和(おとな)しい立原に物の見方を教えてくれただろうし、心につながる追分村が、ただの村ざとでなくなっていたのであろう。」(我が愛する詩人の伝記)
7月には、塾生の高校生が、お母さんと軽井沢へ泊りに行った土産話を聞き、私自身も立原や堀辰雄の軽井沢、追分にあこがれた学生時代や、その後数回遊びに行った二十年ほど前の一時期のことを、なつかしく思い返しました。
まことに立原さんらしい、初期の一篇です。お目通しいただければ幸いに存じます。