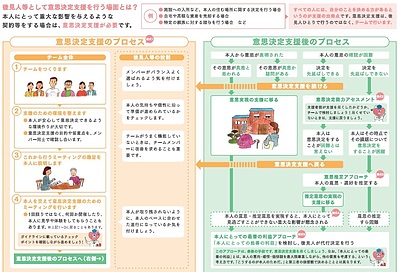遺言書に記載した相続人が先に亡くなったら
「自宅を自分に遺す、という遺言を父がつくっている様なのですが、家には母も住んでいるので、自分は相続しなくてもいいと思っています。その遺言を拒否することは出来るのでしょうか?」というお問い合わせをいただいたことがあります。
遺言で財産の引き継ぎをすることを「遺贈」といいます。
また、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」という2つの種類があります。
包括遺贈とは、引き継いでもらう財産の割合だけを指定した遺贈で、「Aに全財産の半分を遺贈する」などの場合です。
これに対し、特定遺贈とは引き継ぐ財産を特定した遺贈で、「○○をAに遺贈する」という様な場合です。
そして、遺贈の放棄については、方法や期限の有無など、その種類で規定が異なっております。
包括遺贈の放棄
包括遺贈は、民法第990条で「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と、規定しております。
相続におきまして、相続人が財産の引き継ぎを希望しない場合、家庭裁判所へ「相続放棄」の申立をする必要があります。
この相続放棄は、「相続があったことを知った時より3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立をすることにより、「初めから相続人とならなかったものとみなす」という制度です。
これと同様に、遺贈による財産の引き継ぎを希望しない場合、「包括遺贈があったことを知った時より3ヶ月以内」に、「包括遺贈放棄」の申立をしなければならない、ということになります。
なお、包括遺贈の放棄につきましては、実務上、相続放棄申述書を訂正した形で用いることになっている様です。
その際、遺言者の最終戸籍と住民票の除票、放棄をする方の住民票、それに遺言書の写しを添付する必要があります。
特定遺贈の放棄
民法第986条第1項には、「受遺者は、遺言者の死後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる」という規定があります。
こちらから、特定遺贈を放棄する場合には、相続人や遺言執行者に対してその意思表示をすればよいことになり、包括遺贈の様な期限もありません。
ですが、ここで問題となるのは、遺言が「○○をAに相続させる」というような文言であった場合です。
「~に遺贈する」ではなく、「~に相続させる」という文言の遺言を放棄できるか、ということにつきましては、見解が定まっていません。
これを否定した判例(平成21年12月18日決定・東京高裁)では、「~に相続させる」遺言は“遺産分割方法の指定をしたもの”という見解を示し、その利益を放棄するには「相続人全員の協議による合意が必要」としております。
この裁判は、「不動産をすべて相続させる」という遺言の放棄について争われたのですが、亡くなられた方から離れて生活をしている相続人にとって、現在の生活圏から離れた場所の不動産取得を望まない方は、決して少なくありません。
ただ、特定の事情があったとしても、現在の法律では“不動産だけを相続放棄する”ということは認められていません。
この為、正式な「相続放棄」をして、すべての財産を相続することを放棄していない場合、望まない不動産であっても相続人が全員が相続をすることになります。
この“相続をしたかどうか”につきましては、相続に関する手続きが完了しているかどうかとは関係がありませんので、名義人が亡くなられた方のままであっても、その所有者は相続によって相続人になった、ということになります。
遺言内容と異なる相続を希望する場合には
こちらは、民法第907条第1項の「共同相続人は、~その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができる。」という規定から、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることが可能だと考えられております。
この時、一旦遺言通りに相続したものを、相続人全員の協議によって新たに分割をやり直しをする、ということになるのであれば、“相続税の納税義務者は誰になるのか”、“協議によって分割を受ける相続人へ贈与税が課税されるのか”、という疑問が生じます。
この点について、国税庁は「受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当」とし、相続税が課税される場合の納税義務者は、協議によって相続をした者となり、この協議で引き継いだ財産に贈与税は課税されない見解を示しております。
⇒国税庁HP タックスアンサーNo.4176