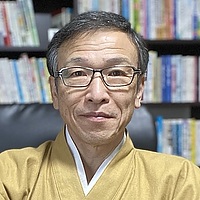見えない心に寄り添うために、親が持つべき“観る眼”とは
家族の再生
「この子のひきこもりに取り組んだことで、
初めて夫婦になれたような気がします」
「この子のお蔭で、家族がまとまりました」
「わが家の一大事も悪いことばかりではありません。
多くのものを得ることができました」
これらの言葉は、家族支援を行っていく中で、
しばしば聞かれる言葉なのです。
いずれも、目の前の厳しい現実に立ち向かっていった
家族がたどりついた心境です。
私はこの言葉を聞くたびに、家族の蘇生力、絆の尊さに
感動します。
世間とは何か
不登校やひきこもりに限らず、
様ざまな「問題」が長期化する背景には、
『世間』というものがあります。
この『世間』という言葉は、もともと仏教の言葉です。
俗世間を表す言葉で、社会一般を示しているように使われていますが、
「社会」とは違うものです。
政治家や財界人などが何らかの嫌疑をかけられたとき、
しばしば「自分は無実だが、世間を騒がせたことについては
謝罪したい」と語ることがありまが、
この言葉を英語やドイツ語などに訳すことは不可能だそうです。
(『「世間」とは何か』阿部謹也著)
世間は社会ではなく、自分が加わっている
比較的小さな人間関係の環なのです(同書)。
長期化の背景にある「世間」とは、“世間の目”です。
相談機関に足を運ぶまでに、
事態が起こって一年以内ということはまれです。
だいたい数年を経過しています。
数年前に一度当協会に相談に来られ、再訪されるケースもあります。
一度足を運んだだけで、具体的な解決行動まで踏み出せず、
さらに期間が過ぎての再訪です。
もちろん、事態がさらに深刻化したために、
切羽詰って来られたわけです。
世間体の回避
なぜこのように、解決のための具体的な行動に出るまでに
時間を要するかというところに「世間の目」つまり、
世間体がかかわってくるのです。
もちろん子どもが学校に行き渋りだしたり、
部屋に閉じこもりがちになっても、
しばらくは様子をうかがっているものです。
しかし、「どうもこれはただ事ではないな」と思い出してからでも、
なかなか動き出せないものです。
「うちの地域じゃ、離婚だって話せないぐらいです」
「親戚にすら黙っています」
親から「出歩くな」と言われたひきこもり青年からの話もありました。
実の姉にも10年以上の妹のひきこもりを黙っていた母親もいました。
これらはすべて「世間体」を考えてのことです。
全国組織のひきこもり親の会の提言にも以下のような内容がありました。
『引きこもりを形態としてとらえると「世間体」が悪く隠し
そのことに因り、内在化させ深め、エンドレスの悪循環に陥る。
身体で例えれば“肺炎”だよと病状と割り切り解釈すれば
「世間体」も悪くなく、病気なのだから、施療に取組み回復へ向かい、
中間施設や社会参加への道が開かれる。
これが欧米での世界標準のやり方だ。
日本の全関係者もそろそろ腹をククッテ行こう!』
いかがでしょうか?
あなたをこの提言をどうとらえられますか?
「そうそう、病気だったら世間体は保てるわ」とお考えですか?
肺炎ならまだしも、実際この団体が病名としてあげているのは、
気分障害(うつ)、社会恐怖症、強迫神経症、パニック障害、
PTSD、ADHD、摂食障害、躁うつ病、自閉症、広汎性発達障害、
統合失調症
と精神障害などのてんこ盛りです。
わが子が何かを思い煩っているだけで(病気でもないのに)、
世間体をごまかすために、これらの病気だからと割り切れますか?
「世間体」を気にするのは、先に例であげたように
日本人の民族性だと思いますので、
「一切気にしないこと」とまでは申しません。
私自身、何事にも「世間体」を一切気にしていないかと言いますと、
そう言い切れるほど自信はありません。
ただ、「世間の目」をはぐらかすために、
問題をすり替えてしまのは新たな問題を生じさせてしまい、
道が開かれるどころか危険ですらあります。
私が、病気ではなく長きに渡ってひきこもっていた
青年たちと対していて感じるのは、
彼らもまた、過剰に「世間の目」に怯えています。
これに関しては、当事者向けのブログで述べていますので、
こちらも読んでみられてください。
出世間の勧め
仏教用語で「世間」と合わせて「出世間」という言葉があります。
これは、“世間を超えた”といった意味です。
ですから、世間を無視するとか、否定するといった
ことではありません。
「世間体」をとりつくろうために問題をすり替えるのは、
無視や否定と同じです。
世間を超えるというのは、世間の通念をわきまえた上で、
次元を変えるという意味です。
常識という言葉で表現すれば、「出世間」というのは、
超常識ではあっても、決して非常識ではないということです。
私は、この「出世間」という考え方を勧めます。
たとえ「世間」の誤った誤解、偏見があったにせよ、
無責任な批評、風評に迷わされるのではなく、
わが子の何を守ってあげるべきかを
よくよく考えるということです。
わが身の「世間体」を優先させ、
わが子のこれからを粗末にしていないか。
わが子の成長と可能性を大切にするための行動を
選択していくことが世間を超えるということです。
近視眼的なとりつくろいの行動ではなく、
大局観でわが子の行く末を幸福にする行動をとることです。
「世間」の認識、理解の足りなさが分かれば、
世間の声の誤りにも寛容になれるはずです。
「世間」に申し開きが立たないことは、
世間への迷惑よりも自分の利益を優先させてしまう行為では
ないでしょうか。
それこそが、人目をはばかる行為です。
わが子の不登校、ひきこもりは、
決して人目ををはばからなければならないことではありません。
世間を超える出世間の視点をそなえるために良い方法をご提案しましょう。
「世間」に“さま”をつけてみてください。
「世間さま」です。
ニュアンスが違ってまいります。
「世間」に対してだったら、「ばつが悪い」という風に
なってしまいがちですが、
「世間さま」に対してでしたら、
「お天とうさまが見てござる」の如く、
畏れ畏(かしこ)み、天(世間さま)に恥じない行動という風になります。
天(世間さま)は、自分を生かし、支えてくださっている存在なのですから。
出世間を心がけてさえいれば、
無責任な「世間の目」に動じることはないのです。