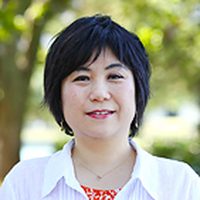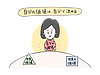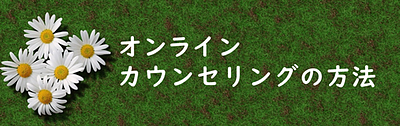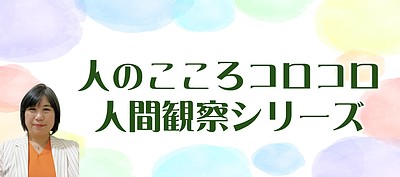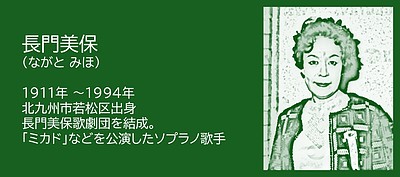雇用という考え方が無くなる時代になる

今日のお話は西島伊三雄氏(1923年~2001年)は、福岡生まれのグラフィックデザイナーであり童画家。
ハウス食品が販売する豚骨インスタントラーメン「うまかっちゃん」のパッケージデザインやネーミングでも知られています。
西島伊三雄氏の作品は、博多の文化や風景を描いたものが中心。
博多の文化や風景を描いたもので、福岡市民にとって馴染も多い作品を数多く残しています。
その生涯を振り返り、その人柄を通じて心の在り方を探ります。
光を描き続けた人生
1923年、福岡に生まれた西島伊三雄氏。
戦後の混乱期に「自分の描いたもので世の中を明るく照らしたい」との思いから。
観光ポスター、ロゴマーク、パッケージデザイン、イラストなど、多岐にわたる作品を制作。
西島伊三雄氏の作品は素朴でノスタルジックな童画や、誰が見てもわかりやすいロゴマークが特徴です。
博多の魂と共に
郷土愛に溢れる心意気は、博多どんたくや博多祇園山笠など、地元の祭りの広報普及にも尽力。
祭り用のうちわや手ぬぐいのイラストもボランティアで描いています。
そのことで、西島伊三雄氏作品は福岡の街にちりばめられ、今もなお愛されています。
デザインがもたらす希望
西島伊三雄氏の作品には、一貫したテーマがあります。
それは、「デザインを通じて社会を明るくする」という信念。
その一つに福岡市営地下鉄の各駅のシンボルマークのデザイン。
マークは地域の美化やまちづくりのきっかけとなりました。
病の床でも失わない創作意欲
病気療養中のベットの上で、西島伊三雄氏は地下鉄七隈線の駅のシンボルマークのデザインについて創作意欲は失われることはなく。
「夢のある自然路線」をテーマにしたマークを考え続け、長男の西島雅幸氏に語っていたそうです。
福岡市地下鉄七隈線のロゴへの思い
特に、福岡市地下鉄七隈線の「次郎丸駅」の蛍のロゴ。
病床の西島伊三雄氏は「昔はここ(次郎丸)にホタルがよう飛びよったと。今はホタルはおらんばってん、そんなら、いつかここにホタルが帰って来るごたあ~マークば作りやい」と長男の西島雅幸氏に伝えたそうです。
他にも「橋本駅」のもみじのマーク。
西島伊三雄氏が「将来、周辺にもみじをいっぱい植えてもらえるようなマークばつくりやい」と強く念を押したそうです。
それを聞いた長男の西島雅幸氏は、西島伊三雄氏の亡き後に、言葉を実現させ完成させています。
心に残る思い出
他にも、陶板作品があります。
勇壮な博多祇園山笠の絵が有田焼のタイルに直筆で描かれ、底辺約1メートルの三角形。
博多駅筑紫口で約40年間、待ち合わせ場所の目印だったピラミッド型の噴水塔がありました。
博多駅の再開発の際、塔は駅前広場の再整備で取り壊されることとなり保存会が動きました。
現在、その一部は、福岡市西区能古の「のこのしまアイランドパーク」に陶板作品が寄贈され、地域の文化財として大切にされています。
文化財となるものを古臭い、維持費がかかると思うのか?
保存会が動かなければ失われてしまう文化財は数多く。
福岡市は維持管理の観点から、すぐに壊してしまう。
そのことが私は残念でなりません。
文化は建物と共に生まれ育まれてていく。
建物が変われば、その文化を終わり、どんなに語り継がれようと忘れ去られるばかり。
つい先日も、北九州市の明治期の初代門司港駅(当時の名称は門司駅)関連遺構は、市が保存と移築を決めた機関車庫跡のわずか一部を除いて事実上の全面解体となっています。
長崎のように、文化と現代が融合できるように、なぜ考えられないのか。
大阪のように、文化財の保存のために指定管理企業を置いて、建物としての役割を担えるようにしないのか。
フランチャイズやチェーン店で地場の企業色が失われていくことに寂しさが募ります。
最後に
西島伊三雄氏は、温かく優しい心を持った人物。
デザインを通じて人々の心を温め、地元福岡を「明るく照らしたい」という強い願いが込められています。
病気療養中でもデザインへの情熱を失わなかった。
最後まで「夢のある自然路線」をテーマにしたシンボルマークを考案し続けています。
そんな自分にできることに打ち込んだ姿から私達は何ができるのでしょうか。
今もなお福岡の街に息づいているデザインを見るたびに福岡市の魅力って何だろうと考えてしまいます。
情報発信だけのこの働きしかできず。
無力感に心が痛くなることが多いんです。(苦笑)