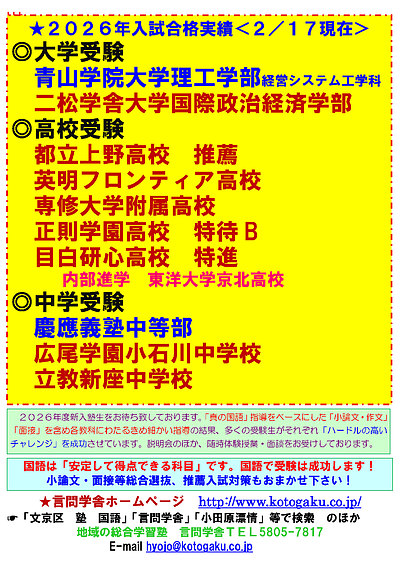三陸の鉄道に捧げる頌(オード)の完結作『志津川の海』を書きました!
今日8月21日は、私が敬愛し、先日来私自身が歌ったことをお伝えしている「長崎の鐘」「新しき」をお歌いになった藤山一郎先生のご命日です。今年で30年となりました。例年のことですが、言問学舎塾長ブログの記事を常体のまま転載させていただきます。
1993(平成5)年、8月21日。そのころ私は、当時勤めていた会社で転勤したため、名古屋に住んでいた。土曜日だったその日は、当日に藤山一郎先生がお亡くなりになっていたことを知る由もなかった。
週明けの月曜日に、新聞で訃報を知らされたのだと思う。ずっと藤山先生を「太陽のような存在」と仰ぎつづけていた私は、またその頃先生のご体調が芳しくないということを、陰ながら案じ申し上げていた。だから、永遠に来てほしくないと願っていた先生とのお別れの日が来てしまったことを、愕然としながら、かつ厳粛に受け止めた。
その日は豊橋の書店さんと、翌年分の配本の打ち合わせのアポイントがあったのだと思う。翌日の火曜日がご葬儀ということだったが、その火曜日に上京することはできない状況だった。ただ藤山家ではご自宅で弔問を受け付けて下さっているということも、あわせて報じられていた。名古屋から豊橋まで、わずかに東京方向に身柄を移動させていた私には、打ち合わせを終えて名古屋へ戻ることは、どうしても考えられなかった。
そこで豊橋から営業所に電話を入れ、その日の午後は半休を取って、昼過ぎに上りのこだま号で、東京へ向かったのである。地下鉄日比谷線で中目黒を過ぎ、東横線の祐天寺の駅前に降り立つと、慶応大学の学生さんたちが藤山家への案内に立ってくれていた。辻々に立つ学生服姿をたよりに藤山先生のご自宅へ向かう道すがら、頭の中では「東京ラプソディ」や「夢淡き東京」の先生のお声が、繰り返されていたように覚えている。
ご自宅に伺った頃は、夕闇が迫りつつあった。予想されたことだが、弔問客は多く、玄関から順に先生のお柩(ひつぎ)と祭壇に導かれるようになっていた。ご自宅の中へお邪魔した時から、CDかレコードで流されている先生の歌声が聞こえていたが、感極まってお柩の前まですすみ、お顔を拝した時には「懐かしのボレロ」がかかっていた。その時の先生の歌声は、30年経った今日も、あざやかに思い出される。
当時所属していた歌誌「歌人舎」平成5年11月号に追悼文を書かせていただいたのだが、そのうちの2か所を引用させていただきたい(引用は再掲した歌文集『わが夢わが歌』より)。
<先生の至言に、歌は正三角形でなければならないというお言葉がある。作曲、作詞、表現(歌い手)の三者が均等の力を持って対峙する、その緊張の上にのみすぐれた歌が成り立つのだというものである。同じく古関裕而、サトウハチロー、藤山一郎の見事な正三角の調和によりもたらされたのが、『長崎の鐘』(昭24)であろう。(後略)>
<(前略)たくさんの歌が脳裏をめぐってやまなかったが、新幹線が東京を離れるころ、ひとつの言葉がようやく私の心をまとめあげた。「長い間、ほんとうに、ありがとうございました」と。われわれが嘆き悲しむことを、決して先生はお望みにならないだろう。すべては私のこれからの、生きてある生き方においてお応えしてゆくほかはない。それだけが、今の私の唯一無二の心境なのである。>
あれから30年。はなはだ畏れ多いことではあるが、先日私はその「長崎の鐘」と、永井隆博士の短歌に藤山先生ご自身が曲をつけられた「新しき」とを歌わせていただき、新刊の音読DVDに収録した上YouTubeでも公開させていただいた(2023年9月19日まで。JASRAC、日本コロムビア許諾済)。
あわせて新刊に長崎および広島の原爆のこと、戦没学徒のことを書いたのは、これからの時代を生きる子どもたちに大切なことを知って欲しいと願う教育者としての思いに加え、この時の私自身の「生きてある生き方においてお応えして」ゆきたい、と願った誓いを実現するためでもある。もちろんそれは今回限りのことでなく、今後も生涯通して子どもたちに大切なことを伝え、教えつづけてゆくことを改めてお誓いし、お亡くなりになって30年となる今日のこの文の結びとさせていただきたい。
令和5(2023)年8月21日
小田原漂情