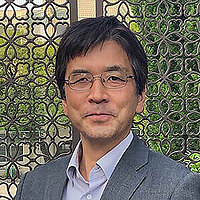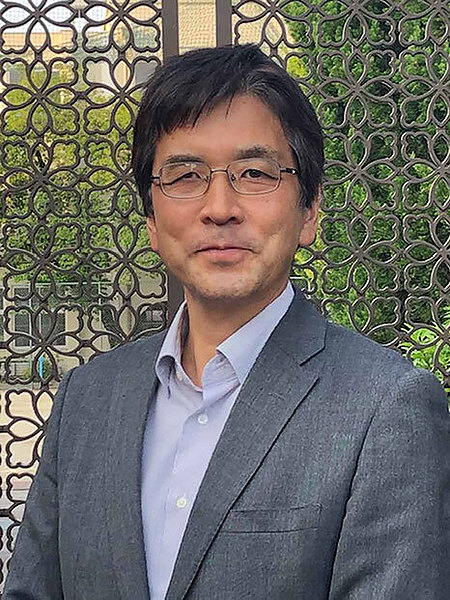放置空き家が招く損失とは(その2)
「認知症 自宅の処分難題」という見出しが、8月14日付の日経新聞夕刊の一面に出ました。住まいの終活に関連する記事は空き家問題が中心ですが、この記事は「認知症⇒資産凍結⇒空家増加」とつながり、我が意を得たりでした。しかも金融資産ではなく、資産凍結の対象を住宅(不動産)においたことも的を射ていると思いました。
記事によれば、認知症の人の所有する住宅は、2018年に210万戸、2021年に221万戸、2040年には280万戸に増えると試算しています(第一生命経済研究所による試算)。高齢者の高い持ち家率と認知症の高齢者の増加が背景にあります。高齢者以外の世代の持ち家率が50%に満たないのに対し、高齢者世帯の持家率は80%を超えています。一方、厚労省の試算では、2025年は高齢者の約5人に1人、2040年には約4人に1人が認知症になると見込まれています。
認知症により意思能力を失い、いわゆる意思無能力者になれば、有効な法律行為をすることが難しくなります。そのため所有する資産が凍結され、使用・収益・処分が制限されます。自宅を所有していれば、自宅の譲渡や建替え、また遺贈や相続などの継承にも支障がでます。被相続人であれば、遺産分割協議も成立しません。その結果、管理不全な空き家として放置されるリスクが高くなります。このようなリスクを内包する住宅予備軍が200万戸を超えているという事実は看過できません。
それでは私たちはどのように対応したら良いのでしょうか。
一つは、住まいの終活に早く着手することです。一旦、空き家になり時間が経過していけば、その関心は徐々に低くなり、その結果、問題先送りの状態が長期化する傾向があります。相続発生前がベストですが、遅くとも相続発生後1~2年がベターです。しかし一方で、いつ認知症になるかの予測は不可能です。よって、「元気なうちの早めに」ということになります。そして同時に、遺言、生前贈与、任意後見制度、家族信託制度、死後事務委任契約などの既存制度を上手に使って、認知症への備えを事前にしておくことです。
長寿社会は認知症患者の増加は避けることはできません。ご自身や親が認知症になり、自宅の円滑な承継が進まなくなるリスクを十分に想定しておかなければなりません。しかし、このような現状が十分に認知されているとは思えません。更には、各制度の専門家が各々の制度を説明するより、任意後見制度や家族信託制度などを住まいの終活のフレームワークで説明する方が理解しやすいのではないかと思います。そのため行政や消費者団体は、認知症と自宅を含めた不動産の処分や活用への影響に関する消費者教育をもっと推進すべきです。超高齢社会では決して他人事ではありません。