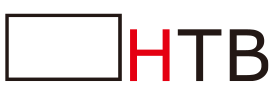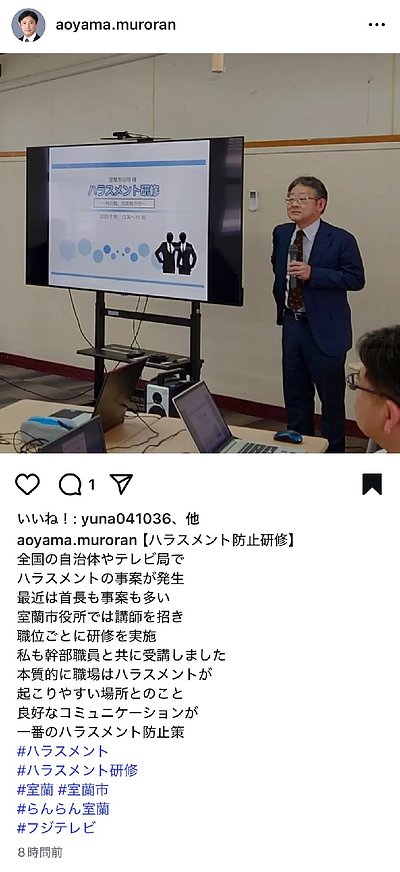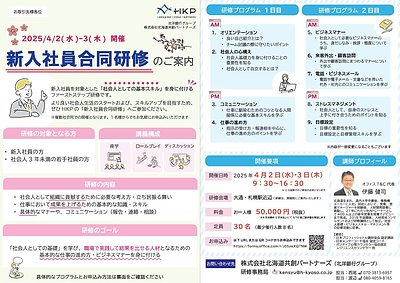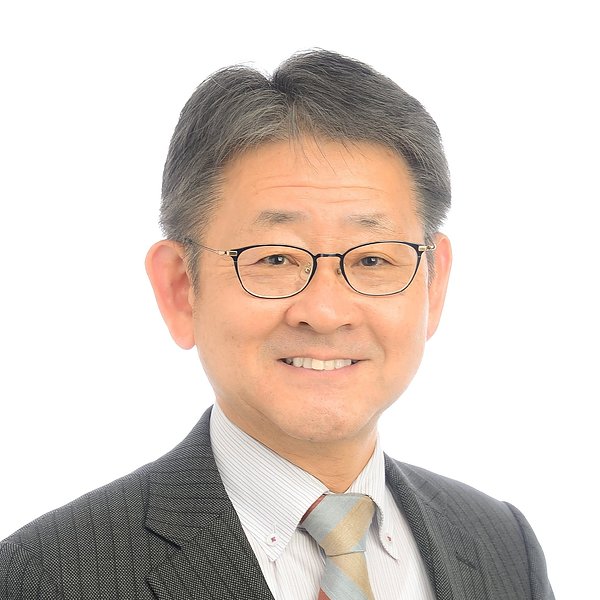職場のコミュニケーションを円滑にするコツ
先日、札幌市様からの委託を受け、「アンコンシャス・バイアス研修」に登壇する機会がありました。
札幌市様では現在、年齢、性別、国籍、民族、障がいの有無を問わず、「誰もが互いに個性や能力を認め合い、多様性が強みとなる社会(共生社会)」の実現に向け、ユニバーサルプロジェクトを展開されています。今回の研修も、その一環として、意識の醸成を目的に企画されたものです。
「アンコンシャス・バイアス」とは?
「アンコンシャス・バイアス」とは、日本語では「無意識の偏見」と訳されることが多い言葉です。「アンコンシャス(unconscious)」は「無意識」という意味ですが、「バイアス(bias)」は「かたより」を指します。そのため、「偏見」ほどの強いネガティブな意味ではなく、「偏ったものの見方」「100%中立ではない視点」程度に捉えるのが適切かもしれません。
私たちは、何かを認識するとき、過去の経験や自分の常識と照らし合わせて、「あてはめて」理解しようとします。例えば、目の前に真っ赤なスープのラーメンが出てきたら、「きっと辛いに違いない」と考えます。スーツを着た人を見かけたら「会社員だろう」、幼い子どもと一緒にいる女性を見たら「お母さんだろう」と、無意識に「あてはめて」認識します。
こうした思考は、日常生活で役に立つことも多いですが、特定のイメージに固定されすぎたり、重要な判断の根拠としたりすると、問題が生じることがあります。
典型的な例として、「男性はこうだろう」「女性はこうだろう」といった性別に関するステレオタイプがあります。これは時に「男性はこうあるべき」「女性はこうあるべき」といった、思い込みや押しつけになってしまうこともあります。
他にも、「若者はデジタルに強いだろう」「高齢者は新しい技術が苦手だろう」といった年齢によるバイアスや、「日本人は〇〇」「外国人は△△」といった国籍・人種に関するバイアス等々……。
特に対人関係におけるバイアスは、差別や人権侵害につながる可能性もあります。
不都合を生み出すアンコンシャスバイアスを減らそう
そこで今回の研修では、ご自身の業務を振り返りながら、「リスクにつながる可能性のあるアンコンシャス・バイアスには、どんなものがあるか?」「不都合を生み出すアンコンシャスバイアスを減らすために、どんな取り組みができるか?」についてグループで意見交換していただきました。
アンコンシャス・バイアスは、誰にでも存在します。大切なのは、それを自覚し、自身の言動を振り返る機会を意識的に持つこと。他者からのフィードバックを求め、受け入れること。そして、判断を下す際に「自分が相手の立場だったらどう感じるか?」「他の人ならどう考えるか?」といった視点を持つことです。
私自身も、この研修を通じて改めて意識を深めることができました。これからも、自分のバイアスに気づき、より公正な視点を持てるよう努めていきたいと思います。
「アンコンシャス・バイアス研修」お客様の声
https://mbp-japan.com/hokkaido/office-tc/voice/5006229/