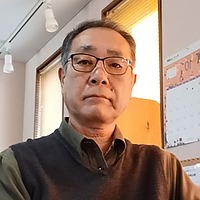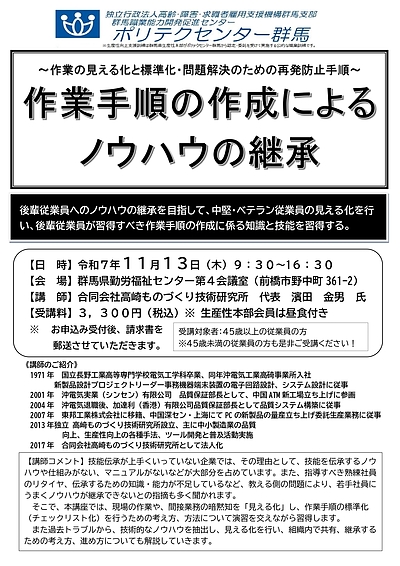在庫は悪と言われているが、それはなぜか?貸借対照表では、資産として扱われているが!
1.スループット会計の概要
スループット会計は、エリヤフ・ゴールドラット博士が提唱した制約理論(Theory
of Constraints:TOC)に基づいた管理会計の手法です。
従来の原価計算とは異なり、企業の目的を「お金を儲けること」と明確に捉え、その
目的達成を最大化するための意思決定を支援することを主眼としています。
★無料ものづくりネット相談・お問い合わせフォーム
(伝統的原価生産手法では儲からない、スループット会計、損益分岐点分析
など多品種少量生産に適合した原価計算方式をマスターしよう!)
2.スループット会計の基本的な考え方
スループット会計では、企業全体の生産プロセスにおけるボトルネック(制約)を特定
し、その制約を最大限に活用することで、より多くのお金を稼ぎ出すことを目指します。
(1)スループット会計の主要な指標
スループット会計では、主に以下の3つの指標を用いて業績を評価し、意思決定を行い
ます。
●スループット(Throughput:T)
定義: 販売を通じて企業に入ってくるお金の速度。具体的には、売上高から変動費(主に
材料費)を差し引いたものです。
重要性: スループットは、企業がどれだけ効率的に価値を生み出し、顧客に提供できて
いるかを示す最も重要な指標と考えられます。
●投資(Inventory:I):
定義: 企業が販売するために保有している全てのお金。具体的には、原材料、仕掛品、
完成品などの在庫、設備、不動産などが含まれます。
重要性: 投資は、企業がお金を眠らせている状態を示すため、できる限り少なくする
ことが望ましいと考えられます。
●業務費用(Operating Expense:OE):
定義: スループットを生み出すためにかかる全てのお金。具体的には、人件費、光熱費
減価償却費、間接費などが含まれます。
重要性: 業務費用は、スループットを生み出すために必要なコストであり、できる限り
少なくすることが望ましいと考えられます。
(2)スループット会計による意思決定
スループット会計では、上記の3つの指標に基づいて、以下のような意思決定を行います。
●スループットの最大化: 制約となっているリソースの能力を最大限に引き出す方法を
検討します。例えば、制約工程の作業時間を短縮したり、不良品を減らしたりすること
が考えられます。
●投資の最小化: 不要な在庫を削減したり、設備の購入を慎重に検討したりすることで、
投資を抑えます。
●業務費用の最小化: スループットに直接貢献しない業務費用を削減する方法を検討します。
(3)従来の原価計算との違い
スループット会計は、従来の原価計算とはいくつかの点で大きく異なります。
●直接労務費の扱い: 従来の原価計算では、直接労務費は製品原価の一部として扱われ
ますが、スループット会計では、多くの場合、業務費用として扱われます。これは、現代
の製造業においては、直接労務費が製品の生産量に比例して変動するとは限らないという
考えに基づいています。
●間接費の扱い: 従来の原価計算では、間接費は様々な配賦基準に基づいて製品に配賦
されますが、スループット会計では、間接費は原則として業務費用として一括して扱わ
れます。
●在庫の扱い: 従来の原価計算では、在庫は資産として評価されますが、スループット
会計では、在庫は「お金が眠っている状態」と捉えられ、できる限り少なくすることが
重視されます。
例えば、ある工場で製品Aと製品Bを製造しているとします。
●従来の原価計算の場合
製品Aと製品Bそれぞれに、直接材料費、直接労務費、そして配賦された間接費を合計
した製品原価を計算します。
製品ごとの利益率を算出し、利益率の高い製品に注力するといった意思決定を行います。
在庫は資産として評価され、過剰な在庫も必ずしも悪いとは限りません。
●スループット会計の場合
製品Aと製品Bの売上高から直接材料費を差し引いたものがスループットとなります。
工場全体の従業員の給与や光熱費などは業務費用として一括で管理されます。
在庫はできる限り少なくすることを目標とし、制約となっている工程を特定し、その
工程の生産性を向上させることに注力します。
例えば、製品Aの製造工程にボトルネックがある場合、製品Bの利益率が高くても、
まずは製品Aのボトルネックを解消することを優先します。なぜなら、ボトルネック
が解消されない限り、全体のスループット(お金を儲ける速度)は向上しないからです。
なぜこのような違いが生まれるのか?
従来の原価計算は、製品ごとの正確な原価を把握することに重点を置いてきました。
これは、大量生産の時代において、製品の多様性が少なく、比較的安定した環境下
では有効でした。
しかし、現代のように市場の変化が激しく、多品種少量生産が主流となる中で、従来の
原価計算は以下のような課題を抱えるようになりました。
●配賦の恣意性: 間接費の配賦基準は必ずしも客観的ではなく、経営判断によって左右
されることがあります。
●誤った意思決定: 製品ごとの利益率だけを見て意思決定を行うと、全体のスループット
を低下させる可能性があります。例えば、ボトルネック製品の生産を抑えて、利益率の
高い製品ばかりを作っても、最終的な販売量が伸びなければ意味がありません。
●複雑性: 製品の種類が増えるほど、原価計算が複雑になり、時間とコストがかかります。
スループット会計は、このような従来の原価計算の課題を克服するために生まれました。
企業の目的を「お金を儲けること」と明確にし、その目的達成を阻害する要因(制約)
に焦点を当てることで、よりシンプルで効果的な意思決定を支援します。
どちらの手法が優れているか?
どちらの手法が優れているかは、企業の状況や目的によって異なります。
●従来の原価計算: 製品ごとの詳細な原価情報を必要とする場合や、長期的な価格設定
戦略を立てる場合には有効です。
●スループット会計: 短期的な利益向上を目指す場合や、生産プロセスのボトルネック
を解消したい場合には有効です。特に、制約理論(TOC)を導入している企業にとって
は、スループット会計は非常に有効なツールとなります。
多くの企業では、それぞれの会計手法のメリットを理解し、状況に応じて使い分ける
ことが望ましいと言えるでしょう。
3.スループット会計のメリット
●シンプルで理解しやすい: 主要な指標が少なく、考え方がシンプルであるため、経営
層から現場の従業員まで理解しやすい。
●短期的な意思決定に役立つ: 制約に焦点を当てることで、短期的に効果の出やすい
改善策を見つけやすい。
●部門間の対立を解消しやすい: 企業の目的を「お金を儲けること」と明確にすること
で、部門間の協力体制を築きやすい。
4.スループット会計のデメリット
●長期的な意思決定には不向きな場合がある: 短期的な視点に偏る可能性があるため、
長期的な戦略立案には注意が必要。
●状況によっては詳細なコスト分析が必要になる: 全ての状況においてスループット会計
が最適とは限らず、場合によってはより詳細なコスト分析が必要となる。
まとめ
スループット会計は、制約理論に基づいた実践的な管理会計手法であり、企業の目的
達成を最大化するための強力なツールとなります。ボトルネックの特定と活用に焦点を
当てることで、効率的な経営と利益向上に貢献することが期待できます。