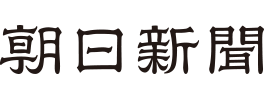マナーだけではない「ながらスマホ」の危険
人それぞれの意識や感情と事件の真実
近年、犯罪被害者やその家族の「知る権利」が注目されるようになりました。今日までの日本では「復讐」の概念から、新たな犯罪を防ぐ目的で、被害者や家族への告知を避けてきました。これは、犯罪プロセスの起点を絶つ考え方で、無益な犯罪を減らす手法として、非難されるものではないと考えます。しかし、想像を超えた出来事に直面した時、真実を知りたいと切望することも当然と言えます。また、真実を拒絶したい悲しみもあるでしょう。人の意識や感情は、知識や性格だけではなく、環境や条件でも異なり複雑に絡み合っています。日頃真面目な人が凶悪な犯罪を起こす、温厚な人が被害に遭うなど、こうすればこうなるという常識はありません。目を覆い、耳を塞ぎたくなる事件の報道が増え、不安を感じる人、関わらない(無関心)人、当事者以外も様々です。しかし、犯罪を防ぐ観点から、私たちは犯罪と向き合い、真実を知るべきか否か、結論を出すべき分岐点に立たされているのではないでしょうか。
被害者に対する考え方の移り変わり
日本には古来「仇討」という「復讐」を正当化した習慣があり、心を打つ出来事として語り継がれている事件(赤穂浪士など)もあります。明治維新とともに「仇討」は廃止され、人命を尊ぶ思想に変化しました。そして、第二次世界大戦以降「被害者学」が誕生し、被害者の立場や心情が考えられるようになりました。しかし、被害者には事件の有責性(ケンカ両成敗)が指摘され、様々な我慢が求められると同時に非難の対象にもなっていきます。また、加害者の責任を審議する刑事裁判の場でも、犯罪を立件する証拠の一部として採用されることが殆どでした。1960年代には、被害者の有責性を問いかねる場当たり的な犯罪の増加がきっかけで、世界的に被害者の悲惨さが注目されるようになりました。日本でも70年代に被害者保護制度が導入されることで、徐々に被害者の立場や心情に注目が集まるようになります。現代では、警察や検察の処理結果を伝える「通知制度」をはじめ、優先的に裁判を傍聴でき、被告人質問のできる「被害者参加制度」など様々な形で被害者の保護が始まりました。
真の被害者保護とは寄り添うこと
このような犯罪被害者の保護制度は、怒りや悲しみなど感情を補うものだけではありません。真実を知り、受け入れ、立ち直る機会を作るものでもあります。犯罪被害の苦しみは、本人にしか解らない、計り知れないものです。「仇討」という習慣から「有責性」の観点、加害者を処罰するための「証拠」と言った時代を経て、犯罪被害者に対する考え方は時代と共に変化しています。そして、犯罪の凶悪化、惨忍性が進んでいる裏付けでもあります。犯罪には、加害者と被害者が存在し、双方が同じ人であることを忘れてはいけません。加害者が自分と同じ人であることで、被害者の憎しみや悲しみを増大させていることも否めません。しかし、深い憎しみや悲しみを解決できるのは、被害者や家族の本人だけです。悩み、苦しみ、葛藤を乗り越え、平穏を取り戻すまで「寄り添う」ことが、犯罪という非日常に直面した、犯罪被害者の真の保護です。そして、私たちは犯罪と向き合い、真実を知ることで、犯罪被害者に寄り添い、自身が犯罪被害者にならないことが重要です。