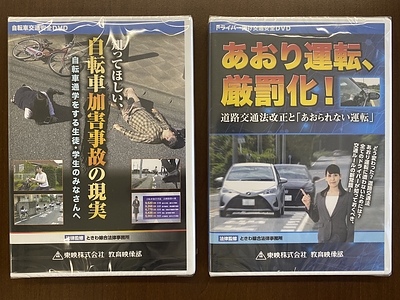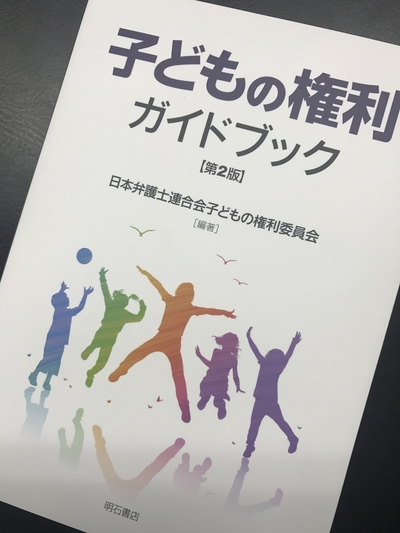父親や専業主婦でも得られる、離婚における親権の獲得について
離婚を決めるには、その夫婦ごとにさまざまな理由が挙げられることでしょう。
しかし裁判などで離婚が認められるためには、民法に定められた離婚理由に該当していることが必要となります。
ここでは、その各要件を個別の事例とともに紹介していきます。
裁判などの第三者が介入する離婚では、明確な理由が必要
夫婦間の話し合いのみによって離婚に至ることを協議離婚と呼び、日本における離婚件数の大多数を占めています。この場合、両者が合意の元で離婚届を提出する訳ですから、理由の如何を問わず離婚は成立することとなります。
しかし、夫婦のどちらか一方が離婚を望んでいるのに、もう片方がそれに応じないというケースもあります。
協議による離婚がまとまらなければ、調停(家庭裁判所での話し合いの仲裁)・審判(家庭裁判所での離婚の審議)、そこでも離婚合意に至らなければ裁判に訴えることになります。調停・審判・裁判という第三者介入の段階においては、離婚という結論に至った理由が、民法の定めによる離婚理由に該当するか否かが問題となります。そこに該当しない場合、離婚という結論に至るのは難しいと考えられます。
正常な夫婦関係の妨げとなる「不貞行為」と「悪意の遺棄」
では民法が定める離婚理由とは、どのようなものがあるのでしょうか。具体的には、以下に挙げる要件が該当します。
まず挙げられるのが、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶという、「不貞行為」です。一般的に浮気や不倫と呼ばれる行為であり、その期間が長いほど離婚の理由として強固なものになります。
次に挙げられるのが、「悪意の遺棄」と呼ばれる行為です。これは、夫婦生活を営む上での同居義務・協力義務・扶助義務に違反することであり、意図的に働かない、収入があるにも関わらず生活費を出さない、明確な理由なく同居を拒否するなどの行為が該当します。
ただし、夫婦双方が合意した上での別居(単身赴任など、やむを得ない場合を含む)であったり、既に夫婦関係が破綻した後の別居の場合は、悪意の遺棄は認められません。
配偶者の状況によって離婚が認められることもある
3年以上に渡って配偶者の生死が不明な場合も、民法の定める離婚理由に該当します。ここでは「生死を確認できないこと」が重要であり、たとえ所在が不明であっても生きていることがわかっている(何らかの形で連絡があるなど)場合は、この事由には該当しません。
配偶者が回復の見込みのない重度の精神疾患にある場合も、離婚理由として認められることがあります。この場合は、献身的な介護を施した上で、なお夫婦生活への協力義務が果たせるまでに回復する見込みのないことが重要です。
また、精神疾患にある配偶者が、離婚後に継続して看護・療養が受けられるであろうという保証も、離婚が認められる前提条件となります。
このほか、配偶者による暴力・虐待行為、親族との不和、多額の借金、長期のセックスレスなどは、「婚姻を継続し難い重大な事由」として、個別の事情を鑑みて離婚理由に認められることがあります。