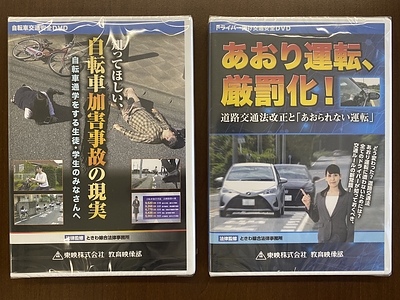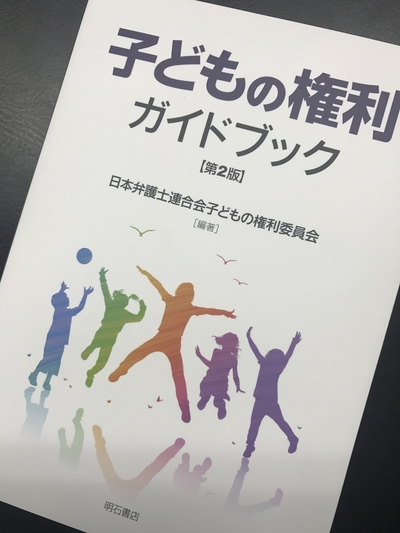相続人の優先順位の決め方、法定相続人の範囲と順位について
被相続人の遺言書によって、法定相続人以外の第三者に財産を遺贈することができます。
しかしその場合であっても、法定相続人である配偶者・子どもには、遺留分とよばれる割合が保証されています。
遺留分の計算方法を含め、遺言にまつわる知識として紹介します。
どのような遺言書があっても、法定相続人には遺留分が保証されている
財産を相続する場合、被相続人(相続をする人)の配偶者・子ども(ケースによっては父母)が法定相続人となり、そのまま受け継ぐことが通常の流れです。
一方で、被相続人の意思を尊重するため、法令に則った形の遺言書を作成しておけば、特定の第三者(知人や法定相続人にならない親族など)に財産を遺贈することもできます。
しかし、このような遺言書があった場合であっても、法定相続人は一定の割合で財産を受け取る権利を有しています。この最低限受け取ることのできる財産が遺留分と呼ばれるもので、残された配偶者・子どもなどの家族が生活に困らないようにという配慮のもと、民法で保証されています。
全財産のうち、遺留分を除いたものが、被相続人の意思によって自由に処分(遺贈など)できる割合となります。
被相続人の配偶者と子どもの遺留分は、全体の1/2が計算のベース
通常、被相続人の配偶者と子どもが遺留分の権利を持つ法定相続人となります。被相続人に子どもがない(先に死亡しているなども含む)場合、被相続人の父母も遺留分が認められます。被相続人の兄弟・姉妹には、遺留分は認められていません。
遺留分は、まず全体の1/2が基準となって確保されており、法定相続人の続柄によって割合が算出されます。法定相続人が配偶者のみの場合、遺留分は全財産の1/2(遺留分の全て)です。
法定相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者は1/4(1/2×1/2)、子どもは1/4となります。子どもが複数人いれば、その1/2をさらにその人数で分けることになります。
被相続人に子どもがなく、父母が健在の場合、配偶者は2/6(1/2×2/3)、父母が1/6となります。配偶者がなく、子どものみの場合は1/2を人数で割り、父母のみの場合は全体の1/3が遺留分として計算されます。
遺留分が侵害されている場合は、侵害している相手側に直接請求する
遺言書によって遺留分が侵害されている(遺留分として認められている額未満しか受け取れていない)場合、上記の遺留分を認められた法定相続人は、遺言書によって相続した人に対して遺留分を主張し、請求することができます。これを「遺留分減殺請求」と呼びます。
遺留分減殺請求は、相続開始かつ遺留分の侵害を知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手側に行います。
具体的に決められたルールはありませんが、請求を明確にすべく、個別に内容証明郵便などで請求する方法が一般的です。
侵害している側がこれに応じない場合、家庭裁判所に調停や審判、裁判を行うことができます。仮に相続開始を知らずに遺留分が侵害されていたとしても、相続開始から10年で遺留分減殺請求の権利は失効します。