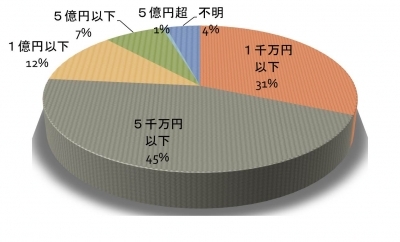自筆証書遺言の「検認」とは?
例えば、「私が死亡したら、自宅は長男に遺贈する。その代わりに、年老いた母さん(遺言者の妻・受遺者の母)の介護をすること。」といったように、遺言で財産を誰かに与える際に、その見返りとして「もらう側(受遺者)」に一定の法律上の義務を負担させることを「負担付遺贈」といいます。
負担付遺贈の例としては、他にも「自宅を遺贈するので、住宅ローンの返済を引き受けること(この場合は債権者の同意が必要)」「預貯金を遺贈するので、障害を抱えた三男の面倒をみること」という例があります。さらに、遺言者の配偶者が認知症などで財産管理能力が無く、配偶者自身に不動産や預貯金を相続させられない場合、息子や娘に不動産や預貯金などを相続させた上で、「母親を引き続き自宅に住ませる(使用貸借)」義務と、「母親に生活費として毎月5万円を支払う」という義務を負担させるという利用方法もあります。
ただし、負担付遺贈の負担はあくまで遺贈とセットでなすべきものなので、遺贈をしないで負担だけを課すことはできません。そのため、「長男は、受取生命保険金のうちの500万円を、二男に支払う」という負担は課せません。なぜなら、生命保険金は保険契約に基づいて長男が保険会社から直接受け取る固有の財産であり、親から遺贈により取得する財産ではないからです。
なお、負担付遺贈の相続税法上の取り扱いですが、「負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における当該財産の価額から当該負担額(当該遺贈のあった時において確実と認められる金額に限る。)を控除した価額によるものとする。」とされています。
この負担付遺贈は、包括遺贈(第36首参照)、特定遺贈(第37首参照)のいずれの場合でも可能です。ただし、遺贈を受けた財産の価額がわずかなのに、負担が重すぎるという場合もありえます。そのため、民法1002条では「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。」とされています。例えば、500万円の遺贈がなされた際の負担として毎月5万円を仕送りするような場合、仕送りの合計額が500万円に達した時点で、負担は終了となります。
また、全財産の負担附遺贈を受けたものの、本来の相続人からの遺留分減殺請求を受け、受け取った財産の一部を引き渡したような場合には、その目減りした財産の額に応じて、負担の割合も減少します(民法1003条)。
なお、負担付遺贈の受遺者は、遺贈を放棄することもできます。その場合、通常の遺贈では、受遺者が遺贈を放棄すると、受遺者がもらうはずだった財産は相続人のものになるところ、負担付遺贈では、「負担の利益を受けるべき者(受益者)は、自ら受遺者となることができる。」とされています。つまり、冒頭の例で、長男が遺贈を放棄すると、遺言者の妻が遺贈を受けることができます。そして、この場合、「介護をすること」という負担の部分については、妻が自分で自分の介護をする形になるために消滅し、単なる遺贈となります。ただし、遺言者がその遺言で別段の意思表示をしたときは、その意思に従います(民法1002条2項)。
では、負担付遺贈の受遺者が、財産はしっかりといただいて、負担はサボっている場合にはどうなるでしょうか? このような場合には、民法1027条で「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」と定められています。
ただし、このような場合でも遺贈そのものが直ちに無効になるわけではありません。そのため、例えば負担として定められた親の介護をサボっている受遺者から、「遺言で定められたとおりに、自宅をオレに引き渡せ」と求められた場合、相続人は「オマエは遺言で定められた親の介護をサボっているではないか」という理由で遺贈の履行請求を拒否することはできません。したがって、このような場合には、自宅をいったんは受遺者に引き渡した上で、あらためて家庭裁判所に遺言の取消しを請求することになります。
このように、負担付遺贈では、誰に何を遺贈し、どのような負担を課すのかはとても重要です。したがって、負担付遺贈をする場合には、遺贈者と受遺者との間で事前に十分話し合っておくことや、負担がきちんと履行されるかを見守るために、遺言執行者の指定をしておく方が安全といえます。