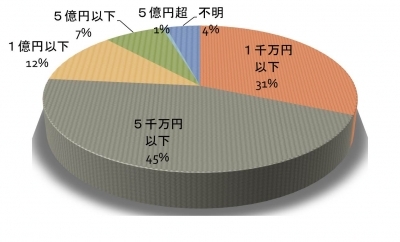遺された母の面倒をみるなら遺産を与えるという遺言は有効か?
今回もコレクションの承継についてのお話です。ただし、前回は「欲しくないものの遺贈を受けた場合」でしたが、今回はその逆で「欲しいものの贈与を受けられなかった場合」についてです。
さて、前回は「死因贈与(しいんぞうよ)契約」について少し触れました。「死因贈与」というのはあまり聞き慣れない言葉だとは思いますが、例えば、「私が死んだら、私が集めていた骨董品を、すべてあなたに譲ります」というような契約を、生前に「あげる側(贈与者)」が「もらう側(受贈者)」との間で契約しておくことをいいます。
この「死因贈与」については、民法554条で「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」とされています。つまり、死因贈与も「あげる側」の死亡によってその財産が「もらう側」に移る点では遺贈と同じなので、原則として遺贈と同様に扱うものとされています。ただし、遺贈は遺贈者が生前に受遺者に財産を与える旨を通知したり、承諾を得たりする必要のない単独行為であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者との間で生前にあらかじめ契約しておくものであるため、その性質上、以下のような取り扱いの違いがあります。
(遺贈と同様に扱われる規定)
・遺言者の死亡により効力が発生する。
・遺贈が効力を生じない場合や放棄された場合、受遺者が受ける
べきであった財産は相続人に帰属する。
・遺言執行者を定めることができる(判例・実務)。
(遺贈と同様には扱われない規定)
・遺贈は15歳から可能であるが、死因贈与は契約なので、原則
として20歳以上から可能。
・遺贈は遺言で定めるため自筆証書遺言、公正証書遺言などの要
式を守る必要があるが、死因贈与では必ずしもそのような要式
は求められない。
・遺贈の承認や放棄に関する規定は死因贈与には適用されない
(第37首参照)。
・死因贈与契約書は、贈与者の死後に検認を受ける必要がない。
・不動産の死因贈与については、贈与者の死亡前に仮登記をする
ことが可能。
(遺贈と同様に扱われるかについて意見の対立があるもの)
・遺言者(贈与者)の死亡以前に受遺者(受贈者)が死亡したと
きの遺贈(死因贈与)の効力。→通説では「生じない」
(第18首参照)。
・遺言の撤回・取消しに関する規定。
ここで、今回取り上げるのは撤回、すなわち「あげようと思っていたけど、やっぱりやめた」という場合です。遺贈の場合、遺言は遺言者が生きているうちは何度でも書きかえることができる(第26首参照)ため、原則として自由に撤回できます。しかし、死因贈与の場合は、生前に贈与者と受贈者の双方が合意して契約しています。契約である以上、贈与者の気が変って一方的に契約を破棄して他の人にその財産を贈与したり、他の人にその財産を遺贈する旨の遺言をしたりしてもいいのかという問題があります。
この点については、法律の学者さんの間でも、死因贈与も遺贈と同じように贈与者の最終の意思を尊重すべきなので、いつでも撤回できるという意見と、死因贈与はあくまで契約であり受贈者の側の「もらえる」という期待権を保護すべきなので、贈与者が一方的に撤回することはできないという意見があり、対立しています。この点、判例では「遺言の撤回に関する規定を準用する」、すなわち「いつでも撤回できる」という意見に基づいたものが多いようです。ただし、遺言の撤回は遺言の方式で行わなければなりませんが、死因贈与にはこのような形式面での制限はありません。
ということは、「私が死んだら、私がこれまで集めてきたコレクションは、すべて君に譲る」という内容の死因贈与契約書を作成して双方で署名押印をした場合でも、贈与者の気が変れば、この契約を撤回してコレクションを他の人に贈与したり、他の人に贈与する遺言をしたりすることができてしまいます。結局「タダでもらえるものは、あてにしてはいけない」ということですね。
ただし、「私が死んだらこの骨董品を譲るので、それまでは私の介護をして欲しい」というように、受贈者の側にも一定の負担があり(負担付死因贈与契約)、受贈者がその通りに介護を行っているような場合は、贈与者の都合だけで死因贈与契約を一方的に撤回することができないこともあります(判例)。まあ、この場合には、ある意味「タダでもらえる」とはいえませんからね。