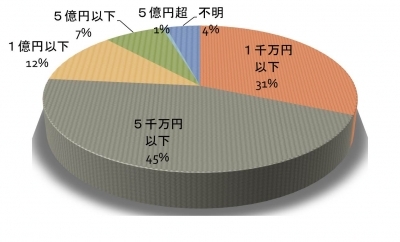「遺言信託」の費用は遺産から差し引けるか?
認知症や知的障碍などの理由で判断能力(事理弁識能力)が不十分な人は、自分では不動産や預貯金などの財産を管理したり、事業者と介護などの契約をしたり、遺産分割の協議をしたりすることができない場合があります。また、契約の内容が判断できずに、悪質商法の被害に遭うおそれもあります。
そのため、このような人が単独で有効な契約などを行う能力(行為能力)に一定の制限を加えるとともに、その人を代理して契約などの法律行為を行い、またはその人が行う法律行為に同意を与える者を選任する制度が成年後見制度です。成年後見制度には、家庭裁判所の審判による法定後見と、本人の判断能力が十分なうちに本人自らが候補者と契約をしておく任意後見とがあります。
法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて、3つの類型があります。
(1)成年後見:判断能力を「常に欠く状態」にある者
→本人を「成年被後見人」として「成年後見人」が支援します。
(2)保 佐 :判断能力が「著しく不十分」である者
→本人を「被保佐人」として「保佐人」が支援します。
(3)補 助 :判断能力が「不十分」である者
→本人を「被補助人」として「補助人」が支援します。
さて、成年被後見人・被保佐人・被補助人(制限行為能力者)が遺言をする場合、物事を理解する能力(意思能力)さえあれば、行為能力に制限があっても、本人が単独で遺言をすることができます(第27首参照)。一方、代理による遺言の作成は認められません。ただし、成年被後見人については、遺言をした時に意思能力があったことを証明するために、民法973条で以下の規定があります。
1.成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、
医師二人以上の立会いがなければならない。
2.遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理
を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押
さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記
載をし、署名し、印を押さなければならない。
なお、この規定は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のほか、特別方式の遺言でも準用されます(民法982条)。
また、成年被後見人(と15歳以上の未成年被後見人)が遺言をする場合、誰に財産を遺すかについても、一定の制限があります(民法966条)。
1.被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益と
なるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2.前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
遺言で誰にどの財産を与えるかは、基本的には遺言をする本人の自由です。もちろん、本人が普段お世話になっている後見人に本心から財産を遺贈したいという場合もありえます。しかし、後見人は本人の財布を握り、生活を管理する立場にあります。そのため、後見人がそのような立場を悪用して自己の利益になる遺言をするよう本人に圧力をかけたり、後見人が本人の財産を横領したことを隠蔽する目的で遺贈を受けたりするおそれがあります。また、後見人自身が遺贈を受けるのでは企みがミエミエなので、その配偶者や子に対して遺贈をさせるかも知れません。そして、そのような後見人の意図を立証することは非常に困難ですので、そのような遺言は一律に無効とされています。
もっとも、後見人が本人の直系血族(父母・祖父母・子・孫など)、配偶者又は兄弟姉妹である場合にまで一律に遺言を無効にすることは、法による干渉が過ぎ、人情にもとるという理由や、これらの者はもともと推定相続人となりえる立場であるという理由から、この制限は適用されません。
しかし、実際のところ後見人が本人の財産を横領する事件は、弁護士や司法書士が後見人に就任する「第三者後見」よりも、本人の子や兄弟姉妹が後見人に就任する「親族後見」の方が、数としては圧倒的に多いのです。そのため、
この例外規定については批判があります。
一方で、本人には配偶者も子供もなく、兄弟姉妹はいるが高齢などの理由により甥や姪が後見人を引受けている場合や、子の配偶者(義理の息子・娘)が後見人になっている場合、本人がその後見人に財産を譲りたいと思って遺言をしても、その遺言はこの条文では無効になってしまうという矛盾があります。したがって、これらの人に後見をしてもらうことを前提に財産を遺贈するには、本人が後見状態になる前に遺言や任意後見契約をしておく必要があります。