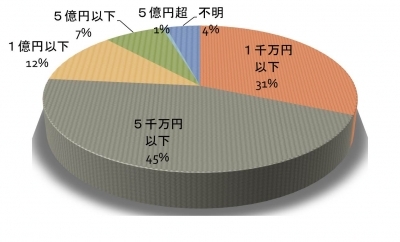遺された母の面倒をみるなら遺産を与えるという遺言は有効か?
前回の続きです。今回は、前回説明した「死亡危急者遺言」以外の3種類の特別方式の遺言について説明します。なお、いずれの方式の遺言についても、遺言者の死亡後には家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
○船舶遭難者遺言(難船危急時遺言:民法979条)
船舶が遭難した場合において、その船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます。イメージとしては、沈没しつつある船の乗員や乗客が、二人以上の証人に「私はもうダメだ、足を負傷して逃げられない。私の財産は、すべて私の妻に相続させると伝えてくれ。頼んだぞ。」という言葉を遺して、船と共に沈んでいくといった、かなり切迫した状況でなされる遺言の方式です。
一般危急時遺言とは異なり、遺言者から口頭で遺言の内容を伝えられた証人は、その場で筆記する必要はありません。また、筆記した遺言を遺言者や他の証人に読み聞かせたり、その場で署名押印したりする必要はありません。その意味では、かなり緩い方式の遺言ですが、これは考えてみれば当然で、船舶が遭難する場面では、遺言者と同様に証人も生命の危機にあります。ですので、口授→筆記→読み聞かせ→署名押印などという、悠長なことをしている状況ではないからです。
そのため、証人は安全なところに避難してから、記憶を頼りに遺言の趣旨を筆記して、他の証人とともに署名押印し、家庭裁判所に請求して、その確認を受けることになります。この確認の効力や内容等については一般危急時遺言と同様ですが、期間については、一般危急時遺言では「遺言の日から20日以内」となっていますが、船舶遭難者遺言では「遅滞なく」とされています。
しかし、問題は、そのような状況下で証人を引受けてくれる人がいるのか、また、仮に引受けてくれる人が見つかったとしても、その証人が無事に生還して遺言の筆記や確認などの手続きを行ってくれるかは、保証ができません。
なお、この形式による遺言は、遺言者が無事に救助され日本国内又は日本の領事が駐在する国に上陸(領事が公証人の役割を代行できるため)するなど、普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、その効力を生じません。
○一般隔絶地遺言(伝染病隔絶地遺言:民法977条)
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。この場合、遺言者が遺言を作成し、または誰かに代筆してもらい、遺言者と筆者、立会人および証人が、各自遺言書に署名押印を行います。
また、伝染病で隔離された者以外に、刑務所で服役中の者や災害で被災した者も、この方式で遺言をすることが可能です。その際、自筆証書遺言をすることが可能な場合であっても、この方式によって遺言をすることもできます。
ちなみに、警察官が立会人とされたのは、警察官は交通を断たれた場所にも比較的自由に立ち入ることができるためです。そして、警察官が立会っていることから、一般隔絶地遺言では家庭裁判所による確認手続きは不要です。
なお、この形式による遺言は、遺言者について隔離された状態が解かれ、普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、その効力を生じません。
○船舶隔絶地遺言(在船者遺言:民法978条)
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。この場合、遺言者が遺言を作成し、または誰かに代筆してもらい、遺言者と筆者、立会人および証人が、各自遺言書に署名押印を行います。
船舶に乗船して陸地から離れた人のための遺言の方式で、船員であるか乗客であるかは問いません。その際、自筆証書遺言をすることが可能な場合であっても、この方式によって遺言をすることもできます。また、船長等が立会っていることから、船舶隔絶地遺言では家庭裁判所による確認手続きは不要です。
なお、この形式による遺言は、遺言者が日本国内に帰還し、または日本の領事が駐在する外国の領土に上陸して普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、その効力を生じません。