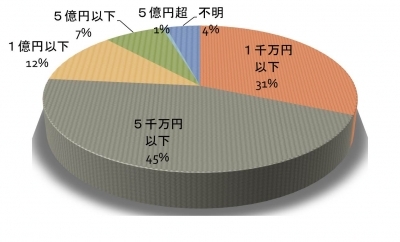遺言の文言で、「相続させる」と「遺贈する」では大違い?
これまで「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」についての解説をしてきましたが、この3種類の遺言を普通方式の遺言といいます。
民法967条では「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。」とされており、上記の3種類の遺言を原則としながらも、遺言者の状況により、以下で説明する特別方式の遺言をすることが認められています。
特別方式の遺言は、死亡の危機が目の前に迫っている場合(危急者遺言)と、交通が遮断された場所にいる場合(隔絶地遺言)に認められます。危急者遺言には「死亡危急者遺言」と「船舶遭難者遺言」、隔絶地遺言には「伝染病隔離者遺言」と「在船者遺言」の、それぞれ2種類があります。今回は、このうちの「死亡危急者遺言」について説明します。
○死亡危急者遺言(一般危急時遺言:民法976条)
病気やケガで死亡の危機が目前に迫っているため、自ら遺言を書いたり署名押印をしたりすることができない場合に認められる遺言の方式です。民法976条1項では、死亡危急者遺言の方式について、以下のように定めています。
(1)疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言を
しようとするときは
(2)証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を
口授して、これをすることができる
(3)この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記
して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ
(4)各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名
し、印を押さなければならない
※( )内の番号は便宜的につけたもので、条文にはありません。
つまり、簡単に言えば、公正証書遺言における公証人の役割を三人の証人のうちの一人が担い、他の二人以上の証人がそれに立会うという方式で、その際に証人となる資格や、口のきけない者や耳の聞こえない者が遺言をする方法についても、公正証書遺言に準じます(第30首参照)。ただし、公正証書遺言とは異なり、遺言者自身は遺言書に署名押印する必要はありません。一方、証人は必ず自ら署名押印する必要があります。
ちなみに、この遺言は死亡の危急時のみにすることができますが、客観的に医師より危篤状態と診断されている必要まではなく、疾病その他相当の事由があって遺言者自身が死亡の危急に迫っていることを自覚している場合にも、することができます。ただし、遺言者が死亡の危険性を単に予想、空想したり、主観的に思い込んだりしただけでは、することができません。
余談ですが、このような危急者遺言の方式を認めるかどうかについては、明治時代に民法が作られた際に激しい議論があったそうです。賛成派の意見は、西洋では遺言は若くて元気なときに準備しておくという慣習があるのに対し、日本ではそのような慣習がなく、臨終に際して枕元で親族を集めて遺言をすることが多いので、必要性があるというものです。これに対し、反対派の意見は、そのような方式の遺言では遺言者の真意が確保しにくい。遺言者が口頭で遺言をしたいのであれば、公証人を呼んで公正証書遺言を作成してもらえばいいというものでした。そして、決議をしたら賛成と反対が同数で、議長の一票により採用されたという歴史があります。
そこで、遺言者の真意を確保するために、この形式により行われた遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の一人または利害関係人から家庭裁判所に請求してその「確認」を得なければ、その効力を生じない(同条4項)とされました。そして、家庭裁判所は、その遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができません(同条5項)。
ただし、遺言の「確認」は、遺言者の真意に基づくことの確認であり、遺言自体が有効であるかを判断するものではないため、遺言の内容に不満がある者は、確認が終わった後でも、民事訴訟で遺言の無効を争うことができます。
また、家庭裁判所での「確認」は、遺言者の死亡後に行う「検認」(第20首参照)とは別の手続きです。したがって、危急時遺言の「確認」を受けた後でも、遺言者の死亡後には別途「検認」の手続きを行う必要があります。
なお、特別形式による遺言は、あくまで例外的に認められる方式ですので、遺言者の容態が回復するなど、普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、その効力を生じません。