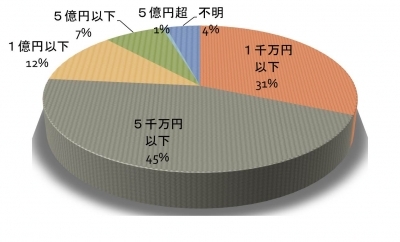「遺言信託」の費用は遺産から差し引けるか?
これまでに自筆証書遺言と公正証書遺言の解説をしてきましたので、今回は秘密証書遺言について解説をします。秘密証書遺言は、遺言者が自ら作成し、または他人に代筆してもらった遺言書に署名押印をした上で封筒に入れて封印し、その封筒を公証人と二人以上の証人の前に提出し、本人の遺言である旨の確認を受けるものです。民法970条1項では、以下のように定めています。
1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3.遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書で
ある旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言
者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
ここで注意しなければならないのは、秘密証書遺言を公証人に提出する際には、「その筆者の氏名及び住所を申述すること」です。封筒の中に入れる遺言書は、遺言者が自筆または自らパソコンやワープロ打ちで作成したものでも、遺言者から依頼を受けた遺言者の友人や弁護士・行政書士が代書したものでも構いませんが、代書の場合には、筆者として遺言者自身ではなく代書した人の氏名及び住所を申述する必要があります。これは、代書した人が市販の遺言書の書き方の文例を参照し、氏名の部分だけを置き換えてワープロ打ちして印字して遺言書を作成した場合も同様であり、筆者としてその人の氏名及び住所を公証人に申述しなかった場合、その秘密証書遺言は無効となります(判例)。
なお、秘密証書遺言の際の証人についても、民法974条(第30首参照)が適用されますので、未成年者、遺言者の推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、証人にはなれません。ところが秘密証書遺言では、文字通り遺言の内容は秘密です。したがって、証人が受遺者になっているのかどうかは、遺言者や筆者にしかわかりません。しかし、判例では、それでも、受遺者は自己が受遺者となる遺言の証人にはなれないとしています。
ただし、証人等の問題で秘密証書遺言としては無効になる場合でも、その遺言書が自筆証書遺言としての要式を備えている場合には、自筆証書遺言として有効となります。
ちなみに、推定相続人や受遺者は、秘密証書遺言の証人にはなれませんが、「筆者」になることは可能です。しかし、そのような立場の人が筆者となって秘密証書遺言が作成されますと、他の相続人等から「無理に本人に作らせた」などと疑いの目で見られる可能性がありますので、避けた方が無難でしょう。
ところで、秘密証書遺言で筆者の氏名及び住所を申述させる理由は、後日、遺言について争いになった場合に、その筆者を尋問する便宜からです。その意味では、筆者を中立的な立場でかつ専門家である弁護士や行政書士などに依頼するのも、遺言の信頼性を高める上で、ひとつの方法といえそうです。
秘密証書遺言のメリットは、以下の通りです。
1.その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできる。
2.遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができる。
3.体力の低下で全文の自書は困難だが、署名はできる場合にも作成可能
(ただし、公正証書遺言とは異なり、必ず遺言者自身の署名が必要)。
4.パソコンやワープロで作成する場合には、文案の推敲や修正が容易
(ただし、作成後に訂正する場合、自筆証書遺言の訂正方法と同様)。
5.公証人手数料が、遺産の額にかかわらず定額(11,000円)であること。
一方、秘密証書遺言のデメリットは、以下の通りです。
1.自筆証書遺言と比較すると、手間と費用がかかり、証人も必要となる。
2.公証人は遺言書の内容をチェックできないため、法的な不備により遺言が
無効になってしまう危険性がある。
3.原本は公証役場には保管されないので、紛失や隠匿の危険性がある。
4.自筆証書遺言と同様に、遺言者の死後は検認手続が必要。
5.パソコンやワープロで作成する場合、遺言者の気持ちを伝えるという機能
では、自筆証書遺言と比較すると劣る。
最後に、秘密証書遺言の作成件数は年間100件程度(公正証書遺言は年間約8万件)と、非常に少ないのが現状です。しかし、遺言者の状況によっては活用できる制度ですし、パソコンの普及に伴い、今後は少しずつ増えてくるかもしれません。